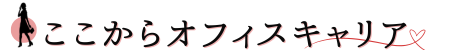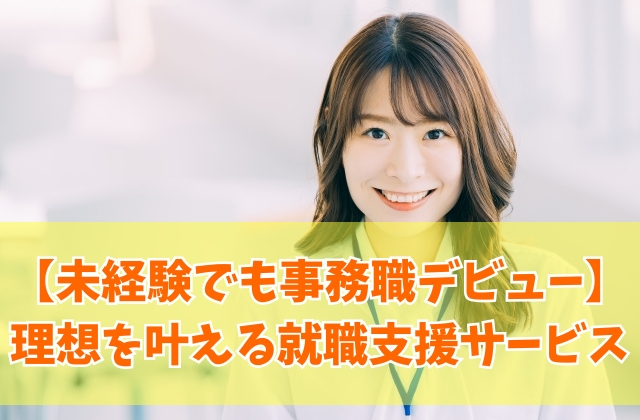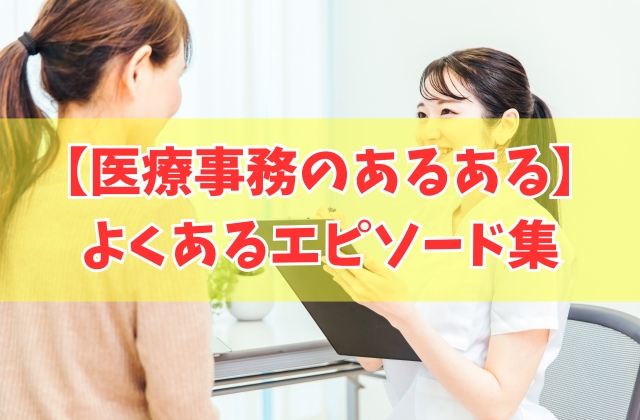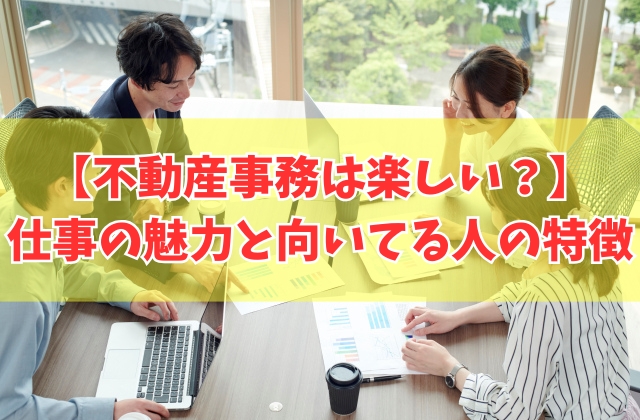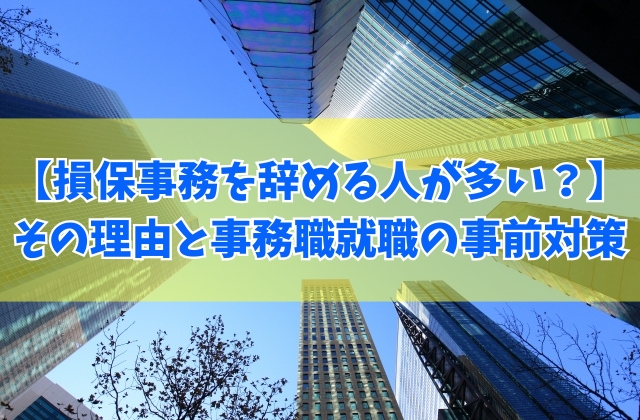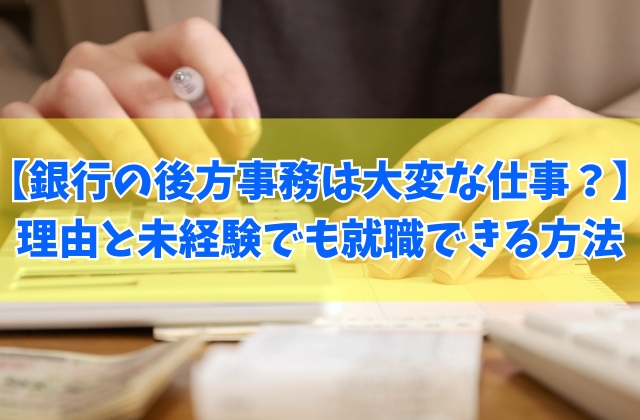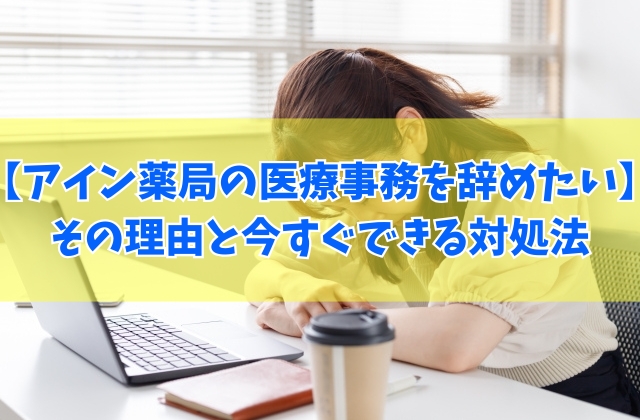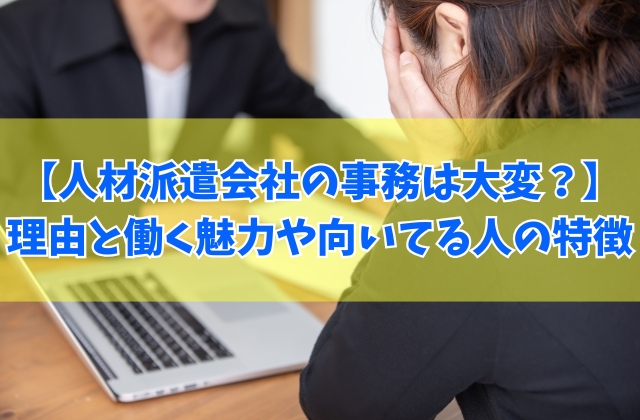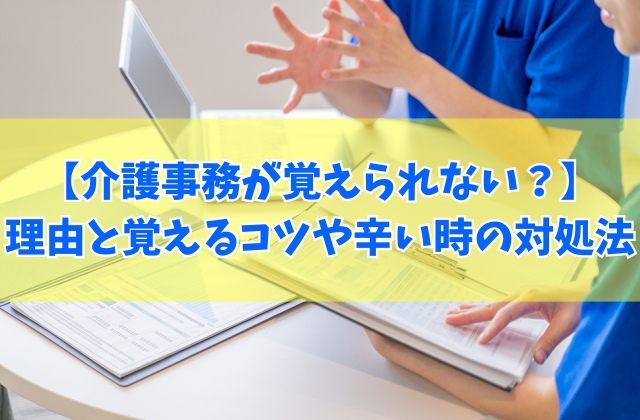
「介護事務の仕事が覚えられない…どうすれば?」
「覚えるコツはある?どうしても辛いときはどう対処すればいい?」
介護事務として日々の業務に向き合っている中で、「何度やっても覚えられない」と感じていませんか?
制度や書類の多さに圧倒され、ミスを恐れて手が止まる——そんな経験を重ねると、自分には向いていないのではと落ち込んでしまう方も少なくありません。
けれど、「介護事務の仕事が覚えられない」と悩むのはあなただけではなく、多くの人が通る道です。
この記事では、難しくて辛いと感じる理由を丁寧に紐解きながら、無理なく乗り越えるための具体的な対策や対処法をご紹介します。
自信を取り戻す一歩を、ここから踏み出してみませんか?
- 業務が複雑でも、優先順位をつければ覚える負担が軽くなる
- 苦手な点はメモや質問で補い、少しずつ経験を積み重ねることが大切
- つらいときは転職支援やエージェントなど外部の力を借りる選択肢も有効
介護事務の仕事が覚えられないと悩む声は珍しくありませんが、大切なのは一人で抱え込まないことです。
段階的に覚え、相談できる環境をつくることで、着実に前へ進めます。焦らず、今の自分に合った働き方を見つけましょう。
そして、新しい仕事・職場を探すなら派遣会社の複数登録も視野に入れてみてください。
たとえば、ランスタッドやテンプスタッフ、アデコなど、サポート体制が充実している派遣会社では、あなたの希望や適性に合った仕事を紹介してもらえます。
派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
介護事務の仕事が覚えられないと感じる6つの理由と対策
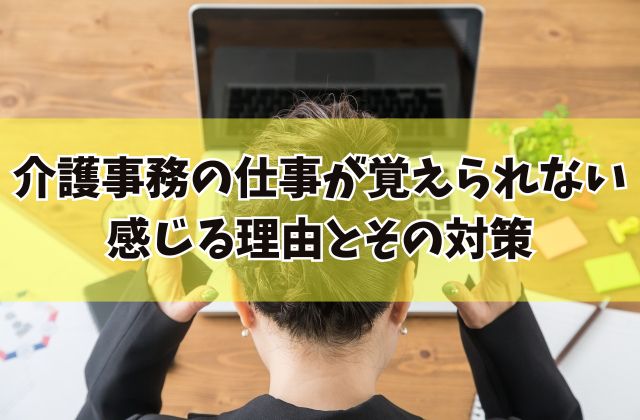
介護事務として働き始めたものの、「介護事務の仕事が覚えられない」と感じて悩んでいる人は少なくありません。
制度の複雑さや書類作成の多さに戸惑い、日々の業務が重く感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、つまずくポイントには共通した原因があり、それぞれに有効な対策があります。
ここでは、仕事が覚えられないと感じる代表的な6つの理由と、その乗り越え方について具体的に解説します。
【理由1】覚える制度や計算が多すぎて混乱してしまうから
介護事務の仕事を始めて最初につまずきやすいのが、「覚えることの多さ」に圧倒されてしまうことではないでしょうか。とくに制度や計算に関しては、知識ゼロの状態から一気に情報を詰め込もうとすると、頭がパンクしそうになります。
介護報酬の仕組みは、単なる数字の足し引きでは済みません。たとえば、基本単位に地域ごとの区分を掛けて、そこに加算・減算の条件が細かく加わるという流れです(出典:地域区分について)。
実際、「訪問介護(30分以上1時間未満)」では404単位が基本ですが、地域区分や人件費率、加算条件によって金額は変動します(出典:参考資料)。慣れるまでは「なんでこの金額になるの?」と戸惑う場面が続くのも無理はありません。
加えて、制度そのものが頻繁に見直されるため、最新のルールを追いかけ続ける必要もあります。何を、どこまで、どう覚えればいいのかが見えにくく、混乱や不安につながりやすいのです。
とはいえ、最初からすべてを完璧に覚えようとしなくても大丈夫です。まずは業務でよく使うサービスや計算パターンから少しずつ押さえていくこと。そして、計算支援ソフトや先輩のチェックを活用することで、安心して慣れていくことができます。苦手意識を抱えたまま無理に進めるよりも、自分に合ったペースで少しずつ「分かる」を積み重ねていく方が、結果的には近道になるのです。
【理由2】パソコンや書類操作が苦手で手が止まるから
「パソコン作業が苦手で、思うように手が動かない……」。介護事務の現場では、そんな不安を抱えている方が少なくありません。とくに事務職が初めての人にとっては、マウスの使い方ひとつで時間がかかってしまったり、Excelでの作業が複雑に感じたりして、なかなか前に進めないことがあります。
実際、介護事務ではWordやExcelを使った記録の整理や、請求書類の作成が日常的に求められます。請求業務では専用ソフトを使う場面もありますが、基本的な操作はパソコンに慣れていないと時間ばかりが過ぎていき、ミスにつながることも。たとえば利用者の基本情報をExcelにまとめる場面でも、「セルって何?」「入力しても文字がズレる」といったつまずきがよく起こります。
ただ、だからといって「自分は向いていない」と落ち込む必要はありません。誰もが最初は戸惑うものですし、今は職場で簡単なマニュアルを用意していたり、無料で使える学習動画も豊富にあります。最初は「コピー&貼り付け」だけでもいいのです。毎日少しずつ触れることで、自然とできることが増えていきます。
苦手意識があると、仕事そのものまで怖くなってしまいます。でも、本当に大切なのは「完璧を目指すこと」ではなく、「昨日より1つ進めること」。少しずつでも、自分のペースで成長していけば大丈夫です。
【理由3】レセプト業務が難しくて時間がかかってしまうから
介護事務のなかで「いちばん大変」と感じる人が多いのが、月初に行うレセプト業務です。利用者ごとのサービス実績を集計し、請求書と明細書を作成して国保連へ提出するこの作業は、正確さとスピードの両方が求められます。
ミスがあると“返戻(へんれい)”と呼ばれる修正対応が必要になり、やり直しになることもしばしば(出典:返戻レセプト・各種帳票について)。しかも制度のルールが定期的に変わるため、毎月同じ手順では済まず、細かい変更に気づけないと見落としにつながります。
たとえば、請求対象となる加算の条件が見直されたり、サービスコードが変更されたりするだけでも混乱の元になります(出典:報酬算定構造・サービスコード表等)。
小規模な事業所では、レセプトをひとりで担当しているケースも多く、「ほかの仕事が進まない…」と感じている人も少なくありません。とくに慣れないうちは、どこから手をつけていいかわからず、時間だけが過ぎてしまうことも。
ただ、この業務を通して制度の仕組みや加算の意味が理解できてくると、自然と処理スピードも上がってきます。最初は時間がかかって当然です。焦らず、チェック体制やマニュアルを整えながら、少しずつ身につけていけば大丈夫です。実はレセプトをしっかり覚えることが、介護事務としての大きな自信につながるのです。
【理由4】月末月初の請求業務が一気に集中して負担が大きいから
介護事務に携わる方なら、月末月初がどれだけ忙しいか、身にしみて感じているのではないでしょうか。特に1日から10日にかけては、レセプト請求の作成と提出、利用者への請求書発行が同時進行になり、気が抜ける暇がありません。
一番の負担は、すべての作業が短期間に集中することです。前月分のサービス実績を確認しながらデータを打ち込み、ミスがないか確認し、国保連に電子請求。そのうえで利用者やご家族に送る請求書の処理も行わなければならない。これらを数日で終わらせるのは、正直プレッシャーが大きいです。
特に人員が限られている小規模施設では、「他の仕事に手が回らない」と感じる場面も多いでしょう。実際、レセプトの締め切りを意識しながら、他業務と並行して進めるのは簡単ではありません。でも、この時期を毎月しっかり乗り切ることで、業務の全体像がつかめるようになり、少しずつ自信にもつながっていきます。
最初から完璧にやろうとしなくても大丈夫です。大切なのは、請求作業の“ピーク”を見越して、前倒しで準備を進めておくこと。スケジュールの組み方ひとつで、気持ちにゆとりが生まれ、月初の負担もぐっと軽くなります。
【理由5】職場の人手不足で教えてもらえず戸惑うから
誰かに頼りたくても、職場にその余裕がない—。そんな状況に身を置いている介護事務の方は少なくありません。教えてほしくても、周りは自分の仕事で手一杯。声をかけるタイミングすらつかめず、結局「わからないまま」になってしまう。その繰り返しが、「仕事が覚えられない」という不安や焦りを生むのです。
介護業界は慢性的な人手不足が続いており、教育係をつける余裕すらない事業所も多いのが実情です(出典:介護人材確保の現状について)。特に中小規模の施設では、事務と現場スタッフの兼任も少なくなく、教える側にも時間と心の余裕がありません。
介護労働安定センターの調査でも、介護職全体の離職理由の上位に「サポート不足」や「人間関係の希薄さ」が挙がっており、特に「介護従事者が直前の介護の仕事を辞めた理由」の第1位が「職場の人間関係に問題があったため(34.3%)」で、前年比でも増加傾向にあり、この問題は決して珍しいことではないとわかります(出典:令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について)。
「聞きたくても邪魔になりそうで言い出せない」「メモを取ろうにも内容があいまいすぎる」──そう感じながらひとりで悩み続けていると、自信もやる気も失われてしまいます。
でも、あなたが悪いわけではありません。覚えられないのは“努力が足りない”のではなく、“教わる環境が整っていない”だけなのです。必要なのは、遠慮せずに「少しだけでも時間をとってもらえますか?」と伝える勇気と、教えてもらえなかったことを責めず、自分の手で「覚え方」を作っていく工夫です。
次の章では、そうした厳しい職場環境でも前向きに乗り越えるための具体的なコツをご紹介します。焦らなくても、少しずつ確実に進めば大丈夫です。
【理由6】介護保険制度が頻繁に変わり追いつけないから
せっかく覚えたと思った矢先に、また制度が変わる。介護事務の現場では、そんなため息が毎年のように聞こえてきます。「どこが変わったの?」「今まで通りじゃダメなの?」と不安になるのは当然です。
介護保険制度は、基本的に3年ごとに見直しがあり、その間にも細かな変更がしれっと加えられることがあります(出典:介護保険制度の見直し)。たとえば2024年度は4月の報酬改定を皮切りに、6月や8月にも個別のサービスごとに変更が入りました。訪問看護や通所リハビリなど、業種によっては報酬単価や加算条件まで変わっており、現場としては“何が最新か”を追うだけで手いっぱいになることも。
さらに今回は、介護報酬の全体引き上げ(+1.59%)に加え、複数あった処遇改善加算の一本化が実施され、計+2.04%もの影響が出ました(出典:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料)。この数字だけを見ても、どれだけ事務作業に変更が加わったかが伝わるはずです。
こういった制度改定が繰り返されるなかで、常に「覚え直し」が求められるのはつらいもの。とくに一人事務や小規模施設では、情報をキャッチするのもひと苦労です。でも、だからこそ大切なのは「すべてを網羅しよう」とせず、まずは改定の時期とポイントを押さえること。具体的には、たとえば「2024年4月改定」「6月一部見直し」といったカレンダーを作っておくだけで、ずいぶん混乱が減ります。
情報に追われるより、自分から「必要な情報だけ拾いにいく」姿勢でいれば、制度の波にのまれずに済みます。覚えられないのではなく、変わりすぎて当然なのだと、まずは自分にそう言ってあげてください。
覚えられない人必見!介護事務の仕事を覚えるコツ5つ
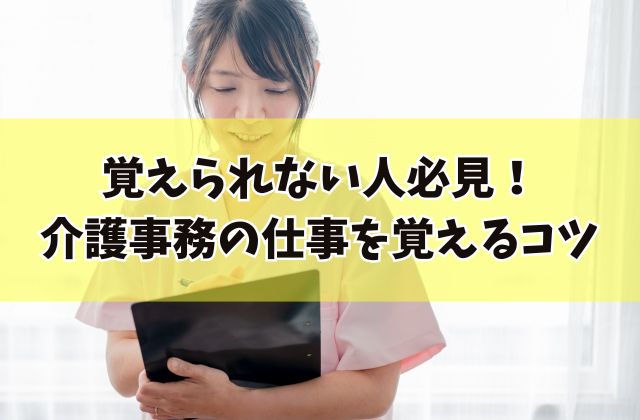
介護事務の仕事は、覚えることが多くて混乱したり、自信をなくしてしまう方も多いものです。
制度や請求のルール、パソコン操作など、一つひとつを積み重ねるのが大変に感じることもあるでしょう。
そんな中でも前向きに乗り越えるための方法があります。
ここでは「覚えられない人必見!介護事務の仕事を覚えるコツ5つ」と題して、実践しやすい工夫や意識の持ち方を具体的にご紹介します。
【コツ1】業務に優先順位をつけて覚えるようにする
介護事務の仕事は、やることが多くて頭の中がごちゃごちゃになりやすいものです。そんなときに役立つのが、「今やるべきこと」を明確にする習慣です。なんでも一気に覚えようとするのではなく、まずは目の前で必要なことから手をつけていく。それだけで、驚くほど気持ちが落ち着きます。
たとえば、月初にレセプト請求の締切が迫っているなら、計算や入力業務を最優先に。次に確認業務、そして空いた時間で書類整理やマニュアルの見直しなどを進めていきます。頭の中だけで管理しようとすると混乱しやすいので、紙に書き出したり、スマホのメモ機能を使って「今日やる3つのこと」を決めておくのがおすすめです。
こうした小さな“優先づけ”を繰り返すことで、自然と覚える順序も整っていきますし、仕事全体の流れもつかみやすくなります。「覚えられない」のではなく、「どこから手をつければいいかわからない」だけ。順番をつけるだけで、迷いが一つ減り、心にも余裕が生まれます。
【コツ2】メモを習慣化して復習する時間を作る
介護事務の仕事を覚えようとしても、次々と新しい情報が入ってきて、頭の中が整理できない。そんなときこそ、「書いて残す」ことが力になります。単にメモを取るだけではなく、それを“見返す時間”を日課にすると、少しずつ仕事が自分の中に落とし込まれていくのを実感できるようになります。
カナダのウォータールー大学の研究では、学んだことを翌日に10分、1週間以内に5分ほど復習するだけで、記憶の定着率が大幅に向上するという結果が出ています。この理論は介護事務にもぴったりです。たとえば「請求業務の順番」や「ミスしやすい入力ルール」などをメモにまとめ、寝る前や週末の少し空いた時間に見返すだけでも、自然と頭に残ります。
実際に、終業後の5分で「今日やったこと・つまずいたこと・次に注意すること」をノートに書いている人は、忘れにくくなるだけでなく、自分の成長にも気づきやすくなったと感じているそうです。
忙しい毎日でも、10分だけ自分のために時間を使ってみてください。その積み重ねが「覚えられない毎日」を「自分で進んで覚えられる感覚」へと変えてくれます。焦らず、今日の一歩から始めてみましょう。
【コツ3】わからないことはすぐ先輩に質問する
仕事でつまずいたとき、「こんな初歩的なこと、今さら聞いていいのかな……」と迷ってしまうことはありませんか?でも、介護事務のように制度やルールが複雑な仕事ほど、早めに質問して不安を解消することが何よりの近道です。
実際、介護業界では「分からないことを素直に聞ける人ほど、伸びる」と言われています。何となく進めてあとから間違いに気づくよりも、早めに確認しておくことで、無駄な手戻りも防げます。
もちろん、ただ「わかりません」と投げかけるだけでは、相手も戸惑ってしまいます。たとえば「ここまで自分で調べたのですが、この点だけ自信が持てなくて…」と前置きすれば、先輩も状況をつかみやすく、教える側の負担もぐっと軽くなります。
それでも忙しそうで声をかけにくいときは、「今10分ほどだけ、お時間いただけませんか?」と時間を区切ってお願いしてみてください。相手にとっても答えやすく、自分も聞きやすくなります。
質問することは恥ずかしいことではありません。むしろ、「覚えられない」と悩む人ほど、疑問を抱いたタイミングで誰かに助けを求める姿勢が、あとで大きな力になります。小さな質問が積み重なった先に、「仕事がわかってきた」という実感が待っています。焦らず、安心して、声を出してみてください。
【コツ4】チェックリストや手順書を作って整理する
「何から手をつければいいのか分からない」「覚えたつもりでも抜けがある」——介護事務の仕事でこんなモヤモヤを感じる場面は少なくありません。業務の流れを頭の中だけで整理しようとすると、どうしても限界があります。そんなときは、自分専用のチェックリストや手順書を作ってみるのが一番の近道です。
たとえば、「月末のレセプト作成」というひとつの業務でも、細かく分けると「利用実績の確認」「加算項目の入力」「請求書の出力」など、やるべきことは山ほどあります。それを一つひとつ紙に書き出してチェックできるようにすると、「今どこまで進んだか」が一目でわかるようになり、うっかりミスも減っていきます。
また、パソコンに打ち込んで簡単な手順書にしておくのもおすすめです。慣れないうちは、「何を」「どの順番で」「どうやるか」が自分でもあやふやになりがちですが、手順書があるだけで作業がずっとスムーズになります。忙しい現場の中でも、迷わず手が動くようになる実感が出てくるはずです。
一度作ってしまえば、それは“未来の自分へのメモ”になります。「あのときの自分、よくまとめてくれてたな」と、あとから感謝することになるかもしれません。
【コツ5】少しずつ実際に手を動かして慣れていく
正直、介護事務の仕事は、マニュアルを読むだけでは身につきません。制度や処理の流れを頭で理解しても、実際にやってみると「あれ?ここどうするんだっけ?」と戸惑う場面が出てきます。でも、それは自然なことです。
実務は“体験してこそ身につく”ものです。たとえば、初めてレセプトの入力にチャレンジしたとき、最初の一歩はすごく緊張したとしても、一回やってみるだけで手順のイメージが掴めたという声は多くあります。完璧を目指さなくていいので、まずは「1件だけやってみる」くらいの気持ちで触れてみると、次から不思議とスムーズに手が動くようになるんです。
厚生労働省の介護報酬改定なども年々変化しますが、それに柔軟に対応できている人たちも、最初は皆「分からない」から始めています。職場で先輩がやっていることをそばで見て、できそうなところから少しずつ真似ていく。それだけで、気づけば「できること」が増えていきます。
最初の数週間は「これ本当に自分にできるのかな…」と不安になるかもしれません。でも、焦らなくて大丈夫です。自分の手で覚えたことは、あとから必ず大きな力になりますから。
覚えられない介護事務の仕事でも楽しいと感じる瞬間ややりがい
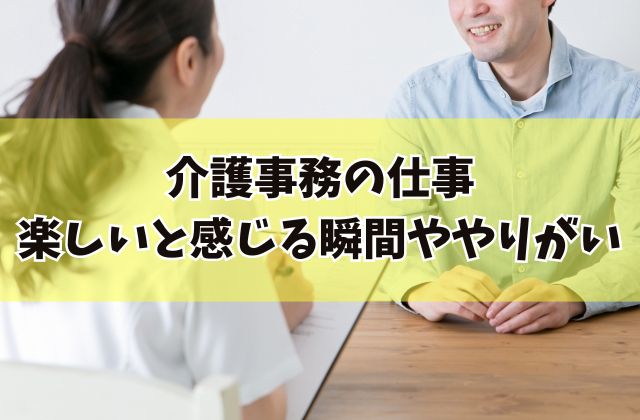
介護事務の仕事は覚えることが多く、最初は誰でもつまずきます。
それでも日々の業務を通じて少しずつ理解が深まると、思わぬ場面で喜びややりがいを感じられるようになります。
そこでここからは、覚えられない介護事務の仕事でも楽しいと感じる瞬間ややりがいについて触れていきます。
迷いや不安がある方にも、前向きな気持ちが芽生えるきっかけになるはずです。
【楽しさ1】利用者さんや家族から感謝されるとやりがいを感じる
介護事務の仕事は表に出にくく、評価されづらいと感じることもありますが、ときに思いがけず届く「ありがとう」のひと言が、心の芯に染み渡ることがあります。
たとえば、保険証の確認や請求明細の説明で困っているご家族に寄り添ったとき、「本当に助かりました」と頭を下げられた瞬間。自分のしてきた仕事が誰かの安心につながっていると実感できた、その日一日は不思議と疲れを感じませんでした。
レセプトや書類整理のような地味な作業も、誰かの暮らしを支える一部だと思えば、見え方が変わってきます。決して目立つ役割ではないけれど、だからこそ、ふとした場面で感謝の言葉を受け取ると、胸の奥があたたかくなります。
介護事務という仕事は、数字とにらめっこするだけの職種ではありません。人と人のつながりの中にいる、かけがえのない役割です。ほんのひとことの「ありがとう」に支えられて、今日もまた前を向ける——そんな仕事です。
【楽しさ2】請求業務が無事終わると安心して達成感がある
介護事務の仕事の中でも、月末月初に立ちはだかる請求業務は、ひとつの“山”のような存在です。書類を突き合わせ、入力ミスを確認し、レセプトを提出するまでの数日間は、息をつく間もないほど忙しい。
けれど、その作業が終わった瞬間、ふっと肩の力が抜けるような感覚とともに、「ああ、ちゃんと終わらせられた」と自分に小さくガッツポーズしたくなる達成感があります。
請求内容に不備がなければ、事業所の収入に直結するため、責任は大きいです。だからこそ、月初に返戻がなかった日は、本当にほっとしますし、「ちゃんとできたんだ」と自分を認めてあげられる大事な瞬間です。スタッフに「今回スムーズだったね」と声をかけられることもあり、裏方の努力が報われたようで報酬以上の喜びを感じることもあります。
慣れないうちは不安のほうが勝ちますが、ひとつ山を越えるたびに「次も頑張ろう」と思える。それが、介護事務を続けていく力になっていくのだと感じます。
【楽しさ3】介護現場を裏で支えると使命感がわく
介護事務の仕事は、表には出ません。でも、だからこそ「現場を支えているのは自分たちだ」と感じたとき、大きなやりがいが生まれます。請求ミスひとつで施設の運営に響くほど、裏方の責任は実はとても重たいんです。
たとえば月末のレセプト業務。提出期限に追われながらも、現場スタッフが安心して働けるように、書類をひとつずつ丁寧に整える。その過程で「これがうまくいけば、現場は滞りなく回る」と思える瞬間があります。誰かの仕事を支えるという意識は、日々の業務をただの“作業”から“使命”に変えてくれます。
「ありがとう」の言葉を直接もらうことは少ないかもしれません。でも、現場がスムーズに動いているときこそ、陰で事務がしっかり支えている証拠。そんな実感があるからこそ、「地味だけど、この仕事には意味がある」と感じるのです。
覚えられないのは自分だけ?介護事務に向いている人の特徴

介護事務の仕事がうまく覚えられず、自分だけがつまずいているように感じる方は少なくありません。
しかし実際には、多くの人が同じように壁にぶつかっています。
では、どんな人がこの仕事に向いているのでしょうか?覚えられないのは自分だけ?介護事務に向いている人の特徴を知ることで、不安を少しでも軽くするきっかけになるかもしれません。
【特徴1】人を支える仕事にやりがいを感じる人
介護事務の仕事は、表に立つことは少なくても、誰かを支えることが好きな人にとっては、やりがいを実感しやすい仕事です。
なぜなら、書類を整えたり請求を処理したりといった“裏方の仕事”が、介護現場の土台になっているからです。実際に、介護職全体では約84%の人が「やりがいを感じている」という調査結果もあり、事務職であっても例外ではありません。
たとえば、レセプトをミスなく仕上げた月の終わり、家族から「毎月ありがとうございます」と声をかけられた経験がある方もいます。そのひと言に、何日分もの疲れがふっと軽くなる——そんな瞬間があるのが、この仕事の良さです。
「もっと喜んでもらいたい」と感じたら、受付でのちょっとした声かけを意識してみるのもおすすめです。仕事の幅が広がるだけでなく、人とのつながりも自然と深まります。それがまた、次の日の頑張る力になります。
【特徴2】締め切りをきちんと守れる人
介護事務の仕事に向いている人の共通点の一つは、「決められた期限を守ることが当たり前になっている人」です。
介護報酬の請求業務では、レセプト提出の締切が毎月決まっており、少しでも遅れると事業所の入金スケジュールにズレが生じ、最悪の場合、経営にも影響が出てしまいます。現場では、月初から10日までの期間に一気に作業が集中するため、「明日やろう」が通用しません。
ある介護施設で働く事務員の方は、「締切の2日前には全てを仕上げておくよう心がけています。焦るとミスが増えるし、利用者さんの生活に関わるお金なので妥協はできません」と話していました。これは、事務職という立場であっても、仕事が福祉の現場とつながっていることを実感できる瞬間でもあります。
スケジュール管理に自信がある方や、日頃からToDoリストをこまめに確認しているような方であれば、介護事務の現場でも無理なく馴染めるはずです。信頼は「締切を守ること」から始まる、そんな空気の中で働きたい人には、ぴったりの職場かもしれません。
【特徴3】細かい手順を丁寧に進められる人
介護事務の仕事には、細やかな確認と正確さが何より大切です。特にレセプトや各種請求書の作成では、数字や用語の一つひとつにミスが許されません。だからこそ、地道に確認作業を重ねられる人は、とても頼られる存在になります。
実際、現場で活躍している介護事務の方々の多くは、「確認作業が苦にならない」と話しています。ミスがあると請求先にも迷惑がかかるため、一つのチェックを何度も繰り返すことも珍しくありません。でも、そこにやりがいを感じる方も多いのです。
たとえば、「チェックリストを活用して、どんな忙しい日でもミスを防ぐのが日課」という声も見られます。こうした日々の工夫が、安心して任せてもらえる力につながっているのでしょう。
「介護事務の仕事が覚えられない」と不安になるときこそ、手順を一つひとつ丁寧にこなす習慣が自信につながります。派手さはなくても、誠実に積み重ねる姿勢が、この仕事に向いている最大の資質なのかもしれません。
介護事務の仕事が覚えられなくて辛いときの適切な対処法5選
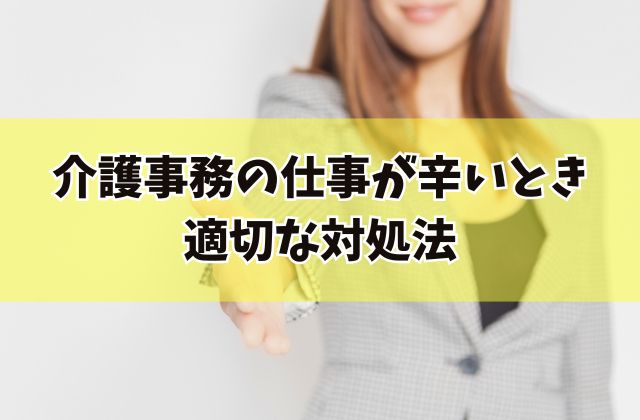
慣れない介護事務の仕事に追われ、「向いていないのかも」と落ち込んでしまう人は少なくありません。
覚えることの多さや業務の重なりに気持ちが折れそうになる場面もあるでしょう。
そんな時こそ、視点を変えることで心が軽くなるヒントがあります。
ここでは、介護事務の仕事が覚えられなくて辛いときの適切な対処法5選をまとめました。
今すぐ試せる具体的な対応策を紹介します。自分を責めすぎず、ひと呼吸おいて読み進めてみてください。
【対処法1】信頼できる人に悩みを相談する
介護事務の仕事が思うように覚えられず、気づけばひとりで悩みを抱え込んでいる——そんな状況が続くと、心も体もすり減ってしまいます。けれども、誰かに話を聞いてもらうだけで、肩の荷がふっと軽くなることがあります。
仕事の手順や制度の複雑さに混乱しても、「それ、私も最初は分からなかったよ」と言ってくれる同僚がそばにいるだけで救われるものです。実際、厚生労働省の調査でも、職場内で信頼関係が築けている人ほど、仕事への不安やストレスが減る傾向があるとされています。
「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮する必要はありません。むしろ、自分の気持ちを正直に伝えることが、前に進む第一歩になります。もし職場に話しづらいと感じるなら、外部の相談窓口やキャリアカウンセラーを頼るのも立派な選択肢です。
ひとりで抱えず、まずは声に出してみてください。ほんの一言から、状況はゆっくり動き出します。
【対処法2】定期的にしっかり休んで身体をリセットする
長時間パソコンに向かって作業していると、頭がぼんやりしてミスが増えたり、入力の手が止まりがちになったりしますよね。そんなときは、思い切って少し手を止めてみましょう。
実は、たった10~15分の短い休憩(“マイクロブレイク”とも呼ぶ)でも、集中力や気力が約0.35ポイント向上するという研究報告があります。介護事務の仕事はとにかく細かくて、請求業務や制度対応など、気を張り続ける場面が多いもの。ずっと気を張っていると、知らないうちに心も体も疲れてしまいます。
たとえば、20~30分作業したら、席を立って軽くストレッチをする。深呼吸しながらお茶を一杯飲む。それだけでも、頭の中がリセットされて、次の業務に前向きに向き合える余裕が生まれます。疲れを無理に押し殺して続けるより、定期的にリズムよく休んだ方が、結果的に早く正確に仕事をこなせることもあるのです。
「介護事務の仕事が覚えられない」と感じているなら、まずは日々の働き方を少し見直して、休む時間をスケジュールに組み込んでみてください。完璧を目指さなくて大丈夫。あなたが心地よく働けるリズムを見つけていきましょう。
【対処法3】自己分析をして働き方や向いている仕事を見直す
「何度やっても覚えられない…」と感じるときは、自分を責めるより、いったん立ち止まって考えることが大切です。
もしかすると、いまの仕事が自分の得意分野と少しズレているのかもしれません。焦る気持ちは当然ですが、そういうときこそ「自分には何が合っているのか」「どんな働き方なら続けやすいのか」を見直すチャンスです。
たとえば、人とのやりとりが好きな人は電話対応や来客応対で力を発揮できるかもしれませんし、細かい数字や処理が得意なら、レセプト業務を丁寧にこなすことができます。反対に、パソコン操作に苦手意識があるなら、入力作業のボリュームが多い職場はしんどく感じるかもしれません。
自分の強みや苦手を洗い出してみると、「あの業務がしんどかったのは自分に向いていなかっただけなんだ」と気づくこともあります。自分自身をよく知り、向いている方向に少し舵を切るだけでも、日々の負担はぐっと軽くなります。迷ったら、ノートに書き出してみることから始めてみてください。
とはいえ、自分一人で自己分析を進めるのは簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【対処法4】派遣会社に登録して自分に合う職場を探してみる
「このまま今の職場で頑張るしかない」と思い込んでいませんか?でも実は、介護事務の仕事に自信をなくしているときこそ、派遣会社に相談するという選択が有効です。なぜなら、派遣会社は“あなたに合う”働き方を一緒に考えてくれるからです。
派遣の介護事務求人には、例えば「残業なし」「ゆっくり教えてくれる職場」「子育てと両立OK」など、条件を細かく指定できる案件が多くあります。特に《かいご畑》や《キララサポート》など、介護業界に強い派遣会社は、実際の職場の雰囲気や指導体制を把握していて、希望に沿ったマッチングをしてくれます。
ある派遣スタッフの方は、「前の職場では毎日ついていけず泣いていましたが、派遣で環境を変えたら、少しずつ仕事が楽しくなった」と話していました。職場選び次第で、仕事の感じ方は大きく変わるのです。
「向いてないのかも…」と落ち込む前に、まずは登録だけでもしてみませんか?今の自分に無理なく続けられる場所、意外とすぐ近くにあるかもしれません。
そして、派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【対処法5】転職エージェントに登録してキャリアの方向を相談する
今の職場で「もう無理かも」と感じ始めたとき、自分ひとりで悩みを抱え込むのは本当にしんどいものです。
そんなときは、転職エージェントを頼ってみるのもひとつの方法です。無料で登録できて、担当のキャリアアドバイザーがしっかり話を聞いてくれるため、頭の中を整理しながら、これからの働き方を一緒に考えることができます。
「業務が複雑すぎてついていけない」「人手不足で常にピリピリしている」など、今の職場で感じている違和感や不満を伝えると、より自分に合う求人の提案がもらえるのも大きな魅力。
実際にその職場で働く人の声や、残業の実情など、求人票ではわからない“リアル”な情報まで共有してくれるため、転職によるミスマッチも事前に防ぐことができます。
介護事務はどの職場でも同じに見えるかもしれませんが、介護の世界から一歩踏み出すと、雰囲気や業務の内容・やり方は仕事によってまったく違うことに気づかされます。
自分を責めすぎず、少し立ち止まって「この先、どう働きたいか」を考えてみてください。転職エージェントは、その第一歩を支えてくれる頼もしい存在です。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
未経験でも事務職デビューを叶える求人サイトおすすめ3選
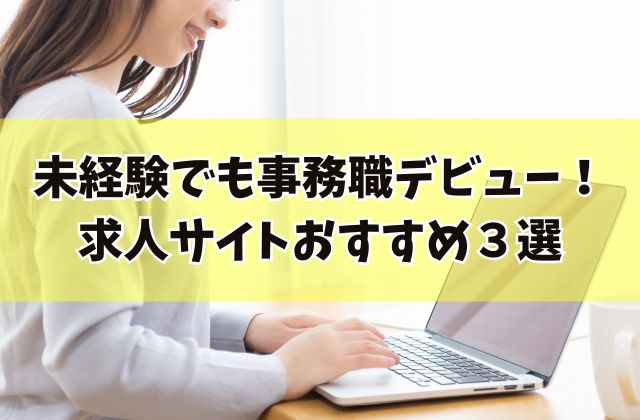
介護事務の仕事が覚えられないと悩む中で、「自分には向いていないのかも」と感じる方は少なくありません。
しかし、環境が変われば力を発揮できることも多く、働きやすい職場に出会えるかどうかが鍵になります。
そこでここからは、未経験でも事務職デビューを叶える求人サイトおすすめ3選を厳選して紹介していきます。
事務職初心者でも研修制度や福利厚生が充実した安心のサービスを紹介します。自分に合う職場探しの第一歩として、ぜひ参考にしてください。
【おすすめ1】マイナビキャリレーション
「事務職に挑戦したいけど、経験がなくて不安…」そんな方に注目してほしいのが、『マイナビキャリレーション』です。マイナビグループが運営しており、研修つきで未経験から始めやすいのが魅力です。研修内容は、ビジネスマナーからWordやExcelの操作まで幅広く、基本をしっかり身につけられます。
実際の研修では、ムービー教材を活用した“ムビケーション”という独自のスタイルを採用。人によっては個別のフォローも受けられるので、パソコンが苦手でも心配いりません。
さらに、無期雇用派遣という働き方なので、契約ごとに職場を転々とする心配が少なく、将来的に正社員を目指すことも可能です。専任のアドバイザーがついて、就業中も相談に乗ってくれるので安心感があります。
【おすすめ2】ランスタッド
「家事や育児と両立しながら、そろそろ事務の仕事を始めたい」そんな思いに寄り添ってくれるのが、『ランスタッド』です。全国に対応していて、週2~3日だけ働きたい方から、しっかりフルタイムを希望する方まで、柔軟に選べる求人がそろっています。時給1,300円以上の案件も珍しくなく、条件面の満足度も高めです。
中でも、人気なのは「サポート事務」の求人。土日祝はお休み、残業もほとんどなし、17時には退勤できる職場もあり、家庭優先の生活にフィットしやすいのが特長です。フレックス勤務や在宅可の募集もあり、働き方の自由度はかなり高めです。
初めての職場って誰でも緊張するものですが、ランスタッドでは専任の担当者がついて相談にのってくれるので安心感があります。未経験でも「まず一歩踏み出してみようかな」と思わせてくれるサービスです。
【おすすめ3】テンプスタッフ
「事務の仕事をやってみたいけど、自信がない…」そんな気持ちに寄り添ってくれるのが、『テンプスタッフ』です。登録後には無料の研修が用意されていて、WordやExcelの基本操作から丁寧に教えてもらえるので、パソコンに苦手意識があっても大丈夫。実際に未経験から始めた方も多くいます。
紹介される求人は、一般事務はもちろん、受付や営業事務なども。時給は1,300円台~1,700円台が中心で、家庭と両立しやすい時間帯や、土日休みの案件も揃っています。「ちょうどいい働き方」を探している方にはぴったりです。
面談や相談には、専任のコーディネーターがしっかり対応してくれるので、はじめての職場でも不安を抱えずにスタートしやすい環境です。「未経験OK」「質問しやすい雰囲気」「残業ほぼなし」など、働きやすさに配慮された案件が多い点も安心材料のひとつです。
【Q&A】覚えられないと感じる介護事務に関するよくある質問
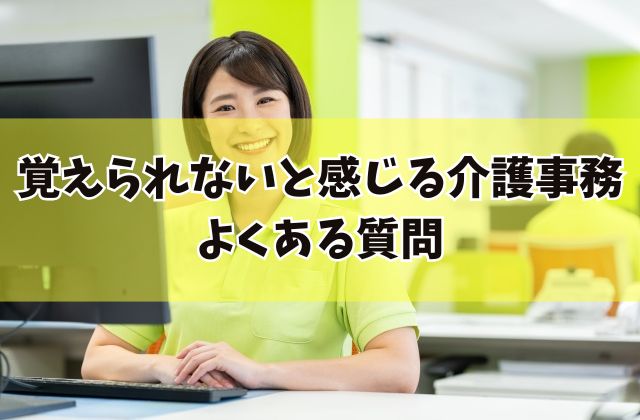
最後に覚えられないと感じる介護事務に関するよくある質問をまとめました。
初心者がつまずきやすいポイントや、仕事を続ける上で知っておきたい現実的な話を丁寧に取り上げています。
【質問1】介護事務で大変なことは何ですか?
介護事務の仕事で一番大変だと感じるのは、やはり「請求業務のプレッシャー」です。
毎月の締め切りに追われるなか、数字を一つ間違えただけで返戻処理になってしまい、事務所全体の動きに影響が出ることもあります。レセプトは何枚もあり、時間との勝負でもあるので、慣れないうちはとにかく神経を使います。それでも、少しずつ流れを理解し、毎月の業務に慣れてくると、落ち着いて処理できるようになります。最初は焦らず、基本を大事にすることが大切です。
【質問2】介護事務に求められるスキルは?
介護事務に必要なスキルは、ただのパソコン操作だけではありません。
業務では、細かな計算や制度の理解も求められますし、電話や窓口での丁寧な対応も欠かせません。たとえば、訪問介護のスケジュール変更に関する連絡が来たとき、現場スタッフに混乱が起きないように的確に伝える力が必要になります。WordやExcelが使えるのは前提として、誰とでも柔らかく会話できる気遣いも大切です。事務作業の裏に「人とのつながり」があるという意識を持てる人は、長くこの仕事を続けられると思います。
【質問3】介護事務として最初に覚えることは何ですか?
未経験から介護事務を始めるなら、最初に覚えるべきは「介護保険制度の基本ルール」と「レセプトの流れ」です。
介護報酬の請求は、この制度の仕組みを理解していないと誤入力が増えてしまいがちです。最初は「要介護1」と「要支援1」の違いも曖昧で、サービスコードもチンプンカンプン。でも大丈夫。私も最初はノートに書いて何度も見返しながら覚えました。請求ソフトの操作や、サービス提供票のチェックなど、現場で少しずつ身につければOKです。焦らず一つずつ覚えることが、長く続けるコツです。
【質問4】介護事務は将来なくなる仕事なの?
結論から言えば、介護事務の仕事が今後なくなる可能性は極めて低いです。むしろ、今後ますます需要は高まると見られています。
理由はシンプルで、高齢化が止まらないからです。厚生労働省のデータでも、2025年には65歳以上の人口が全体の約3割に達すると予測されています(出典:高齢化の状況)。つまり、介護サービスを利用する人は確実に増えるということです。業務の一部はシステムで効率化されていくかもしれませんが、制度の変化に対応しながら現場と連携する介護事務の存在は、しばらく代えが利かないものになるでしょう。
【質問5】医療事務と介護事務どちらが難しいの?
どちらも似たような“事務”に見えますが、実際にやってみると難しさの質が少し違います。
医療事務は診療報酬の算定が細かく、ミスが即、請求の誤りにつながります。一方、介護事務は制度改正の頻度が高く、ルールを追いかける手間があります。ただし、資格取得の難易度や実務への入りやすさで比べると、介護事務の方が初心者にとってはハードルが低いと感じる人が多いようです。実際、通信講座の合格率や現場の声でもその傾向は見てとれます。まずは現場に慣れたい人には、介護事務の方が向いているかもしれません。
【質問6】介護事務はなぜ「やめとけ」と言われるの?
ネットで「介護事務 やめとけ」といったネガティブな声を見かけた人もいるかもしれません。
ただ、すべてが真実とは限りません。確かに、月末月初のレセプト請求が集中する時期は忙しくなりますし、小規模な事業所では介護スタッフの業務を手伝うこともあるため、負担が大きく感じることはあります。けれども、これは職場選びで回避可能なケースも多いです。事前に仕事内容や人員体制を確認したり、余裕のある事業所を探せば、落ち着いて仕事ができる環境は見つかります。大切なのは、情報に振り回されず、自分に合った働き方を見極める視点です。
【質問7】40代から介護事務を始めるのは難しいの?
40代で新たに介護事務を目指すのは無謀だと思っていませんか?実はそんなことはありません。
介護業界では、年齢よりも「誠実さ」や「責任感」を重視する風潮があり、未経験歓迎の求人も多く出ています。特に、40代は家庭や人生経験が豊富な分、事務業務においても丁寧さや気配りが自然に身についている人が多いのが強みです。
最近は、自治体や民間スクールで介護事務の資格講座を受けられる環境も整っており、学び直しにも最適です。新しい職場や業務に不安がある場合は、まずはパートや派遣などから始めて、少しずつ慣れていく方法もあります。年齢を言い訳にせず、踏み出せるかどうかが大きな分かれ道になります。
そして、以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【質問8】50代から介護事務を始めるのは難しいの?
「もう50代だし…」とためらっていませんか?実際のところ、介護事務は50代からでも十分に挑戦できます。
パソコンの基本操作さえできれば、専門知識は入職後のOJTや講座で習得可能です。さらに、デスクワーク中心で体力的な負担も少ないため、年齢的な不安を抱えにくい職種の一つでもあります。実務経験がなくても、「落ち着いた対応ができる」「丁寧な書類作成が得意」といった点を評価されて採用に至る例も多くあります。また、家庭と両立しやすいシフトや勤務時間の相談がしやすい職場も増えてきているため、自分の生活スタイルに合わせて働けるのも魅力です。50代こそ、経験値を活かせる介護事務に適した年代かもしれません。
【質問9】未経験から介護事務を始めるのは難しいの?
結論から言えば、未経験でも介護事務は十分スタートできます。
実際に求人サイトを見てみると「未経験OK」「資格不問」と明記された募集が多くあります。事務職の中でも比較的専門性が高い印象を持たれがちですが、業務の多くは決まった手順に沿って行うため、慣れてしまえば落ち着いて取り組めます。
特にレセプト請求や記録入力などは、丁寧さと地道な作業をいとわない姿勢が求められるため、コツコツ型の人には向いている仕事です。独学や通信講座を通じて、あらかじめ制度や業務の基本を学んでおくと、実務に入ったときの不安も減らせます。今から始めても遅くはありません。必要なのは経験より「やってみよう」という一歩です。
そして、以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
まとめ:介護事務の仕事が覚えられない理由とその対策や対処法
介護事務の仕事が覚えられない理由とその対策や対処法をまとめてきました。
改めて、介護事務の仕事が覚えられない理由をまとめると、
- 覚える制度や計算が多すぎて混乱してしまうから
- パソコンや書類操作が苦手で手が止まるから
- レセプト業務が難しくて時間がかかってしまうから
- 月末月初の請求業務が一気に集中して負担が大きいから
- 職場の人手不足で教えてもらえず戸惑うから
- 介護保険制度が頻繁に変わり追いつけないから
そして、介護事務が覚えられないと感じたときに知っておきたいポイントもまとめると、
- 制度や計算の多さに戸惑ったら、まずは優先順位をつけて段階的に覚える
- パソコンや書類が苦手なら、チェックリストや手順書で作業を整理すると効果的
- レセプト業務が難しく感じたら、繰り返し実践して感覚を身につけていくことが大切
- 月末月初の負担が大きいときは、スケジュール管理で見通しを立てると気持ちが楽になる
- 人手不足で教えてもらえない場合は、信頼できる人や転職エージェントに相談する
介護事務の仕事は「覚えられない」と感じる場面が多く、自信を失いがちです。
しかし、ポイントを押さえて取り組めば少しずつ慣れていけます。苦手な分野があるのは当たり前。焦らず、自分のペースで学んでいけば大丈夫です。