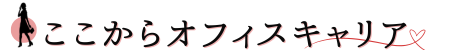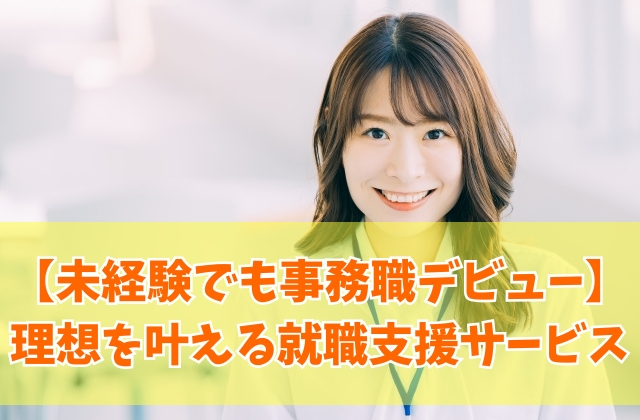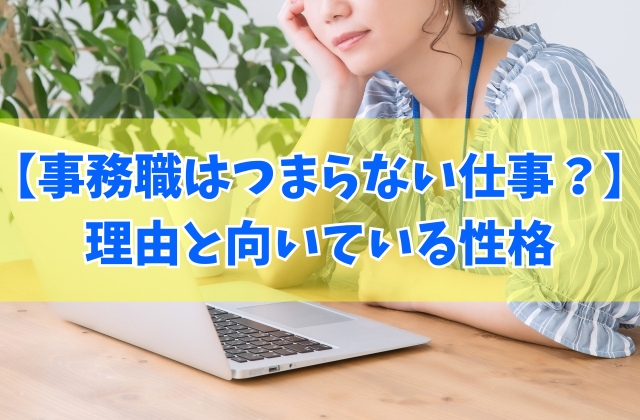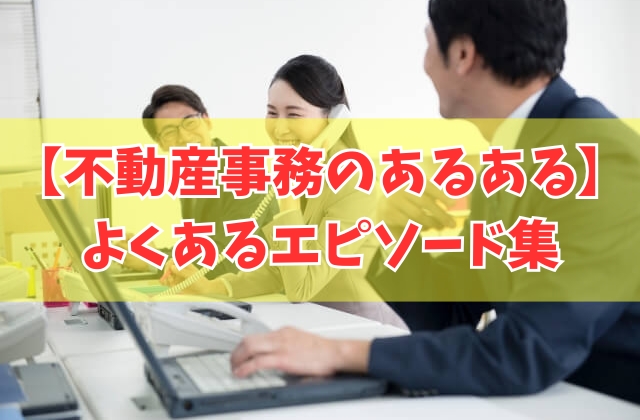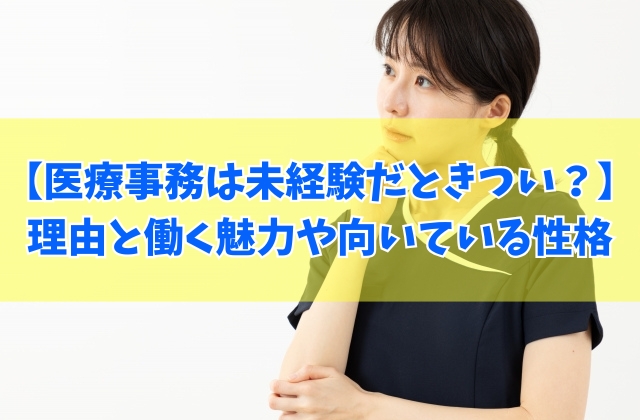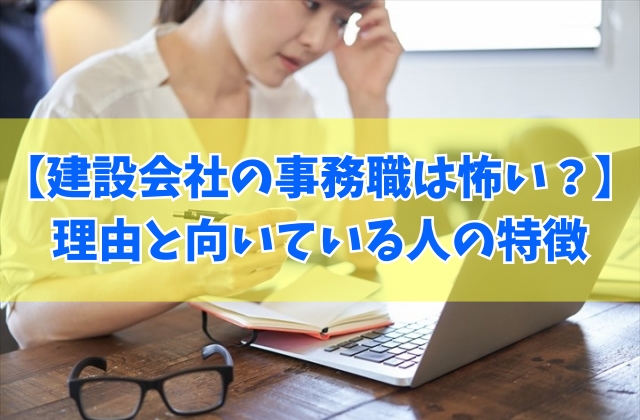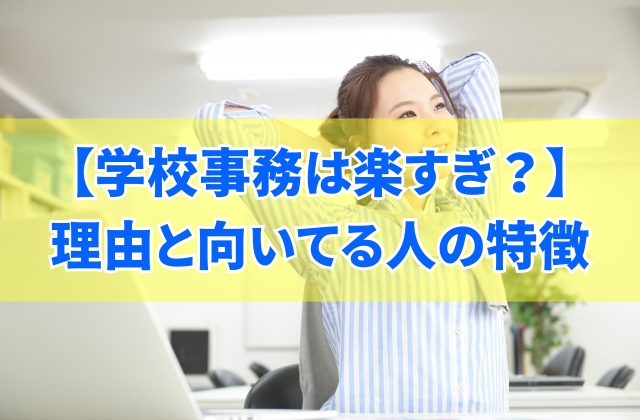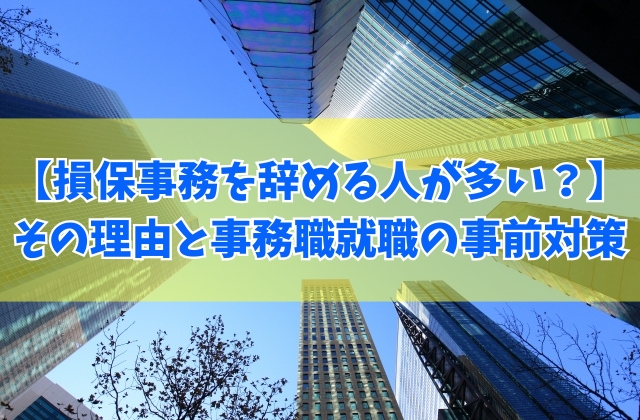
「損保事務を辞める人が多いってホント?」
「その理由は?事務職に就職して後悔しないための有効な対策は?」
「損保事務は辞める人が多いらしい…自分に向いているのか不安」と感じていませんか?
せっかく事務職に就職・転職するなら、長く続けられる環境を選びたいものです。
確かに損保事務はプレッシャーがかかる場面もありますが、一方でやりがいや安定性も備えた仕事です。
この記事では、損保事務を辞める人が多い理由から、実際に働く魅力、後悔しないための準備までをわかりやすく解説します。
事務職への就職・転職を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 業務の正確さやスピードが強く求められ、精神的に負担が大きい
- 新人でも即戦力扱いされやすく、サポート体制にばらつきがある
- クレーム対応や煩雑なルールにより日々のストレスが蓄積しやすい
損保事務は「辞める人が多い」と言われる背景には、業務量や精神的なプレッシャーの大きさが関係しています。
そのため、事前に仕事内容や職場環境を理解し、自分に合った求人を選ぶことで、長く安定して働くことも十分に可能です。
とはいえ、損保事務を辞める人が多いと知って、次のような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
「未経験から事務職に転職したいけど、スキルや経験が不足していると感じる」
「安定した雇用形態と収入を得たいけど、適切な求人が見つからない。。」
「仕事とプライベートを両立させ、充実した生活を送りたい!」
これらの悩みや不安を解消し、あなたの理想の働き方を実現するのが『マイナビキャリレーション』です。
マイナビキャリレーションは、未経験から事務職へ転職を目指す方を支援するサービスです。充実の研修制度や無期雇用派遣による安定した働き方を提供し、スキルアップとキャリア形成を全面サポートします。
- 未経験からの事務職就職をサポート
マイナビキャリレーションでは、事務未経験の方でも安心してスタートできるよう、充実した研修制度を提供しています。ビジネスマナーやコミュニケーションスキル、OAスキルなど、基礎から学べる環境が整っています。 - 安定した雇用と収入
無期雇用派遣社員としての採用により、雇用期間の制限がなく、安定した収入を得ることが可能です。さらに、賞与や昇給制度も整っており、長期的なキャリア形成を支援します。 - 仕事とプライベートの両立
週休二日制や各種福利厚生が充実しており、プライベートも大切にしながら働くことができます。産前産後休暇や育児休業などの制度も完備しており、ライフステージの変化にも柔軟に対応できます。
これらの特徴やメリットにより、マイナビキャリレーションは、事務職への就職・転職を目指すあなたの不安を解消し、安定した働き方とプライベートの充実を実現する最適な選択肢となります。
“こんな働き方がしたかった”を、マイナビキャリレーションで実現しませんか?
【結論】損保事務を辞める人が多いってホント?
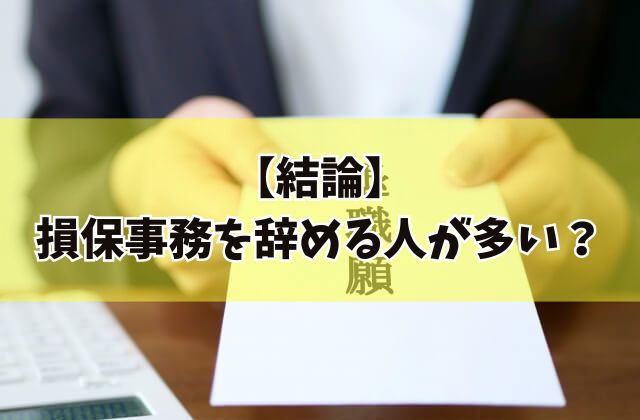
「損保事務を辞める人が多い」は本当なのかどうか。
結論から言えば、損保事務の仕事は「辞める人が多い」と言われているのは、事実に基づいた話です。特に入社から数年以内に離職する人が多く、実際に「3年以内に3割以上が辞めてしまう」というデータもあります(出典:就職四季報)。現場の声や口コミにもその傾向が表れており、「気づけば毎月誰かが退職している」という話すら珍しくありません。
理由としてよく挙げられるのが、仕事の負担が大きいこと。保険金支払いの対応では、細かいミスが許されないため、常に神経を使います。さらに、クレーム対応や複雑な規定の暗記、終わりの見えない業務量など、心身ともに消耗しやすい環境になっています。しかも、未経験でも早い段階で実務に入るため、戸惑いながら仕事を続ける人も多いようです。
実際、口コミサイトなどを覗くと「電話が鳴り止まず、定時で帰れる日はほぼない」「研修はあるけど現場とのギャップが大きすぎる」といったリアルな声が並んでいます。数字だけでは見えない現場の過酷さが、こうした離職率の高さにつながっているのかもしれません。
「安定した事務職」と思って応募しても、想像以上にハードでギャップを感じる人が多いというのが、損保事務を辞める人が多い本当の背景です。興味がある方は、仕事内容をよく調べ、自分に合うかどうかをしっかり見極めることが何より大切です。
損保事務を辞める人が多いと言われる5つの理由
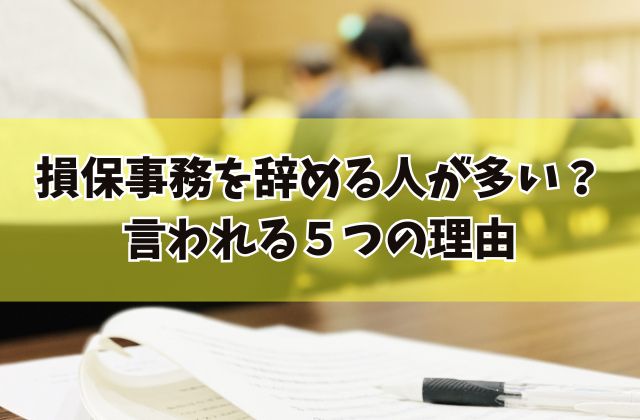
損保事務は一見すると安定していそうな仕事ですが、実際には「辞める人が多い」と言われることが珍しくありません。
事務職への就職や転職を検討している方にとって、なぜそうした声が出ているのかはとても気になるところでしょう。
ここでは、損保事務を辞める人が多いと言われる5つの理由について、現場の実情を踏まえて順にご紹介します。
働き始めてから後悔しないためにも、リアルな事情を理解する参考にしてください。
【理由1】精神的なプレッシャーが大きく毎日疲れやすいから
損保事務の仕事を経験した人の多くが口にするのが、「精神的にかなりきつい」という声です。単なる事務作業とは違い、感情的になった契約者や関係者と直接やり取りをする場面が多く、毎日のようにクレーム対応に追われることもあります。
特に事故や災害といったトラブルの後は、こちらが冷静でも、相手の怒りや不安を真正面から受け止めなければならず、強い心の負担を感じやすいのです(出典:参考資料)。
実際、ある方は「1日中電話が鳴り続け、声が枯れるまで話し続けた」と振り返っており、「怒鳴られるのが日常」だったという証言も珍しくありません。こうした状態が長く続けば、心がすり減ってしまうのも無理はないでしょう。
「黙々とこなす事務仕事」と想像して入社した人ほど、このギャップに苦しみやすく、精神的に疲れてしまい、結果として早期に辞めるケースが多く見られます。職場の雰囲気や業務の実態をあらかじめ知っておくことが、後悔しない選択につながる大切なポイントです。
【理由2】ミスが許されず正確な処理スピードが求められるから
損保事務の現場では、ほんの少しのミスが許されません。扱うのは保険契約や事故対応といった重要な情報ばかり。間違ったまま処理すれば、補償が受けられないなどのトラブルに直結してしまうからです(出典:参考資料)。
中には「免責条件の確認ミスで、お客様に謝罪する羽目になった」と振り返る人もいます。たった一度のチェック漏れが、信頼を損なう事態を引き起こす現実がそこにあります。
加えて、処理の早さも常に求められます。複数の案件を抱えるのが当たり前の環境で、1件ずつゆっくり取り組む余裕はありません。次々に届く電話、期限のある書類、待っているお客様…。急かされるように業務をこなす日々に、焦りと緊張で疲弊してしまう人も少なくないのです。
正確さとスピード。その両方を常に意識しながら働き続けるプレッシャーに、心が折れてしまう人も多く見られます。丁寧に仕事をしたいと思って入ったのに、気がつけば「急げ」「早く」と追い立てられるような毎日。そんなギャップに戸惑い、離職を選ぶ人も珍しくありません。事務職を検討するなら、こうした現場のリアルを知っておくことが、後悔しない選択につながります。
【理由3】膨大なルールと約款を常に覚え続ける必要があるから
損保事務の仕事を始めてまず壁にぶつかるのが、「覚えることの多さ」です。ルールや約款の内容は本当に細かく、しかもどんどん更新されていくため、学びが終わることはありません(出典:損害保険の保険金支払に関するガイドライン)。
「研修で習った通りに処理したつもりが、実はルールが改訂されていた」なんてことも珍しくなく、気が抜けない日々が続きます。
たとえば、保険金の支払いに関わる条文には、特約の条件や除外規定が細かく記されており、一文の解釈を間違えると大問題になります(出典:参考資料)。知識をアップデートし続けなければ対応できないのに、業務量も多く、なかなか勉強の時間が確保できないという矛盾を感じている人も多いようです。
実際に働いていた方の話では、「常に新しいマニュアルが回ってくるけれど、全部は覚えきれず、質問すれば“この前言ったよね?”と冷たく言われた」といったエピソードも聞かれました。プレッシャーを感じながら必死に覚えても、また次の変更が来る。この繰り返しに疲れ、離職を選ぶ人も少なくありません。
損保事務は「知識を積み上げることが好き」な人には向いていますが、「一度覚えたら終わり」と思っていると、かなりきつく感じてしまう仕事です。知識のメンテナンスも業務の一部。それが苦でないか、自分とよく向き合っておくことが大切です。
【理由4】理不尽なクレームや怒鳴られる対応が多いから
損保事務に携わる人たちの声を聞くと、多くの人がまず「電話が怖い」と言います。ただの事務職だと思って入ったのに、いざ現場に出るとクレームの嵐。しかも、その多くは理不尽な内容ばかりです。
例えば、事故の過失割合に納得できない契約者、書類提出の遅れに苛立つ代理店、補償の対象外と伝えた瞬間に怒鳴り声をあげる相手。悪くないのに謝る毎日に、心がすり減っていく感覚を覚えるのも無理はありません。
ある元社員は「毎日誰かしらに怒鳴られていた。電話が鳴るだけで動悸がするようになった」と話していました。実際、損保の現場では対応力より“耐久力”が求められるような場面が多く、メンタル面で折れてしまう人も珍しくないのです。
もちろん、仕事として割り切れる人もいます。ただ、「保険=安心」と信じて入った人ほど、現実とのギャップに悩みやすいのかもしれません。穏やかな職場をイメージしている人にとって、損保事務のクレーム対応は、思っている以上に大きなハードルになることがあります。離職率の高さには、こうした“目に見えないストレス”が確かに存在しています。
【理由5】新人でも業務量が多く慢性的に人手不足だから
「まだ入社して間もないのに、なんでこんなに任されるの?」——損保事務の現場で、そう戸惑う新人は少なくありません。業界全体が人手不足ぎみで、誰かが辞めても補充されないまま、残った人たちで回していくのが当たり前になっているからです(出典:参考資料)。
本来なら、基礎をしっかり学んでから次のステップへ進むはずの新人研修。でも実際には、覚える間もなく現場に投入され、ベテランと変わらない量の仕事をこなすことになります。とくに損害保険ジャパンでは「研修後すぐに繁忙期」「業務分担の余裕がない」といった声も複数あがっており、教育より即戦力を求められる風土があるようです。
ある元社員は、「トレーニー制度と聞いていたのに、蓋を開ければ新人ばかりが現場を支えていた」と話していました。慣れない業務に追われるうちに、自分が何をしているのかさえわからなくなってしまう。そんな状況に心が折れて、静かに辞めていく人もいます。
損保事務を目指すなら、「新人だから優しくされる」という期待は捨てたほうがいいかもしれません。人手不足のしわ寄せは、往々にして新人へ向かいます。だからこそ、事前にその覚悟を持って飛び込めるかが、続けられるかどうかの分かれ道になるのです。
ホントに辞める人が多い?損保事務で働く魅力や楽しさ

「損保事務=辞める人が多い」というイメージばかりが先行しがちですが、実は続ける人にも確かな理由があります。
地道な業務の中にも学びややりがいがあり、働きやすさを感じている声も多く存在します。
ここでは、損保事務で働く魅力や楽しさに焦点を当て、「実際のところどうなのか?」という疑問にお答えしていきます。
マイナス面だけにとらわれず、自分に合う働き方を見つけるヒントにしてください。
【魅力1】保険の専門知識が自然に身につく学びがある
保険って、普段の生活ではあまり深く考える機会がありませんよね。でも損保事務で働いていると、不思議なくらい自然に知識が頭に入ってくるんです。最初は「火災保険?何が違うの?」というレベルだった方も、気がつけば「特約」「約款」「免責」なんて言葉を日常的に使いこなしていたりします。
もちろん最初は戸惑うこともありますが、業務の中で繰り返し目にしたり、上司から教わったり、時には研修で学んだり。いつのまにか「知っている」が積み重なって、「自分の強み」と言えるようになる。これがこの仕事の面白いところです。
ある派遣社員の方は、医療系の保険商品を担当していたことで、まったくの未経験から「医師賠償責任保険」に詳しくなったそうです。知識ゼロからでも経験を重ねるうちに、専門職と堂々と会話できるようになったと話していました。
損保事務という仕事には、数字を打ち込むだけではない“実になる時間”があると思います。保険の知識は、今後どんな業種に行っても、暮らしの中でもずっと役に立つ財産です。知識を深めたい人には、損保事務という選択は決して悪くありません。
【魅力2】福利厚生が整い女性も長く働きやすい
損保事務には「辞める人が多い」という印象もありますが、一方で長く続けている女性が多いのも事実です。その背景には、働きやすさを支える福利厚生の存在があります。
たとえば、大手損保会社では産休・育休の取得はごく当たり前で、時短勤務や在宅ワーク、フレックス制度などが制度として用意されているだけでなく、実際に活用されているという点が大きなポイントです(参考:損保ジャパン)。制度があっても使いづらい会社が少なくない中、「気兼ねなく取得できる雰囲気がある」と話す現役社員の声も少なくありません。
求人情報を見ても、「残業ほぼなし」「週4日勤務OK」「扶養内勤務可」など、家庭と両立しやすい条件が並んでいます(出典:マイナビ転職)。特に子育て中の女性にとっては、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できるこの環境は心強いはずです。
もちろん、仕事そのものは大変な場面もあります。それでも「子どもの体調不良で急に休んでもフォローしてもらえた」「家庭の事情に配慮してもらえた」といった実例が積み重なることで、「ここなら長く続けられる」と感じる人が多いのでしょう。
一口に損保事務といっても、辞める理由ばかりではありません。自分のペースでキャリアを積める環境を求めている方にとって、実は“続けやすい職場”が揃っているのが損保事務という選択肢なのです。
【魅力3】社会貢献を感じられる仕事のやりがい
「ありがとう、あなたのおかげで助かりました」──この一言に救われる、と話す損保事務のスタッフは意外と多くいます。電話口の向こうで困っていた誰かの生活が、ほんの少し前向きになる。その一端を担えたという実感は、地味な事務作業の中に確かな意味を与えてくれるのです。
保険金の支払いが遅れれば、契約者は治療費や修理費を自腹で立て替えることになります。火災や事故、災害といった突然のトラブルに直面した方々に、安心と支援を届ける。それが、損保事務という仕事の本質です。
もちろん、大変なことも多いです。事務処理のプレッシャー、クレーム対応、終わりの見えない業務量。それでも、「この仕事が誰かの人生を支えている」と感じられた瞬間に、報われる気持ちになる方が少なくありません。
派手さはなくても、誠実に積み重ねた一件一件が、契約者の安心につながっている。そんな実感を得られるのは、損保事務ならではのやりがいだと思います。辞める人が多いと言われがちな仕事ですが、それでも残っている人たちは、決して数字だけを追っているわけではないのです。
誰かの困りごとに、自分の働きで応える。そんな仕事に価値を見出せる人にとって、損保事務は誇れる職業です。
【魅力4】未経験でも研修制度で安心して始められる
損保事務に興味はあるけれど、「知識も経験もゼロだし、自分にできるのかな」と不安に感じる方は少なくありません。そんな心配を払拭してくれるのが、各社が用意している丁寧な研修制度です。
たとえば、東京海上グループでは、未経験の方を対象にした約3週間の初期研修が用意されています。保険に関する基礎知識や約款の読み方、書類の扱い方まで、段階を追って学べるカリキュラムです。しかも、研修中も給与が発生するので、生活面での不安も少ないのがありがたいところです。
SOMPOコミュニケーションズも同様に、入社直後に数日間の導入研修を行ったあと、現場に配属されてからはマンツーマンでのOJTで少しずつ仕事を覚えていく流れになっています。わからないことをその場で質問できる環境が整っており、孤独を感じにくいのが特徴です。
「損保事務を辞める人が多い」といった声があるのも事実ですが、裏を返せば、それだけサポート体制の重要性を各社が真剣に考えているということ。未経験でも安心してスタートしやすいのは、研修制度がしっかり整っているからこそと言えるでしょう。
【魅力5】土日祝休みでプライベートとの両立が可能
平日フルタイムで働いて、土日や祝日は家族とゆっくり過ごしたい。そう感じる方にとって、損保事務は意外にも理想に近い働き方ができる仕事かもしれません。
実際、東京海上日動やSOMPO系の損保代理店では、カレンダー通りの休日を基本としつつ、年間休日120日以上を掲げているところも少なくありません。年末年始やお盆休み、有給の取りやすさに言及する口コミも多く、「休みづらい空気がない」という体験談も確認されています。
「休日がちゃんとある」この一言が、働くうえでどれだけ心の支えになるかは、社会人なら誰しもわかること。平日は仕事に集中して、週末は子どもの習いごとの送迎や趣味のカフェ巡り、そんな生活リズムを保ちたい人にとって、損保事務はわりと穴場です。
「損保事務は辞める人が多い」と言われがちですが、その一方で「勤務環境は安定していて満足」という声も確実に存在します。離職率だけでなく、働きやすさの中身にも目を向けてみると、違った景色が見えてくるかもしれません。
辞める人が多いと言われる損保事務に向いている人の特徴

損保事務は離職率の高さがたびたび話題になりますが、すべての人に向かない仕事というわけではありません。
実際には「合う人には非常に安定して働ける職場」でもあります。
では、辞める人が多いと言われる損保事務に向いている人とは、どんなタイプなのでしょうか。
ここからは、具体的な損保事務に向いている人の特徴を紹介します。自身の適性を照らし合わせながら、ぜひ参考にしてみてください。
【特徴1】細かい文字や数値を正確に読むのが苦にならない人
損保事務の現場は、想像以上に「細かさ」との戦いです。数字や記号、略語が並ぶ保険証券や申込書を、毎日のように扱うことになります。そういった情報を、目をこらしてチェックし続けるのは、実は相当な集中力を要する作業です。
保険商品には、さまざまな特約や条件が絡み合っていて、同じように見える契約でも中身はまったく違うというケースがざらにあります。一文字違いで保障の範囲が変わってしまうこともあるため、「まあ大丈夫だろう」と流せないのがこの仕事の難しさでもあります。
実際に働いていた方の声として、「顧客情報の入力欄でひとつ数字を打ち間違えたせいで、後から修正処理が必要になり、上司からも指摘された」といったリアルな体験談もあります。入力や照合においては、どんなに慣れていても油断は禁物です。
とはいえ、そんな環境でもコツコツ仕事をこなせる人にとっては、むしろ静かで集中しやすく、自分のペースを保ちやすい職場とも言えます。目の前の数字や文字と丁寧に向き合える、そんな几帳面さや観察力が自然に身についている人なら、損保事務のような繊細な業務にもストレスを感じにくいでしょう。
【特徴2】常に変わる知識やルールを学ぶことが好きな人
損保事務の仕事は、一度覚えて終わりというものではありません。商品の改定、法律や約款の変更、運用ルールの見直し──こうした変化が日常茶飯事で、毎月のように覚えることが出てきます。ですから、知らないことに出会っても「またひとつ覚えられる」と前向きに受け止められる人でないと、正直しんどく感じてしまう場面が多いです。
現場で働く方からは、「やっと業務に慣れてきたと思ったら、次の週には保険料の算出ルールが変わっていて、最初から説明資料を読み直した」という声もしばしば耳にします。それでも、「ルールの背景にある仕組みが見えてくると面白い」と話す方もいるのも事実です。
つまり、目まぐるしく更新される情報に対して、義務感ではなく興味で向き合えるかが、この仕事を長く続けられるかどうかのカギです。学校の勉強とは違い、正解のない対応や判断も多いため、「新しい知識を取り入れることが好き」という気質のある方に向いています。
【特徴3】責任感を持って仕事を最後までやり遂げる意志力がある人
損保事務の仕事は、表向きは「地味な事務作業」と思われがちですが、実際には一つひとつの業務に“完遂する力”が求められます。途中で判断に迷ったときに、人に投げるのではなく、自分で結論を出し、最後まで手を離さずにやりきる——そんな姿勢が評価される職場です。
たとえば、保険契約者からの問い合わせ対応を経験した方の声によると、「最初から最後まできちんと向き合ったことで、お客様から『ありがとう』のひと言がもらえた」といいます。この一件が、ただの事務作業ではなく“人と信頼を築く仕事”だと気づかせてくれたのだとか。
損保業務はミスが許されにくく、かつ定型的に見える業務の裏に、細かな判断や慎重な対応が求められる仕事です。だからこそ、目の前の仕事に真剣に向き合い、途中で気を抜かず、責任を持ってやり遂げられる人には、強く向いています。
「やりきる力」が自然と発揮できる方にとっては、むしろやりがいを感じられるフィールドかもしれません。
損保事務など事務職に就職して後悔しないための事前対策5選
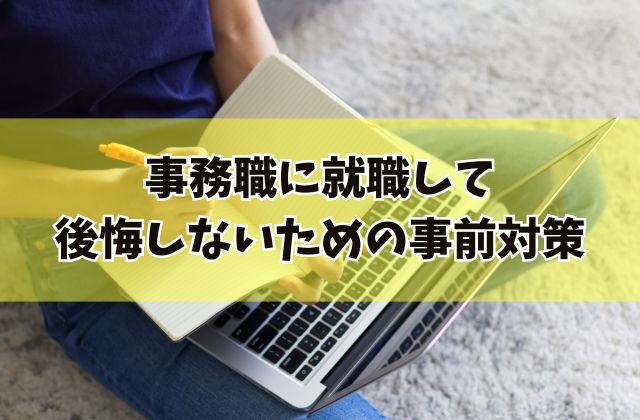
損保事務は、黙々とこなす業務の裏側に、思っている以上の責任や判断力が求められる仕事です。
だからこそ「思っていた仕事と違った…」とギャップを感じて辞めてしまう人も少なくありません。
そこで大切なのが、「損保事務など事務職に就職して後悔しないための事前対策5選」です。
入社前にどれだけ情報を集めて準備しておくかで、入社後の満足度は大きく変わります。
ここからは、後悔を防ぐために必要なポイントを具体的に解説していきます。
【対策1】志望動機と自己分析を明確にしておく
「とりあえず事務なら安定してそう」──そんな気持ちで損保事務を選ぶと、後悔する可能性は高いかもしれません。だからこそ、まず立ち止まって、なぜ損保事務に就きたいのか、何が自分に合っているのかを、丁寧に掘り下げてみてください。
この作業を「自己分析」と呼び、たとえば、家族が事故に遭った際、損保の担当者が心強かった──その体験がきっかけで「自分も誰かの支えになりたい」と思ったなら、それは立派な志望動機です。加えて、過去に「細かいミスを丁寧にリカバリーした経験」があるなら、それも損保事務で活きる強みとして胸を張っていいでしょう。
実際、各種転職サイトでも「志望動機と自己理解の一貫性がある人は採用に強い」という意見は少なくありません。自分の言葉で、納得できる理由を持つ。その積み重ねが「この人なら続けてくれそうだ」と感じてもらえる信頼に、きっとつながっていきます。
とはいえ、自分一人で自己分析を進めるのは簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【対策2】企業や業界をあらかじめしっかり調べておく
損保事務の仕事を選ぶうえで、事前に企業や業界の内情をよく知っておくことは、非常に大事です。なぜかというと、同じ「損保業界」でも会社によって職場の雰囲気や離職率に大きな差があるからです。
たとえば、大手の東京海上日動や三井住友海上などは、新卒3年以内の離職率が一桁台と比較的安定しています。制度や福利厚生が整っているのが理由のひとつでしょう。でも一方で、代理店や外資系などでは、3年以内に8割近くが辞めてしまうという話も実際にあります。口コミをのぞくと「仕事量が多すぎて疲弊する」「サポート体制が薄い」といった声もちらほら。
こうした情報は、公式の求人ページにはまず出てきません。だからこそ、転職サイトや口コミサイト、あるいは実際に働いたことのある人の話を参考にして、応募前に“職場のリアル”をできるだけ集めておくべきです。「入ってから後悔したくない」なら、ここは手を抜けないポイントです。
ただとはいえ、企業や業界の内情を調べるといってもどうすればいいのか?できれば、プロに相談しながら進めたいのが本音ですよね。
そこでおすすめなのが「転職エージェント」をフル活用することです。
転職エージェントを利用すれば、業界に精通したプロのキャリアアドバイザーが、あなたに合った企業の選定から面接対策まで徹底的にサポートしてくれます。
自分ひとりでは気づけない企業の魅力やデメリットも教えてもらえるため、納得のいく転職活動を進めることができます。
ここでは、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
【対策3】複数の派遣会社に登録して仕事の幅を広げる
「ひとまず1社だけ登録しておけば大丈夫」——そう思いがちですが、実はそれ、かなりもったいないんです。というのも、実際に派遣で働いている人の多くは、複数の派遣会社に登録して、自分に合った職場と出会うチャンスを広げています。
日本人材派遣協会の調査でも、2社以上に登録している人が全体の約7割というデータがあるほど。理由はシンプルで、派遣会社ごとに保有している求人が異なるからです。同じ職種・エリアでも、会社によって紹介先企業も条件もバラバラ。たとえば、時給が100円違ったり、交通費が出る・出ないといった差が平気であるのです。
さらに、派遣会社独自の福利厚生やスキルアップ講座、非公開求人など、登録しないと見えない“+αの魅力”も少なくありません。だからこそ、最初は3社ほど登録して情報を比べてみるのが現実的な選択です。
ただし、あまりにも多く登録しすぎると、メールの通知や担当者とのやりとりが追いつかなくなるので注意。最終的には、信頼できる2社ほどに絞り込むのがベストです。損保事務のように人気がある反面、人手不足も叫ばれる業界では、出会える求人が1日違うだけでがらっと変わることもあります。派遣会社を味方につけることで、チャンスを逃さないようにしたいですね。
そして、以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【対策4】転職エージェントを使って情報収集と対策をする
損保事務を目指すなら、転職エージェントの存在を無視する手はありません。求人票の裏側にある“現場のリアル”を知るには、むしろ欠かせない存在です。
というのも、エージェントには一般には出回らない「非公開求人」が豊富にあります。たとえばリクルートエージェントでは、その割合が全体の約半分。つまり、ネット検索だけでは見つけられない企業情報に、ぐっと近づけるというわけです。
加えて、彼らは職種ごとの事情に精通しています。損保事務の面接で問われがちなポイントや、企業ごとの「落ちやすいパターン」など、蓄積されたデータと経験をもとにアドバイスをくれるのです。自分では気づかない改善点にも気づかせてくれますし、忙しい方なら日程調整も任せられて助かります。
たとえば、ある調査では20~30代の約53%が求人サイトを使う一方、エージェント利用者は18%程度に留まっています。まだ少数派ですが、だからこそ「情報の深さ」で差をつけやすいのが魅力です。
「自分で全部やるのは限界がある」と感じているなら、まずは一社でも登録してみるのがおすすめです。動き出すきっかけさえつかめれば、転職活動は一気に前へ進みます。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
【対策5】実際に働いていた人の口コミや体験談を調べる
求人票の数字や制度だけではわからないのが、現場のリアルな空気感。損保事務を目指すなら、まずは実際にその仕事に携わった人たちの声に耳を傾けてほしいです。
たとえば、転職系の口コミサイトや掲示板を見ると、「残業が常態化していて、定時で帰れる日は少ない」「契約内容が細かくて覚えることが膨大」「新人にも容赦なくクレーム対応が回ってくる」といった、生々しい声が並びます。中には「午前中からお客様に怒鳴られて泣いた日もある」なんて投稿も。
とはいえ、ネガティブな意見ばかりではありません。「研修制度がしっかりしていて、未経験でも安心だった」「育児中でも時短勤務が通りやすくて助かった」といった前向きな口コミもちゃんとあります。会社や部署によって実情はかなり差があるようです。
大事なのは、メリット・デメリット両方を知ったうえで、自分にとって何が譲れない条件かを整理しておくこと。現場の声を集める手間を惜しまなければ、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する確率は、きっと減らせます。
※
【無料】未経験でも事務職デビューを叶える求人サイトおすすめ3選
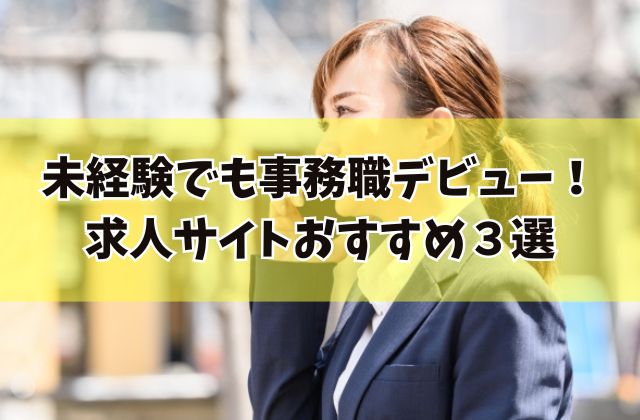
未経験から事務職に挑戦するなら、情報の質とサポート体制が整った求人サイトを選ぶことが成功のカギです。
特に「未経験OK」「研修あり」などの条件を押さえたサイトを活用すれば、初めての転職や就職活動でも不安を減らせます。
ここでは、未経験でも事務職デビューを叶える求人サイトとして、信頼できる3社を厳選して紹介します。
各サイトの特徴を見比べながら、自分に合った一歩を踏み出してみてください。
【おすすめ1】マイナビキャリレーション
「事務職にチャレンジしたいけど、経験がないから不安…」そんな声にしっかり寄り添ってくれるのが、『マイナビキャリレーション』です。未経験スタートの人を想定した仕組みが整っているため、最初の一歩にうってつけのサービスといえます。
たとえば、就業前には4日間の研修があり、WordやExcelの使い方からビジネスマナーまで、基礎をみっちり学べます。ただの座学ではなく、実際の職場を想定したロールプレイング研修もあり、段取りや会話の練習までカバーされているのがポイントです。
さらに心強いのが、担当者によるサポート体制。就業前の不安、働き始めた後の悩み、それぞれに対応する2人の専任担当がつくことで、話しやすい雰囲気があり、安心感も段違いです。
給与面でも、月給20.8万円スタートに加え、賞与や昇給制度、福利厚生サービス(ベネフィット・ステーションなど)も完備。産休・育休の取得実績もあり、将来的に長く働きたい方にも向いています。
「いまの働き方にモヤモヤしている」「でも、いきなり転職は不安」そんな方は、マイナビキャリレーションのような“育ててくれる”仕組みのある環境で、じっくりと事務職デビューを目指してみてはいかがでしょうか。
【おすすめ2】ランスタッド
事務職未経験からのスタートは、不安がつきものです。そんな人にこそ、『ランスタッド』は強い味方になってくれます。実際、私が取材したある派遣社員は「正直、パソコン操作も危うかったのに、丁寧な研修で自然と身についた」と話してくれました。ランスタッドでは、入社前のビジネスマナーから業務の基礎まで、しっかり時間をかけて教えてくれます。
驚くのは、登録スタッフのうち約98%が完全未経験から事務職デビューしている点。この数字は、「できるかどうか」ではなく「やってみたいかどうか」で道が開けるということを示しています。配属先も大手企業が多く、土日祝休み・残業少なめ・年間休日120日以上と、働きやすさも十分。
さらに心強いのは、配属後も定期的にアドバイザーと面談できる点です。困ったときはすぐ相談できる環境があるので、「続けられるか不安…」という声にも応えてくれる安心感があります。自分のペースで成長していける環境が整っている、それがランスタッドの魅力です。
【おすすめ3】テンプスタッフ
「事務職って未経験でもできるの?」と不安を感じている方にこそ紹介したいのが、『テンプスタッフ』です。実際、登録者の多くが「まったくの未経験」からスタートしていますし、事務デビューの支援体制が本当に丁寧です。
まず心強いのが、事務系求人の多さ。月に5万件を超える案件数を持つテンプスタッフでは、「未経験OK」の表示がついた求人も多数。さらに、登録後にはPC操作やビジネスマナーなどの基礎を学べる研修が用意されています。最初はExcelや電話対応すら不安だった方でも、「少しずつ自信がついた」という声が非常に多いのも納得です。
それに、就業後もきちんと担当者がフォローしてくれるのが嬉しいポイント。派遣先とのミスマッチや悩みがあっても、相談できる環境が整っているので、途中で放り出されるような心配は無用です。
「初めての事務職に挑戦したい。でも自信がない…」そんな思いがあるなら、まずはテンプスタッフに登録してみてください。誰にでも最初の一歩があります。その一歩を、ちゃんと支えてくれる仕組みがここにはあります。
【Q&A】辞める人が多いのか気になる損保事務に関するよくある質問
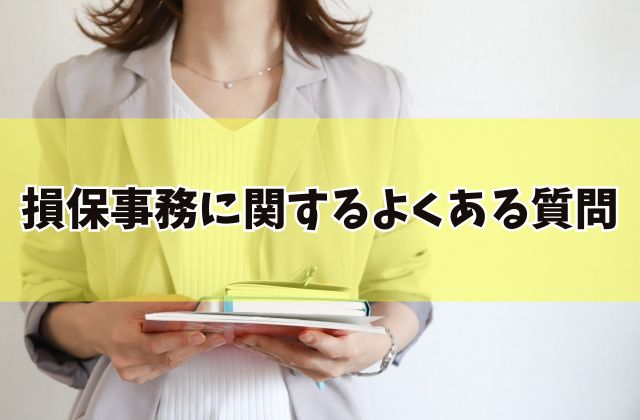
最後に辞める人が多いのか気になる損保事務に関するよくある質問をまとめました。
事前に疑問を解消し、納得のいく選択につなげてください。
【質問1】損保ジャパンの3年以内の離職率は?
「損保ジャパンはすぐ辞める人が多いの?」と心配になる方もいるかもしれません。実は、離職率の具体的な数字は公開されていませんが、参考になるのが平均勤続年数。
損保ジャパンでは17年を超えており、これは大手企業の中でも比較的長め。就職四季報などの情報を見ても、業界内では定着率が高い部類に入ります。口コミでは「育休明けでも働きやすい」「福利厚生が手厚い」といった声も多く、長く働ける土台がしっかりしています。離職率だけに注目するよりも、「続けられる仕組みが整っているか」で見ると、安心感のある会社といえるでしょう。
【質問2】保険代理店事務は本当に楽に働けるの?
「楽そうだから保険代理店の事務を選びたい」という声は意外と多いです。ただし、実際に働いている人の話を聞くと、“完全に楽”とは言えないのが正直なところ。
確かに入力作業が中心で定型業務が多く、未経験でも入りやすい職場もあります。でも、新しい保険商品の更新や約款の見直しなど、細かい変更に追いつく必要があり、集中力と丁寧さが求められます。「研修がしっかりしていて助かった」という口コミもありますが、「楽をしたい」気持ちだけで選ぶとギャップに悩むかもしれません。地道な仕事が苦にならない人には向いている職種です。
【質問3】損保事務派遣の働きやすさは口コミでどう?
派遣で損保事務を考えているなら、働きやすさはかなり気になりますよね。実際、口コミを見ていくと「残業ほぼなし」「定時退社できる」「急なお休みも相談しやすい」など、ワークライフバランスを重視する人には好評な声が多いです。
特に子育て中の女性や、扶養内で働きたい方にはありがたいポイントです。ただ一方で、「繁忙期はバタバタ」「電話対応が苦手だとつらい」といった声もあるので、派遣先や部署によって温度差があるのも事実。気になる方は、登録前に派遣会社から詳しく職場の雰囲気を聞いておくと安心です。
【質問4】損保事務パートはきついって本当なの?
「損保事務のパートってきついって聞くけど…」と不安を抱える人は少なくありません。でも、実情は一概には言えません。
職場によってかなり差があるからです。例えば、「定時退社で家庭との両立がしやすい」「周囲の理解があって働きやすい」といった口コミも多く見かけます。特に大手では時短勤務や育休制度が整っているところも多く、実際にそれを活用している人もいます。もちろん、電話対応やクレーム処理など大変な面もゼロではありません。でも、無理なく続けられる環境かどうかは職場次第。面接時に細かく確認するのがポイントです。
【質問5】損保事務の将来性は明るい?それとも悪い?
損保事務の将来性について「今後なくなる仕事では?」と不安に思う方もいるかもしれません。たしかにDX(デジタル化)が進んで、入力業務などは効率化されつつあります。
しかし、約款の確認や顧客対応、クレーム処理など、人の判断が必要な仕事はまだ多く残っています。さらに、業界全体で制度改正が頻繁にあるため、柔軟に対応できる人材は今後も重宝されるはずです。新しい働き方に適応しつつ、保険の専門知識を深められるという意味では、安定性と成長性を兼ね備えた仕事ともいえます。
まとめ:損保事務を辞める人が多い理由や就職して後悔しないための対策
損保事務を辞める人が多い理由や事務職に就職して後悔しないための対策をまとめてきました。
改めて、損保事務を辞める人が多い理由とポイントをまとめると、
- 精神的プレッシャーやクレーム対応で心身の負担が大きく離職につながりやすい
- 業務の正確さとスピードが強く求められ、プレッシャーを感じやすい職場環境
- 覚えるべきルールや約款が多く、常に学び続ける必要がある
- 派遣やパートでも人手不足により、業務量が多くなる傾向がある
- 一方で、福利厚生や専門知識の習得など長く働くメリットもある
「損保事務を辞める人が多い」と言われる背景には、業務の厳しさや精神的負担があります。
ただし、その一方で専門性が身につき、安定した働き方ができる職種でもあります。適性や働き方のバランスを見極めることが、後悔しない選択につながります。