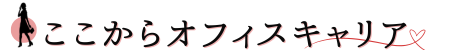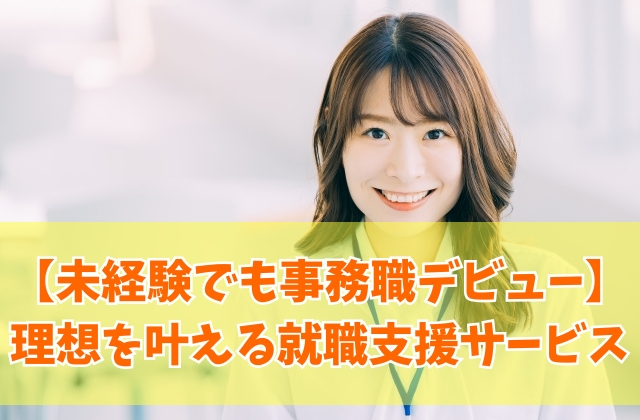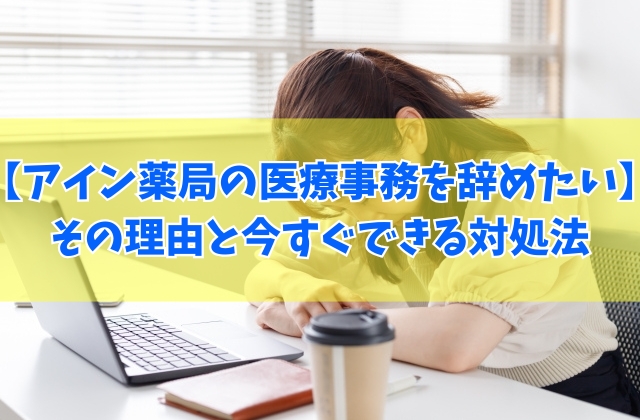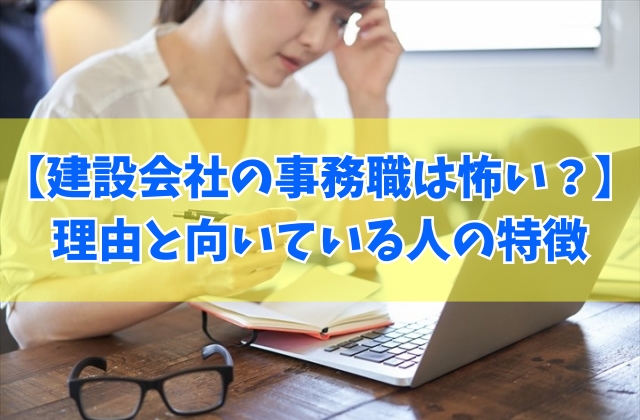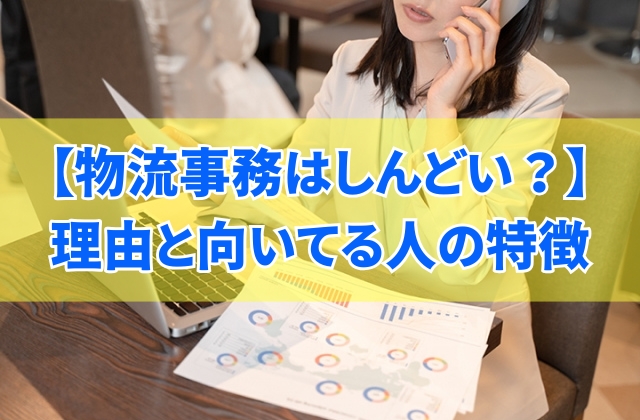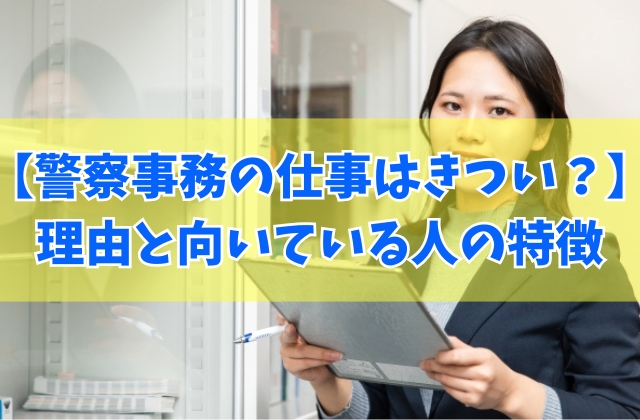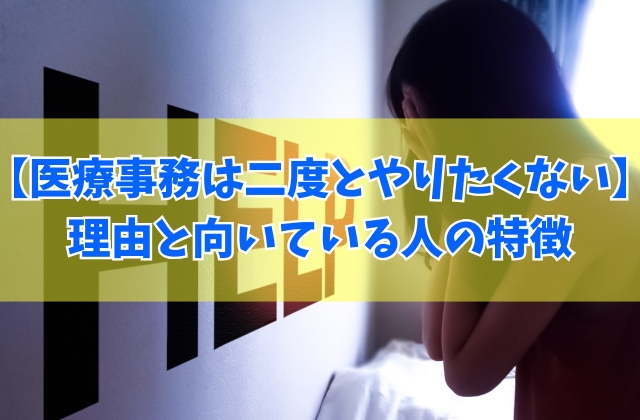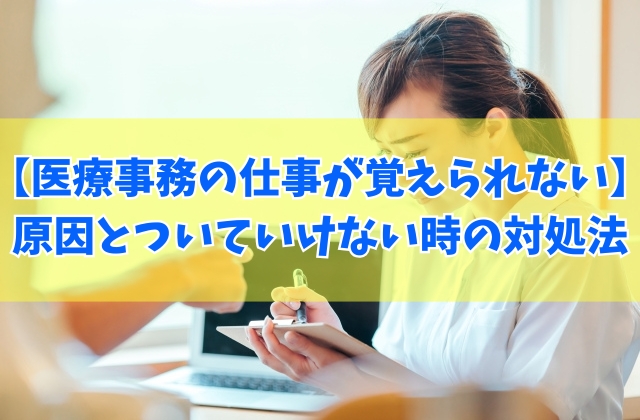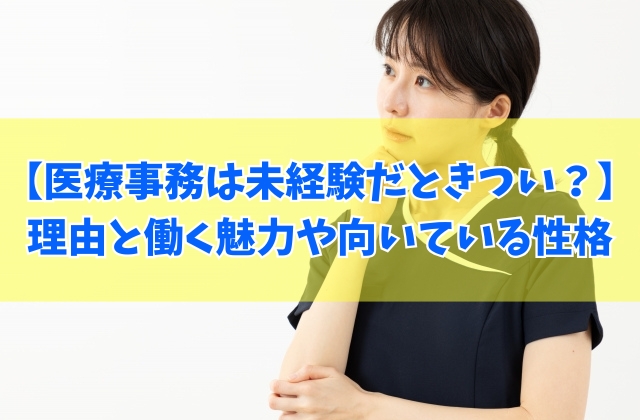
「医療事務は未経験だときつい仕事ってホント?」
「働く魅力は?どんな人に向いている仕事?就活のポイントも教えてほしい!」
「医療事務に興味はあるけれど、未経験だときついのでは?」と不安を感じていませんか。
レセプト業務やクレーム対応など、責任の大きい仕事がある一方で、未経験でも始められる求人は実はたくさんあります。
ですが、事前に仕事内容や職場の特徴を理解し、自分に合った環境を選ぶことで、安心して医療事務の一歩を踏み出せます。
この記事では、未経験から医療事務や事務職を目指す方が気になる「きつい」の実態や、働く魅力・就職活動のポイントまでわかりやすく解説しています。
- 医療事務は未経験だと覚えることが多く、慣れるまでに時間がかかる
- 精神的・体力的なきつさがあるが、働きやすい環境を選べば軽減できる
- 未経験歓迎の求人やサポート体制のある派遣会社を活用すれば安心
医療事務は「未経験だときつい」と言われがちですが、実際は職場の選び方やサポートの有無によって大きく変わります。自分に合った環境を見つければ、未経験でも着実に活躍できる仕事です。
そして、仕事獲得の確率を上げるなら派遣会社の複数登録も視野に入れてみてください。
具体的に派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
たとえば、ランスタッドやテンプスタッフ、アデコなど、サポート体制が充実している派遣会社では、あなたの希望や適性に合った仕事を紹介してもらえます。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【結論】医療事務は未経験だときつい仕事?
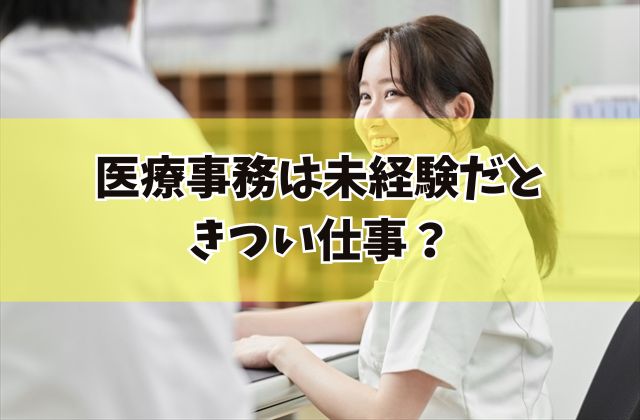
医療事務は未経験だときつい仕事なのかどうか。
正直なところ、医療事務の仕事は「未経験からだときつい」と感じる人が多いのは事実です。ですが、それは「まったくの無理」ではありません。きついとされる理由を知って、事前にしっかり準備すれば、十分やっていける仕事でもあります。
なぜきついと感じるのかというと、まず最初に覚えることが本当に多いんです。医療保険や診療報酬の仕組み、レセプト請求のルール、医療用語に制度改定——最初のうちは、専門用語のオンパレードで「まるで外国語みたい…」と戸惑う人も少なくありません。
しかもこの仕事、ただの事務作業ではなく、ミスが許されないというプレッシャーもあります。特に毎月のレセプト業務は、月末から翌月初めにかけて締め切りがあり、繁忙期には残業が発生することも。「未経験歓迎」とは書かれていても、現場に入ればスピードも正確さも求められるので、最初はかなり神経を使います。
さらに、人と接する仕事でもあるので、患者さん対応にも気を遣う場面が多いです。たとえば「保険証が使えない」「医療費が高い」といったクレームが来たとき、冷静に対応できないと一気に気疲れしてしまいます。
とはいえ、救いなのは未経験OKの求人が多く、研修制度がしっかりしている職場もたくさんあるということ。実際に、資格を取ってから応募したり、事前にパソコンスキルを磨いておいたりすることで、職場にスムーズになじんでいる人も多いです。
「きついから無理」と決めつけるのではなく、「何がきついのか」を知ったうえで、対策しておくことが大切です。それができれば、医療事務は長く安定して働ける魅力のある仕事です。
そして、より多くの求人の中から“自分に合った仕事”を選びたいなら派遣会社の複数登録も視野に入れてみてください。
具体的に派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
たとえば、ランスタッドやテンプスタッフ、アデコなど、サポート体制が充実している派遣会社では、あなたの希望や適性に合った仕事を紹介してもらえます。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
医療事務は未経験だときつい仕事だと言われる8つの理由
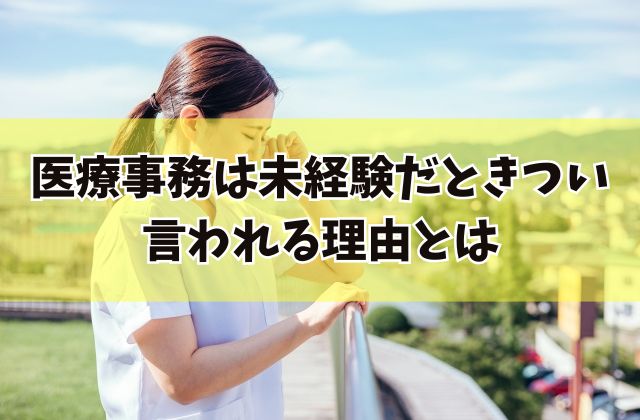
医療事務の仕事に初めて挑戦する人が「きつい」と感じやすいのには、いくつか明確な理由があります。
業務の内容が幅広く、専門性も求められることから、慣れるまでに時間がかかるケースが多いです。
また、職場環境や待遇面にギャップを感じることもあります。
ここでは、「医療事務は未経験だときつい仕事だと言われる8つの理由」について、実際によくある悩みをもとに具体的に解説していきます。
【理由1】覚えることが非常に多く慣れるまで時間がかかるから
医療事務の仕事を未経験から始めて、最初につまずくのが「覚える量の多さ」です。業務自体はシンプルに見えるかもしれませんが、実際はかなり奥が深いんです。
受付のやりとりや電話応対のような事務的なことはまだ入り口。問題はその先で、診療報酬や保険の種類、レセプト請求の仕組みなど、覚えないといけないルールが山のようにあります。しかも、制度は数年ごとに改定されて、内容がガラッと変わることも。そのたびに「また最初から勉強し直し?」とため息が出てしまうこともあるかもしれません。
たとえば、初診と再診で点数が違ったり、保険証の種類で対応が変わったり。そういった細かな違いが毎日のように登場します。慣れないうちは確認の連続で、頭がパンパンになるという声もよく聞きます。特にレセプト提出の時期には、膨大な量のチェック作業が発生し、残業になるケースも珍しくありません。
「慣れるまでに時間がかかる」と感じるのは、決して甘えではありません。それだけ医療事務は知識がものを言う仕事です。ただ、今は未経験者向けにしっかり研修をしてくれる職場も増えていますし、事前に基礎だけでも学んでおけば、入り口でつまずくことはぐっと減ります。
【理由2】レセプト請求など専門的な知識が必要な業務があるから
医療事務の仕事で、未経験の方が最初につまずく壁。それが「レセプト請求」です。
一見、ただの事務処理に見えるかもしれませんが、実際に手を動かすとその複雑さに驚かされます。たとえば、診察ごとにどんな治療が行われたのか、それにどれだけの費用がかかるのかを正確に記録し、保険者に請求する仕組み。それがレセプト業務です(出典:参考資料)。この処理ひとつで病院の収入が左右されるため、ちょっとしたミスも許されないシビアな世界なんです(出典:診療報酬制度について)。
しかも、扱うのは診療報酬や保険制度といった、日常生活ではまず出会わない専門的な内容。点数表の読み方から、病名と診療内容の整合性、保険の種類による請求ルールの違いなど、覚えることは本当に多いです。しかも、それらのルールは数年ごとに改定されるため、常に最新の知識が求められます(出典:参考資料)。
たとえば月末、提出期限の直前。レセプトのミスを一つ見つけてしまったら、残業してでも修正しなければならないこともあります。未経験者にとっては、知識だけでなく、正確さやスピードも求められるこの業務が、強いプレッシャーとなってのしかかります。
ただ、忘れてはいけないのは、「初めてだから難しい」のは当然だということ。今は未経験向けの講座やサポート体制も整ってきています。時間をかけて学び、ゆっくり慣れていけば、専門的な業務も必ず自分の力になります。
【理由3】ミスが許されない責任ある業務でプレッシャーが大きいから
医療事務って、見た目は穏やかでも、実際には“静かな緊張感”が張りつめた仕事です。
表に出ることは少なくても、その裏側では患者さんの個人情報や診療内容を正確に扱う責任がのしかかります。入力ひとつのミスで、保険の請求が通らなくなったり、医師や看護師に迷惑をかけたり(出典:参考資料)。そうなると、病院全体の信頼にもかかわる話なので、「ごめんなさい」だけでは済まされません。
たとえば、診療報酬明細書(いわゆるレセプト)には、保険点数や治療内容を細かく記載しますが、ひと文字の入力違いで金額が大きくズレてしまうこともあります(出典:電子レセプトの作成手引き)。その結果、審査機関から返戻になり、書類を一から作り直し──なんてことも日常茶飯事です。
もちろん、未経験で入ったばかりの頃は、何が間違いで、何が正しいのかすら判断できません。常に「間違えたらどうしよう」という不安がつきまとい、気を抜けない時間が続きます。周りは淡々とこなしているのに、自分だけ取り残されているような気持ちになる──そんな時期を通る人は、実は多いです。
だけど、裏を返せば、それだけ「信頼される仕事」だということ。経験を積んで知識がついてくると、あの独特のプレッシャーがやりがいに変わっていく瞬間が必ず来ます。最初の数ヶ月は大変でも、その先には、自分の手が医療を支えているという確かな実感が待っています。
【理由4】患者さんからのクレーム対応で精神的な負担が大きいから
「すみません、まだ呼ばれないんですけど、あとどれくらいですか?」
受付に立っていると、こうした声が一日に何度も飛んできます。忙しい外来では時間通りに進まないことも多く、こちらに落ち度がなくても矢面に立たされるのが医療事務の宿命。未経験で入った人ほど、その理不尽さに戸惑います。
待ち時間の長さ、診察順の誤解、保険証の使い方……。患者さんが不安や不満を抱える場面では、その感情が一気に受付へとぶつけられます。たとえそれが制度上のルールや医師の判断によるものでも、「説明が足りない」「分かりにくい」と言われるのは、ほとんどが事務スタッフです。
たとえば、診療報酬の仕組みで自己負担額が想定より高くなった場合。「こんなにかかるなんて聞いていない」と強く言われることも。中には声を荒げる方もいて、心がズキッとする瞬間があります。たとえ感情的にならずに対応できても、気づけば心がぐったり疲れている──そんな日も珍しくありません。
とはいえ、こうした対応の中で、人としての成長を感じることも事実です。最初は声が震えていた人も、場数を踏むうちに自然と落ち着いて説明ができるようになっていきます。マニュアル通りにはいかないからこそ、自分なりの“受け止め方”や“寄り添い方”が身につく。そこに、この仕事ならではのやりがいがあるのかもしれません。
【理由5】人手が少ない職場で業務負担が偏ることがあるから
医療事務の現場は、いつだって人が足りているとは言いがたい。これは決して珍しい話ではありません。
特に小規模のクリニックや外来の多い施設では、「受付も電話も会計も予約対応も全部お願い」と言われることがよくあります。実際、業務をこなすうちに「本当にこの人数で回すのが当たり前なの?」と感じたことがある人は少なくないはずです。
スタッフ数がギリギリの状態だと、誰かが休んだときの負担はそのまま他の人へと跳ね返ってきます。急な体調不良や家庭の事情で休む人が出たら、穴を埋めるために残業や休日出勤が必要になることも。こういった状況が重なると、「なんで私ばっかり…」と気持ちが沈んでしまうのも無理はありません。
しかも、未経験で入ったばかりの段階では、業務の流れも頭に入りきっていないのに、先輩が忙しくて質問する余裕すら持てない。そうなると「わからないまま動く」ことが常態化して、精神的な消耗も加速します。
ただすべての職場がそうではなく、うまく分業されていたり、業務効率化のためのシステムを導入している医療機関もあります。研修制度が整っていて、未経験者へのフォローが丁寧なところも確実に存在します。だからこそ、求人を探す段階で「人員体制」や「バックアップの仕組み」を見逃さないことが、本当に大事になってくるのです。
【理由6】給料が仕事内容に比べて低く感じることがあるから
医療事務の求人を見ると、最初に気づくのが「収入の控えめさ」かもしれません。たとえば未経験で正社員として採用された場合、月給は19万~23万円程度が一般的。アルバイトやパートだと、時給1,000円台という募集もまだまだ多く見られます(出典:求人ボックス)。
それだけならまだしも、実際に働いてみると想像以上に業務の幅が広い。受付対応、カルテ入力、レセプト請求、さらには患者さんの対応まで。まるで“何でも屋”のような状態になることもあります。なのに、責任の重さに見合った昇給や手当があるかといえば、そうとは限らないのが現実です。
特に小規模クリニックなどでは、人手がギリギリの状態で回っているため、事務スタッフ一人ひとりの負担がかなり大きくなります。その状況で給料がほぼ変わらないとなれば、「なんだか損している気がする…」と感じてしまっても無理はありません。
ただ一方で、医療事務には「資格を取ればステップアップできる」「働きやすい職場に出会えば長く続けられる」といった希望もあります。だからこそ大切なのは、求人を見るときに“金額”だけで判断しないこと。昇給制度や残業の有無、福利厚生、スタッフの定着率といった周辺の条件をしっかり確認することで、後悔のない選択ができます。
【理由7】連休や希望休が取りにくい職場も存在するから
「やっと子どもの運動会に行けると思ったのに、希望休が通らなかった」──そんな声を、医療事務の現場ではよく耳にします。実際、病院やクリニックの多くは年中無休または土曜診療を行っているため、一般的なカレンダーの休日に合わせた休みは取りづらいのが現実です。
特に月初はレセプト提出で忙しく、スタッフ全員が一丸となって業務に追われる時期。そんなときに「ちょっと休みたいんです」とはなかなか言い出せません。実際に、ある医療事務スタッフは「月初10日までは、ほぼ出勤確定」と話していました。休日の希望を出すこと自体が気まずい雰囲気すらあると漏らすほどです。
もちろん、すべての医療機関がそうとは限りません。中にはシフト制が柔軟で、有給休暇の取得を積極的に勧める職場もあります。ですが、人手が足りない職場では、どうしても“休みたい”より“まわさなきゃ”が優先される。そんな風潮が根付いているケースもあるのです。
だからこそ、未経験から医療事務にチャレンジする方には、求人票の「休日数」だけでなく、「月初の出勤ルール」や「希望休の取得実績」も注視してほしいところ。休み方にも“職場の空気”があるという点は、想像以上に重要な判断軸です。
【理由8】法律や制度が変わるたびに学び直しが必要だから
医療事務の世界は、慣れた頃にまた勉強し直し、という場面が意外と多い仕事です。というのも、診療報酬や保険制度のルールが、国の方針によって2年に1回のペースで改定されるためです(出典:厚労省 保険局パンフ)。医療現場ではこの改定にあわせて、レセプトの内容や点数、入力方法までガラッと変わることもあります。
たとえば2024年度の診療報酬改定では、在宅医療の点数に見直しが入り、該当する医療機関では請求方法を調整する必要が出ました(出典:令和6年度診療報酬改定について)。「このコード、前と違う?」と現場が戸惑うのも無理はありません。特に未経験者は、「やっと覚えたのにまた一から…」と感じることもあるかもしれません。
ですが、だからこそ制度改定のタイミングを「チャンス」と捉える人もいます。変化に対応できる柔軟さは、どの職場でも重宝されますし、求人票をよく見ると「改定内容の研修あり」や「教育担当がつく」といったサポート体制が整っている職場もあります。未経験でも、成長できる環境を見極めて選ぶことが、長く続けるコツかもしれません。
本当にきつい?未経験にとって医療事務の魅力や働くメリット

「医療事務は未経験だときつい」とよく言われますが、実際には未経験だからこそ得られる魅力もたくさんあります。
採用の間口が広く、医療知識を働きながら学べる点や、自分のライフスタイルに合わせて働き方を調整しやすいところも大きな特徴です。
ここでは、未経験の方が医療事務で感じやすい“やりがい”や“働くうえでのメリット”を具体的に紹介していきます。
【魅力1】無資格・未経験でも採用求人が多い
医療事務は「経験者じゃないと無理かも…」と構えてしまう人も多いですが、実は未経験OKの求人は驚くほど多く存在します。たとえば「テンプスタッフ」では、未経験・無資格から応募できる求人が常時500件以上。求人票には「未経験歓迎」や「教育体制あり」といった文言がはっきり書かれているものも珍しくありません。
特に、派遣やパートといった非正規雇用での募集が多く、まずはそこで現場経験を積んで、のちに正社員へステップアップしていく人も多数います。正社員だけにこだわらず、最初の一歩として柔軟な働き方を選ぶのも賢いやり方です。
ただし、「求人が多い=誰でも通る」というわけではないので要注意です。多くの職場では、基本的なPC操作や電話応対などの事務スキルは必須とされています。未経験から医療事務に挑戦する場合は、「教育サポートが整っているか」「OJTがあるか」など、求人票の細かい部分をきちんと読み込むことが、安心して長く働ける環境を見つけるカギになります。
もし、より多くの求人の中から“自分に合った仕事”を選びたいなら派遣会社の複数登録も視野に入れてみてください。
具体的に派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
たとえば、ランスタッドやテンプスタッフ、アデコなど、サポート体制が充実している派遣会社では、あなたの希望や適性に合った仕事を紹介してもらえます。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【魅力2】医療知識や制度が働きながら自然に身につく
「覚えることが多くて不安…」と感じる方もいるかもしれませんが、医療事務の世界は、現場に入ってしまえば意外と馴染みやすいものです。働いていくうちに、専門的な医療用語や保険制度の基本などが、自然と身についていくからです。
たとえば、受付で保険証を確認したり、診療報酬の明細(レセプト)を扱ったりする中で、「こういうケースはこの保険が使える」「この治療には特定の制度が絡む」といった知識が、日々の業務を通じて少しずつ自分の中に蓄積されていきます。
実際、未経験から医療事務に転職した人の多くが、「最初は不安だったけど、毎日現場で触れるうちに、用語や流れがわかるようになった」と話しています。もちろん最初は戸惑うこともありますが、研修やOJTが用意されている職場も増えており、知識ゼロからでもしっかり土台を作っていけます。
制度は変わることもありますが、その都度アップデートしていけば大丈夫。むしろ、実務を通して最新の医療情報に触れられるのは、事務職の中でも医療事務ならではの大きな魅力と言えます。
【魅力3】ライフステージに合わせて働き方を変えやすい
結婚、出産、子育て、介護——人生にはいくつもの節目があります。そんな変化の多いライフステージでも、医療事務という仕事は意外なほど柔軟に寄り添ってくれます。
たとえば、朝の時間にゆとりがない子育て中の方なら、午後からのシフト制で無理なくスタートできますし、「週3日だけ働きたい」といった希望も通りやすい傾向にあります。実際に求人サイトを見ると、「未経験歓迎」「シフト調整可」「資格不要」といった条件の案件がかなり多く、働く側の事情に寄り添っている職場が多いことがわかります。
もちろんすべての職場が柔軟とは限りません。だからこそ、求人票だけではなく、面接時に「どれだけ働き方に融通が利くか」「これまでにどんな働き方をしていた人がいるか」といった点をきちんと確かめておくのがポイントです。
生活のかたちに合わせて働き方を選べるというのは、単なる“メリット”にとどまりません。未経験で医療事務に挑戦する方にとって、それは安心して長く働き続けるための大きな土台になるのです。
【魅力4】資格取得で就職や転職に有利になる
「未経験だけど、やっぱり資格は取ったほうがいいの?」——医療事務を目指す人からよく聞く疑問です。答えは“YES”です。必須ではないけれど、あったほうが確実に道が開けます。
医療事務の資格にはいろいろありますが、たとえば「メディカルクラーク」や「診療報酬請求事務能力認定試験」は、現場で役立つ知識を学べて、履歴書にもきちんと書ける国家水準の認定資格です。実務未経験でも、「基礎は身につけていますよ」と証明できるのは大きな強みです。
しかも最近は、資格を持っているだけで応募先の選択肢が増える傾向もあります。求人票に「有資格者歓迎」と記載されていることも多く、就職・転職どちらでも、資格が“差をつける材料”になるのは間違いありません。
ただ、資格があるからといって、すべてがうまくいくとは限りません。重要なのは、資格をどう活かすか。勉強して終わりではなく、その知識を仕事への熱意とセットで伝えることが、面接ではもっとも効果的です。
【魅力5】患者とのかかわりで感謝される機会が多い
医療事務という仕事は、表舞台に立つ医師や看護師とは違い、いわゆる「裏方」の立ち位置になりがちです。けれど、その裏方にも確かなやりがいがあります。
たとえば、受付で不安そうな顔をしていた患者さんに声をかけたとき、ほっとしたような表情で「助かりました」と言ってもらえることがあります。それだけで、一日頑張ってよかったと思えるものです。
実際、「受付の方の対応が丁寧で救われた」といった口コミやアンケートの声は、医療機関の信頼にもつながる重要な要素として評価されています(出典:病院における患者満足度向上への取り組み)。単に事務処理をこなすだけではなく、人として接することができる職種だからこそ、感謝の言葉が直接届く瞬間があるのです。
もちろん、毎日が感動の連続というわけではありません。しかし、小さな「ありがとう」が重なるたびに、自分の存在が確かに誰かの力になっていると実感できます。未経験で不安を抱えていても、人と人との関係のなかで得られる充足感は、きっとあなたの背中をそっと押してくれるはずです。
きついと言われても医療事務に未経験から働くのに向いている性格
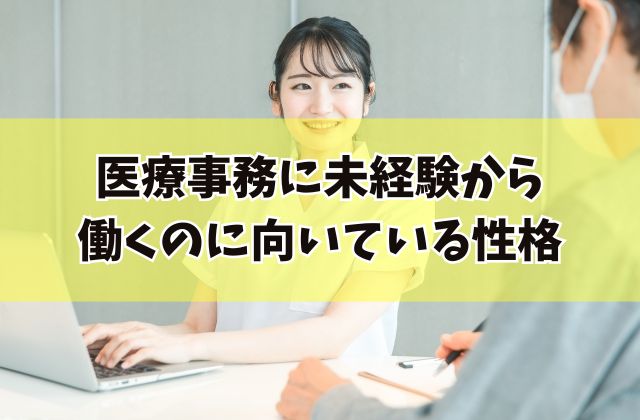
医療事務は未経験だときついと感じる場面もある一方で、向いている性格の人にとってはやりがいを感じながら長く働ける仕事です。
実際、仕事の内容以上に人柄や性格の相性が大切だと現場ではよく言われています。
ここでは「きつい」と言われる理由に不安を抱えている人に向けて、未経験から医療事務にチャレンジしやすいタイプについて詳しく紹介します。
【性格1】思いやりがあり人の気持ちに寄り添える人
「大丈夫ですか?」——このひと言が、患者さんにとってどれだけ救いになるか、医療事務として現場に立つとすぐに実感します。体調の悪さや不安を抱えて窓口に立つ方々は、ほんの少しの気遣いに心をほぐされるものです。未経験であっても、人に優しく接する姿勢がある方は、それだけで大きな武器になります。
たとえば、保険証の提示に戸惑う高齢の方へ目線を合わせて説明する。混雑でイライラしている方には、穏やかな口調で対応する。こうした細やかなやりとりは、マニュアルには載っていませんが、患者さんとの信頼関係を築くうえで欠かせないスキルです。実際に求人サイトでも「接遇マナー」や「思いやりのある対応ができる方」が歓迎される傾向があります。
完璧である必要はありません。けれど、「この人、気にかけてくれているな」と相手が感じる配慮ができる人は、未経験からでも信頼され、必要とされる存在になっていきます。スキルよりもまず大切なのは、その人の“人柄”であるといえるでしょう。
【性格2】正確さを重視しミスをしないよう注意できる人
医療事務に向いている性格のひとつとして、「ミスに敏感で細かい確認を怠らない人」がよく挙げられます。実際の現場では、レセプトの誤入力や書類の記載ミスがあると、保険請求が通らなかったり、医師や看護師の仕事を止めてしまったりすることもあるからです。求人票でも「細やかな作業が得意な方歓迎」といった表記をよく見かけますが、それは現場の声を反映したものだと感じます。
特に、限られた時間の中で膨大な書類を処理する場面も多く、ただ丁寧なだけでは足りません。「正確に、かつスピーディーに」仕事をこなすスキルが、現場では強く求められます。事実、マイナビの調査でも、医療事務に必要なスキルとして「正確性とスピードの両立」が挙げられていました。
もし未経験で医療事務を目指すのであれば、まずは日常生活でも“ダブルチェック”を習慣化してみてください。ちょっとした買い物メモを見直す、家計簿の計算を検算する、メールを送る前に誤字脱字を見直す——そんな小さな積み重ねが、実際の業務でも大きな武器になります。几帳面な性格を「面倒くさい」で終わらせず、それを強みに変えられる人こそが、この仕事で信頼される存在になれるのです。
【性格3】協調性がありチームでの連携を大切にできる人
医療事務の現場に入ってまず驚くのが、「1人で完結する業務がほとんどない」という事実です。レセプト作業や受付応対は表向きには個人プレーに見えますが、実際は他部署との連携があってこそ成り立っています。カルテの確認ひとつとっても、看護師や医師とのちょっとした連携ミスが、大きなトラブルの引き金になることもあるのです。
実際、未経験から医療事務として採用されている人たちを見ていると、共通しているのは「空気を読んで、必要なときに一歩引いたり、逆に手を貸したりできるタイプ」であること。業務の正確さだけでなく、周囲との呼吸を合わせる力が重宝されているのは間違いありません。
例えば、医療事務専門の求人サイトでも、医療事務募集の条件欄に「協調性のある方歓迎」と明記されていることが多く、職場の求める人物像がはっきりと伝わってきます。
要するに、医療事務というのは「人と関わるのが好き」「誰かの役に立つのが嬉しい」と感じられる人ほど長く続けられる仕事です。黙々と作業したい人には少し窮屈かもしれませんが、逆に言えば、チームの中で信頼関係を築いていくことに喜びを見いだせる人には、これほどやりがいのある職場はありません。
きついと言われる医療事務の仕事に未経験でも受かった人の特徴
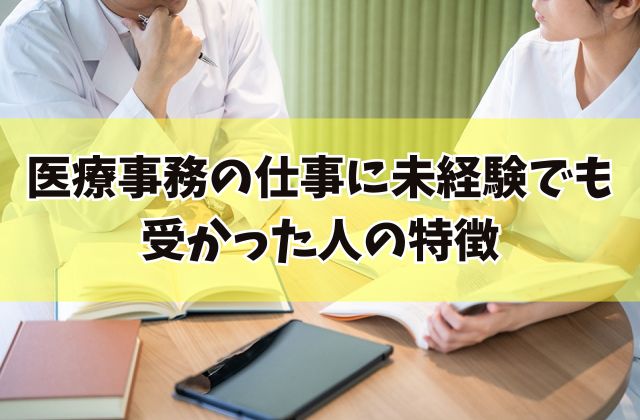
未経験から医療事務の仕事に就くのは簡単ではないとよく言われますが、実際には未経験でも採用されている人が一定数います。
では、そうした方々にはどんな共通点があるのでしょうか。
採用された人の特徴を知ることで、自分のアピールポイントや準備すべきことが見えてきます。
そこで!きついと言われる医療事務の仕事に未経験でも受かった人の特徴をまとめました。
未経験でも医療事務を目指したいと考えている方は、これから紹介する内容をぜひ参考にしてください。
【特徴1】医療事務への意欲や仕事理解を面接で示せた人
「未経験でも大丈夫」と求人に書かれていても、実際に受かっている人には共通点があります。それは、仕事に対する理解と“やってみたい”という熱意をきちんと伝えていること。単に「医療に興味があります」では足りません。
たとえば、「患者さんと接するときは不安な気持ちに寄り添いたい」「ミスが許されない仕事だからこそ、正確にこなす自信がある」といった具体的な言葉が面接官の心に残ります(出典:診療報酬の審査・支払業務の流れ)。
事実、医療事務未経験から内定をもらった人の多くが、面接前に仕事内容や1日の流れをしっかり調べ、自分が働く姿をリアルにイメージしていました。中には「まずは受付から始めて、ゆくゆくはレセプト業務にも挑戦したい」と将来のステップまで話せた人もいます。経験はなくても、“知ろうとした姿勢”が評価されるのです。
未経験がハンデになることは確かにあります。ただ、「この人なら学んで育ってくれる」と感じさせた人が、実際に採用されているというのが現場の本音です。
【特徴2】パソコン操作や一般事務スキルを持っていた人
未経験でも医療事務として採用された人の中には、特別な資格よりも「基本的なパソコン操作ができるかどうか」が決め手になったという声が少なくありません。
実際、WordやExcelで文書を作ったり、簡単な表を管理したりといった経験は、医療現場でも重宝されます(出典:参考資料)。特に、予約情報やレセプト関連のデータ入力など、細かな作業をミスなくこなす力は、どのクリニックでも求められるスキルです。
たとえば、事務職で請求書作成をしていた方が、入力ミスの少なさや対応の丁寧さをアピールして採用に繋がった例があります。医療の専門知識がゼロでも、「仕事に対して真面目に向き合える人だ」と印象づけられれば、未経験というハンデは大きな障害にはなりません。
もちろん、単にパソコンが使えるだけでは不十分です。来客対応や電話の受け答えなど、事務職としての基本姿勢が備わっていることも重要です。とはいえ、「医療事務はきついから未経験だと難しい」と感じる人でも、日々の仕事で磨いてきた一般事務スキルが活きる場面は多くあります。
【特徴3】前職経験を医療事務に活かすアピールができた人
医療事務の仕事に未経験から挑戦する人のなかには、「前の仕事がまったく違う業種だから不利かも」と感じる方も多いかもしれません。ただ、実際のところは、過去の職務経験をどう伝えるかが勝負どころです。
たとえば、飲食店やアパレルなど接客業をしていた方なら、「人の気持ちを読み取って先回りする力」や「忙しい中でも丁寧に対応する姿勢」は、受付や窓口対応においてとても重宝されます。実際、接客経験がある人のほうが患者さんとの距離感をうまく取れるという声も、現場からよく聞かれます。
また、オフィスワークの経験がある場合は、ExcelやWordが使えるといったパソコン操作のスキルはもちろん、細かい入力業務に慣れていることも大きな武器です。レセプト処理のように正確さが求められる場面では、そうしたバックグラウンドが活きてきます。
重要なのは、ただ「やってきました」と話すのではなく、「その経験をどう医療事務で活かしたいか」を言葉にして伝えることです。「〇〇の場面で培った△△を、患者さん対応や事務処理で役立てたい」といった具体的なストーリーを面接で語れる人は、採用担当の印象にも残りやすいようです。
とはいえ、自分一人で経験の棚卸しや自己分析を進めるのは簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【特徴4】コミュニケーションが得意で患者対応に自信がある人
医療事務の現場では、単に事務作業ができればいいというわけではありません。むしろ、患者さんと接する時間のほうが長いこともあります。だからこそ、「話を聞く力」や「伝える力」がある人は、未経験でも歓迎されやすいのです(出典:参考資料)。
たとえば、以前に接客や受付業務の経験がある方は、応募の際にその点をアピールすると好印象です。実際、医療事務の求人票を見てみると、「患者対応に抵抗のない方」「コミュニケーション力を重視」といった文言が頻繁に見られます。現場では、初診の患者さんが緊張している様子を察して声をかけたり、高齢の方にゆっくり説明したりと、ちょっとした気配りが仕事の質を左右します。
大事なのは、ただ「人と話すのが好き」と伝えるだけではなく、「どんな場面で」「どう対応してきたか」というエピソードを交えて話すこと。面接では、その人の言葉だけでなく、話すときの姿勢や表情も見られています。だからこそ、自分なりの“患者さんとの向き合い方”を言葉にしておくことが、採用の大きな一歩につながります。
【特徴5】自主的に勉強を続けて必要な知識を深めている人
「経験がないから不利」──確かにそう思うかもしれません。ただ、実際には“やる気”と“準備”でそのハンデは埋められるケースが多いのです。たとえば、医療事務の基本用語を少しでも覚えておいたり、診療報酬の仕組みをかじっておくだけでも、面接官の印象はまるで違ってきます。
事実、医療事務専門の求人メディアなどの採用事例をのぞいてみると、未経験でも「独学で勉強していました」と話せた人が、採用されているケースが多数あります(特に人気のあるクリニックや総合病院では差がつきやすい印象です)。専門学校や高額な講座に通わなくても、市販のテキストや無料のWeb記事でも十分。要は、“本気で学ぼうとしているか”が見られているのです。
ただし、履歴書に「勉強しています」と一言添えるだけでは伝わりません。たとえば、「レセプトの入門書を1冊読みました」や「保険証の種類について整理しました」といった、具体的な学習内容が語れると、グッと説得力が増します。採用側はスキルよりも「学ぶ姿勢」や「地道に続ける力」を重視していることを、どうか忘れないでください。
きつい医療事務の仕事に未経験では採用されないときの対処法5選
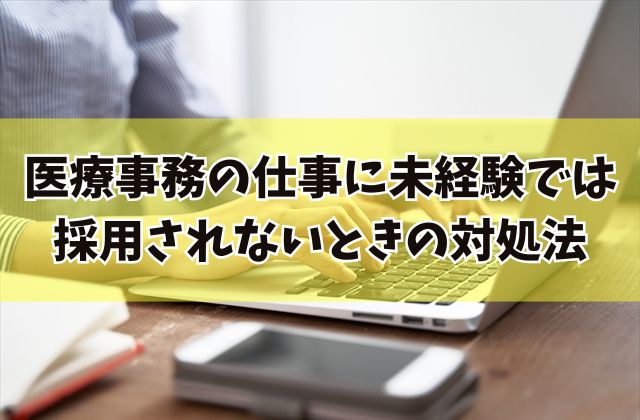
医療事務に未経験から挑戦したいと思っても、「経験がないから不採用」と壁にぶつかることがあります。
ですが、落ち込む前にできる工夫はたくさんあります。採用されやすいコツを押さえておけば、たとえ経験がなくてもチャンスは十分にあります。
ここでは、きつい医療事務の仕事に未経験では採用されないときの対処法5選を紹介します。
現実的かつ実行しやすい方法をまとめていますので、これから応募を考えている方は参考にしてください。
【対処法1】未経験歓迎の求人だけを選んで応募する
医療事務に初めて挑戦する方が、最初の壁としてぶつかりやすいのが「なかなか受からない」という現実です。でも、よく見るとその原因は“選ぶ求人”にあります。未経験OKと明記された募集でなければ、書類の時点で足切りされるのは当然。だからこそ、「未経験歓迎」「研修あり」「資格不問」とはっきり書かれている求人だけに絞って応募することが、遠回りに見えて最短ルートです。
たとえば、ランスタッドでは「医療事務 未経験」で検索するだけで、東京都内だけでも200件近くの求人が出てきます。リクルートエージェントでは「業種未経験歓迎」の医療事務求人が180件以上もヒットしました。これだけ数があれば、いまのあなたに合う職場が必ず見つかります。
ただし注意点もあります。未経験歓迎とは書いてあっても、レセプト請求や保険点数の計算など専門的な業務が求められるケースもあります。仕事内容の欄をしっかり読み、いきなり難易度の高いポジションを避けるのが無難です。
そして最後にもうひとつ。応募書類では「なぜ医療事務をやりたいのか」「今までの経験がどう活かせるのか」を、あなたの言葉で丁寧に伝えましょう。接客や事務の経験、誰かをサポートして喜ばれた思い出。そうしたエピソードが、履歴書の文字に温度を与え、あなたという人を採用担当に届けてくれます。
もし、より多くの求人の中から“自分に合った仕事”を選びたいなら派遣会社の複数登録も視野に入れてみてください。
具体的に派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【対処法2】医療事務の資格を取得して応募書類で強みを出す
「未経験だから不利かもしれない…」と感じているなら、資格の力を借りてみるのも一つの手です。特に医療事務関連では、「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)」「診療報酬請求事務能力認定試験」など、実務に直結する内容を学べる資格が複数あります。実際に求人票を見ても、資格保持者を歓迎している職場は珍しくありません。
とはいえ、資格をただ持っているだけではアピールとして弱くなってしまいます。大切なのは「その資格を通して何を学び、どんな姿勢で取り組んできたのか」を自分の言葉で伝えることです。たとえば、「医療用語の基礎知識を身につけた」「レセプト作成の流れを学んだ」といった具体的な内容を盛り込むと、読む側にもイメージが伝わりやすくなります。
さらに、履歴書や職務経歴書に資格名を書く際は、略称ではなく正式名称を記載するのがポイントです。資格の信頼性が伝わりやすくなるだけでなく、細かいところまで配慮できる人だという印象も与えられます。未経験という壁は、丁寧な準備と伝え方次第で乗り越えられます。資格はその第一歩として、しっかりと活かしていきたいところです。
【対処法3】履歴書・職務経歴書で前職のスキルを医療事務に結びつけて書く
「未経験歓迎」と書かれていても、応募書類がぼんやりしていると面接にはなかなか進めません。医療事務の経験がなくても、前職で身につけたスキルをどう活かせるかを伝えることが、採用担当者の目に留まる第一歩です。
たとえば、接客業で働いていたなら、「初対面の人に丁寧に対応する力」や「ミスを防ぐための確認作業の徹底」は、受付対応やカルテ入力で必ず役に立ちます。事務職なら、電話応対・パソコン操作・書類管理など、まさに医療事務に直結するスキルです。
職務経歴書を書く際は、単に仕事内容を書くのではなく、「どんな工夫をしたか」「どんな成果があったか」まで書けるとより具体的になります。そして最後に、それらの経験がどう医療事務で活かせるかを自分の言葉でつなげましょう。
経験の浅さは視点の変え方でカバーできます。過去の仕事を振り返り、自分だけの“武器”を応募書類に込めてみてください。それが、採用につながる一歩になるかもしれません。
とはいえ、自分一人でスキルの棚卸しや自己分析を進めるのは簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【対処法4】面接で志望動機をしっかり準備して自分の言葉で伝える
未経験から医療事務に挑戦するなら、「なぜ医療事務を選んだのか」という想いを、しっかり言葉にして面接で伝えることが大切です。中でも重要なのは、どこかで拾ってきたようなテンプレートではなく、自分自身の経験や考えから出てきたリアルな動機を語ること。応募先の採用担当者は、あなたの“気持ち”を見ています。
たとえば、過去に接客業をしていた方であれば、「お客様の表情を見て先回りして動く力」を、医療現場での患者対応にどう活かしたいかを語ってみるのも良いでしょう。「ありがとう」と言ってもらえる瞬間にやりがいを感じてきたことがあれば、それを正直に伝えてみてください。
実際、転職支援サイトなどでも、医療事務未経験者の面接では「どう貢献したいのか」「学んだことをどう現場で活かしたいか」が具体的であるほど評価されやすいと紹介されています。資格取得に向けて勉強しているなら、その努力も強みとして伝えてください。
大切なのは、「未経験だから自信がない」ではなく、「未経験だからこそ意欲を持って飛び込みたい」という前向きな気持ちを、自分の言葉でまっすぐ伝えること。たとえ完璧な答えでなくても、“自分の頭で考えてきた”ことが伝われば、面接官の心に届きます。
【対処法5】派遣やパートなど非正規だが経験を積める雇用形態を狙う
「未経験でも医療事務をやってみたい」と思っても、正社員の壁は高く感じてしまうかもしれません。けれど、実は派遣やパートという働き方のほうが、最初の一歩には向いている場合があります。
医療事務の求人を見ていると、「未経験OK」「研修あり」「無資格でも可」などの条件が付いたものが、派遣やパートには意外と多く見つかります。実際、スタッフサービスやランスタッドといった大手派遣会社でも、そういった求人を常時掲載しています。短時間勤務や週3日勤務といった柔軟な働き方も選べるので、子育て中やブランク明けの方にも挑戦しやすい環境が整っているのです。
しかも、こうした非正規の仕事でも、受付やカルテ入力、レセプトの補助業務など、実務を通して医療事務の基礎を身につけていくことができます。経験ゼロから始めても、数ヶ月働けば履歴書に「医療事務経験あり」と書けるようになりますし、派遣先によっては正社員登用の道が開かれていることも。
大切なのは、「派遣だから」「パートだから」とあなどらず、実務経験を積む場として前向きに活用することです。今は“入口”でしかなくても、地道に経験を重ねれば、きっとその先に広がりが見えてきます。
そして、仕事獲得の確率を上げるなら派遣会社の複数登録も視野に入れてみてください。
具体的に派遣会社の登録は、紹介スピードや求人の幅を広げるためにも、相性の良い担当者と出会えるよう2~3社に登録しておくのがおすすめです。
実際、7割以上の派遣社員の人が、2社以上の派遣会社に登録している調査結果もあるほど。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
未経験でも医療事務や事務職デビューが叶う!おすすめ求人サイト3選
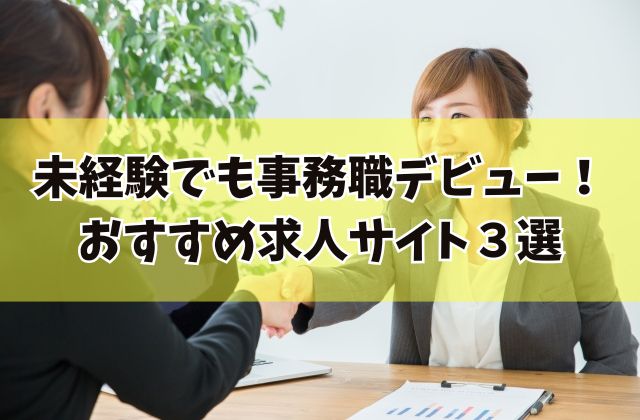
医療事務はじめ事務職は「未経験だときつい」と感じる方も多い一方で、実は最初の一歩を後押ししてくれるサービスも充実しています。
そこで「未経験でも医療事務や事務職デビューが叶う!おすすめ求人サイト3選」を厳選しました。
初心者向けの求人が多く掲載されていて、福利厚生や研修制度も充実した信頼性の高い求人サービスを厳選して紹介します。
【おすすめ1】マイナビキャリレーション
「事務職に挑戦したいけれど、経験も資格もない…」そんな不安を抱えている方にまず勧めたいのが、『マイナビキャリレーション』です。未経験から事務職の仕事を目指す方に向けて、実践的な研修と手厚いサポート体制が整っている点が強みです。
特徴的なのは、入社前に受けられる基礎研修。WordやExcelといったパソコンスキルの基本から、ビジネスマナー、電話応対まで、これまで事務職に縁がなかった方でも安心してスタートできます。
配属前の面談では、担当者と一緒に希望や適性をすり合わせながら、自分に合った職場を探せるのも安心材料のひとつです。加えて、配属後もフォローアップ体制が整っており、職場での悩みや不安を随時相談できる環境が用意されています。
ただし「無期雇用派遣」という働き方のため、正社員と完全に同じ待遇とは限りません。福利厚生や昇給制度など、求人ごとの条件を事前に確認しておくことが大切です。
未経験から事務職に一歩踏み出すなら、マイナビキャリレーションは間違いなく有力な選択肢のひとつです。安心して一歩を踏み出したい方は、ぜひ一度公式サイトをチェックしてみてください。
【おすすめ2】ランスタッド
「医療事務って、未経験だと本当に無理なのかな…?」そう感じている人にとって、『ランスタッド』は心強い味方になります。大げさな話ではなく、経験ゼロ・資格なしでも応募できる医療事務の求人が、実際に公開されているのです。
たとえば、茨城県つくば市のある病院では、保険証の確認や受付業務など、比較的シンプルな仕事を任せてもらえる案件があり、しかも週5日勤務・残業なし・土日祝休みという働きやすい条件が整っています。時給は1,300円、交通費も支給され、制服も貸与されるので、初期費用がかかる心配もありません。
それだけでなく、ランスタッドが扱う医療事務の求人は、研修制度がしっかりしているケースが多く、右も左もわからないまま業務に放り込まれる…というような心配も無用です。むしろ「未経験だからこそ、丁寧に教えてもらえる」という安心感のある環境が整っているところも多く見られます。
ただし注意点として、こうした求人の多くは「長期派遣」という働き方になるため、将来的に正社員を目指したい方は、事前にキャリアの相談をしておいた方がいいかもしれません。とはいえ、現場経験を積むには申し分のないスタートラインです。
医療事務の仕事に一歩踏み出すなら、「未経験歓迎」に力を入れているランスタッドの求人情報は一見の価値があります。現場に飛び込む前に、どんな仕事なのか、どんな人が働いているのかをチェックして、自分の働き方に合うか見極めてみてください。気負わず、でも一歩ずつ確実に——そんなスタートにぴったりです。
【おすすめ3】テンプスタッフ
「医療事務にチャレンジしたいけど、未経験だし不安でいっぱい…」という方には、『テンプスタッフ』がかなり頼れる存在になるはずです。実際に求人サイトを見てみると、未経験歓迎の医療事務案件がずらりと並び、しかも勤務条件が柔軟なものばかり。週4日勤務や残業なしといった働き方ができるのも、毎日忙しい人にとっては大きな安心材料です。
たとえば、都内のあるクリニックでは「未経験OK」「週4日」「残業なし」「駅チカ」と、はじめてでも無理なく馴染めそうな条件が整っていました。さらに、就業前の研修や職場でのフォロー体制がしっかりしているので、「いきなり任されて戸惑う」という心配も少なめです。
もちろん、派遣という雇用形態にはメリットもデメリットもあります。正社員とは違って契約更新が前提ですし、福利厚生や賞与面では差が出ることも。ただ、それ以上に「実際の医療現場で経験を積める」という点は、これから医療事務を目指す人にとって大きな価値になるのではないでしょうか。
医療事務は、未経験から始めるには少し“きつい”と感じやすい職種ですが、こうしたサポート体制が整った派遣求人をうまく活用すれば、最初の一歩がずいぶん軽くなるはずです。まずはテンプスタッフの求人を覗いて、気になる案件があるか確認してみると良いと思います。
【Q&A】未経験にとってはきついと言われる医療事務に関するよくある質問

最後に未経験にとってはきついと言われる医療事務に関するよくある質問をまとめました。
実際に多く寄せられている疑問や声にお答えしていきます。「本当に未経験でも大丈夫なのか?」「続けられるのか?」といったリアルな不安の解消につながる内容を、できる限りわかりやすくまとめています。
【質問1】医療事務は未経験でも大丈夫?
まったくの未経験でも医療事務の仕事は目指せます。実際、求人を見ていると「未経験歓迎」の文字がしっかり記載されているケースは少なくありません。
医療事務には法律上の必須資格がないため、「育てる前提」で採用してくれる職場も多いのが現実です(出典:厚生労働省所管国家資格一覧)。加えて、医療業界は人の出入りが激しく、チャンスが生まれやすい業界でもあります。
最低限のパソコン操作や事務経験があれば土台としては十分。保険制度などの知識は、現場でのOJTや研修を通じて少しずつ身につけていけます。「経験がないから無理かも…」と感じている方も、一歩踏み出す価値はあります。
【質問2】医療事務は何年で辞める人が多いですか?
職場によりますが、医療事務は「数年以内に辞める人が一定数いる」仕事です。厚生労働省の統計(新規学卒就職者の離職状況)を見ると、医療・福祉分野の新卒3年以内離職率は、大学卒で約41%、高卒では約49%と高めの水準。
つまり業界全体として、入職も多いけれど離職もそれなりに多いという傾向です。入ってみて「思っていたより大変だった」というギャップが原因になることも。
とはいえ、職場によっては教育体制やフォローがしっかりしていて、長く続けられる環境もあります。どの病院やクリニックを選ぶかが、離職率を左右する大きなカギになるのです。
【質問3】「医療事務は難しいから辞めたい」と感じる主な理由は?
辞めたくなる理由の多くは、「仕事量の多さ」と「見合わない待遇」に集約されます。受付対応に加えてレセプト処理、保険の確認など業務が重なりがちで、しかも制度変更があればその対応も求められます。
ある求人メディアのアンケートでは、「人手不足」「上司との人間関係」「給与の不満」が辞めたい理由のトップ3でした。特に未経験から入ると、最初の壁が厚く感じやすいです。
ただし、負荷を減らす工夫をしている医療機関も存在します。見極めのポイントは、入職前に「教育体制の有無」「業務の分担がされているか」をチェックすること。そこを外さなければ、無理なく続けられる職場と出会えます。
【質問4】「医療事務は未経験にとって難しい」に対する知恵袋の意見は?
知恵袋では、「未経験には確かに大変だが、やっていける」という声が多く見られます。「保険制度やレセプトは最初こそ取っつきにくいけれど、実務を通じて徐々に慣れていった」という体験談も複数ありました。
中には「受付や会計から覚えて、レセプトは後から勉強すればいい」と段階的なステップをすすめる意見も。要は、焦らずに「今できることから取り組む」という姿勢が鍵です。
未経験OKの求人を選んで応募し、入社後に基礎から教えてくれる環境なら、少しずつ成長できます。知識よりも、学び続ける姿勢のほうが大切だと感じている人も多いようです。
以下の派遣会社はすべて登録無料で、福利厚生や研修制度も充実。まずは気になる会社から気軽に登録して、自分にぴったりの働き方を見つけてみてください。
✅【無料】未経験OKの求人多数!福利厚生&研修制度が充実した派遣会社おすすめ3選
- オンライン完結で気軽に仕事を探すなら『ランスタッド』|70項目以上のこだわり条件から自分に合った仕事をLINEで気軽に探せる!充実の福利厚生制度・キャリアサポートも整った安心のお仕事探しサイト。
- 6年連続総合満足度No.1『テンプスタッフ』|求人数は業界トップクラス!「残業なし」「通勤30分以内」など希望に沿った働き方をできて、仕事紹介~就業中までずっとサポートしてくれる安心の大手派遣会社。
- 在宅勤務OKの求人多数『アデコ』|社員を目指せる紹介予定派遣や無期雇用派遣も可能!単なる仕事紹介だけでなく、一人一人に合った将来のキャリアについても相談・支援を受けられる総合人材サービス企業。
【質問5】「医療事務は大変」に対するガールズちゃんねるの反応は?
ガルちゃんでは、「想像以上に大変だった」という本音が数多く投稿されています。
たとえば、「マイナンバー関連の制度説明で怒られた」といった窓口のトラブルや、「何でも屋みたいで精神的に疲れる」といったコメントが目立ちます。一方で、「10年以上続けてる」「今の職場は人間関係も良くて定着率が高い」など、継続して働いている人の声もありました。
つまり、「職場次第で天国にも地獄にもなる」職業だということ。求人票だけでは見えない現場のリアルを、口コミや面接時の質問で少しでも多く拾い上げる姿勢が、長く働ける環境を見つけるヒントになります。
まとめ:医療事務は未経験だときつい仕事と言われる理由と向いている性格
医療事務は未経験だときつい仕事と言われる理由と向いている性格をまとめてきました。
改めて、医療事務は未経験だときつい仕事だと言われる8つの理由をまとめると、
- 覚えることが非常に多く慣れるまで時間がかかるから
- レセプト請求など専門的な知識が必要な業務があるから
- ミスが許されない責任ある業務でプレッシャーが大きいから
- 患者さんからのクレーム対応で精神的な負担が大きいから
- 人手が少ない職場で業務負担が偏ることがあるから
- 給料が仕事内容に比べて低く感じることがあるから
- 連休や希望休が取りにくい職場も存在するから
- 法律や制度が変わるたびに学び直しが必要だから
そして、医療事務は未経験だときつい?5つの結論もまとめると、
- 未経験でも医療事務の求人は多く、挑戦のチャンスは十分にある
- 仕事内容は多岐にわたり、専門知識の習得に時間がかかる
- レセプト業務やクレーム対応など、精神的な負担がかかる場面もある
- 感謝される機会が多く、やりがいを感じながら長く続けられる職場も多い
- サポート体制のある派遣会社を通じた就業なら、初めてでも安心して始めやすい
医療事務は未経験からスタートすると「きつい」と感じやすい仕事ではあります。
ですが、実際には働きながら学べる環境や未経験歓迎の求人も多くあります。
正しい情報とサポートを得て、無理なく一歩を踏み出すことが成功への近道です。