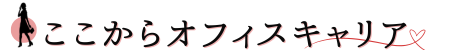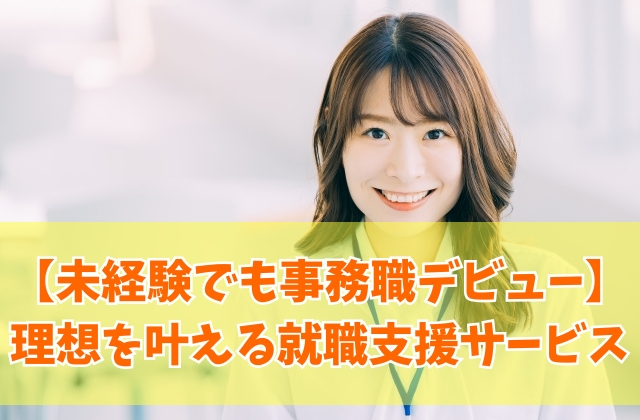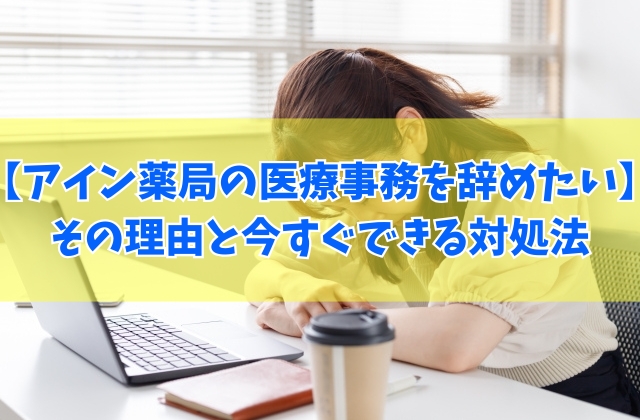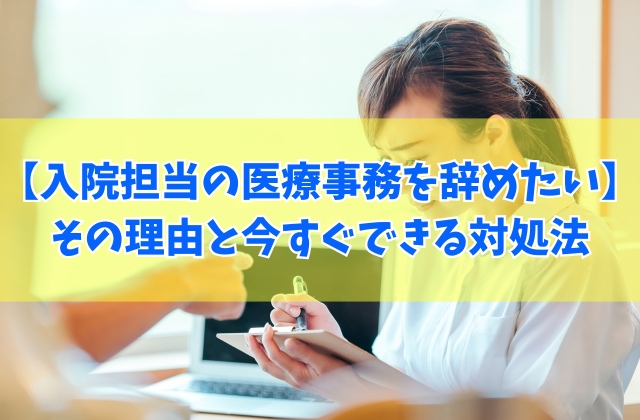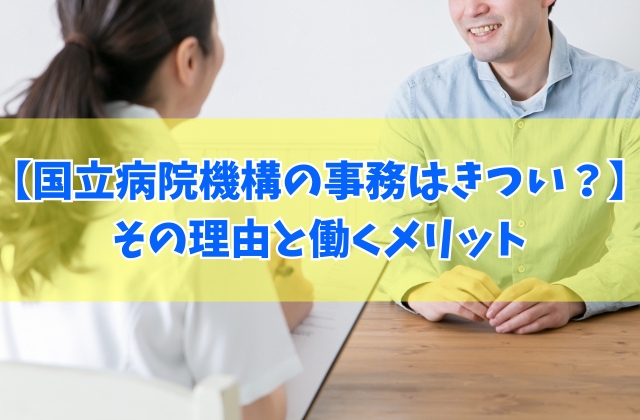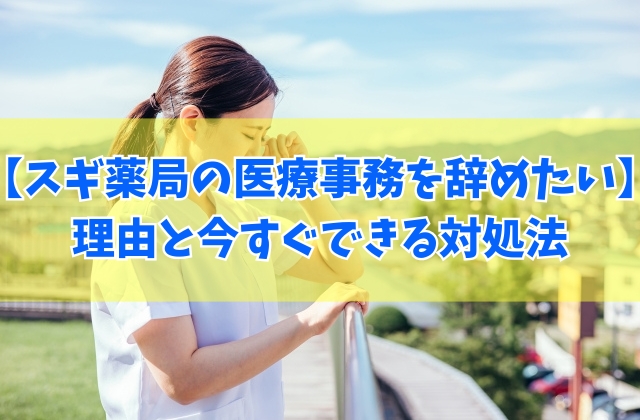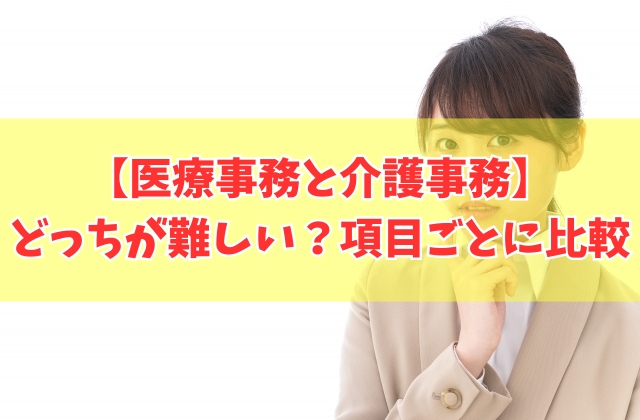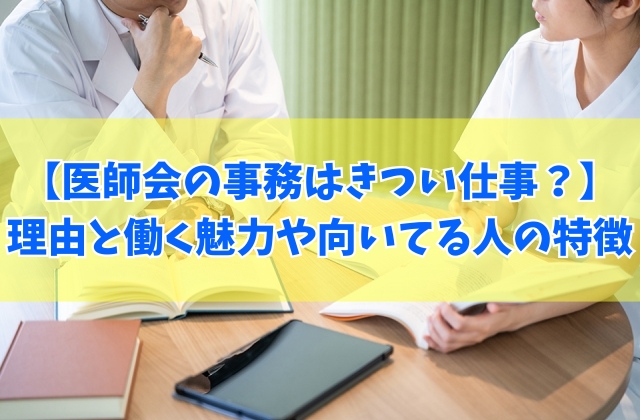
「医師会の事務はきつい仕事ってホント?」
「どんな人に向いてる仕事?事務職就職は未経験だと難しいのかな?」
「医師会の事務って、実際どれくらい大変なんだろう?」——そんな疑問や不安を抱えながら求人情報を見ている方も多いのではないでしょうか。
確かに「医師会 事務 きつい」と検索すると、厳しい声も目にします。しかし、仕事内容を深く知れば、単なるネガティブな印象だけでは語れない魅力も見えてきます。
この記事では、医師会の事務職が「きつい」と言われる理由や、実際に働く上でのやりがい、向いている人の特徴まで、転職や就職を考える方に役立つ情報をわかりやすく解説していきます。
- 業務が多岐にわたり、雑務や突発対応で忙しさを感じやすい
- 会員医師や関係者への対応は責任が伴い、気を張る場面が多い
- 制度や医療知識の継続的な学習が必要で、習得に時間がかかる
医師会の事務は、確かに「きつい」と感じる要素がいくつかあります。
ただし、仕事内容を把握し、自身に合った準備や対策をしておけば、大きなやりがいや成長にもつながります。「医師会の事務はきつい」と感じる前に、適性や職場環境を正しく見極めることが大切です。
とはいえ、医師会の事務の仕事内容を把握できても、次のような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
「未経験から事務職に転職したいけど、スキルや経験が不足していると感じる」
「安定した雇用形態と収入を得たいけど、適切な求人が見つからない。。」
「仕事とプライベートを両立させ、充実した生活を送りたい!」
これらの悩みや不安を解消し、あなたの理想の働き方を実現するのが『マイナビキャリレーション』です。
マイナビキャリレーションは、未経験から事務職へ転職を目指す方を支援するサービスです。充実の研修制度や無期雇用派遣による安定した働き方を提供し、スキルアップとキャリア形成を全面サポートします。
- 未経験からの事務職就職をサポート
マイナビキャリレーションでは、事務未経験の方でも安心してスタートできるよう、充実した研修制度を提供しています。ビジネスマナーやコミュニケーションスキル、OAスキルなど、基礎から学べる環境が整っています。 - 安定した雇用と収入
無期雇用派遣社員としての採用により、雇用期間の制限がなく、安定した収入を得ることが可能です。さらに、賞与や昇給制度も整っており、長期的なキャリア形成を支援します。 - 仕事とプライベートの両立
週休二日制や各種福利厚生が充実しており、プライベートも大切にしながら働くことができます。産前産後休暇や育児休業などの制度も完備しており、ライフステージの変化にも柔軟に対応できます。
これらの特徴やメリットにより、マイナビキャリレーションは、事務職への就職・転職を目指すあなたの不安を解消し、安定した働き方とプライベートの充実を実現する最適な選択肢となります。
“こんな働き方がしたかった”を、マイナビキャリレーションで実現しませんか?
医師会の事務の仕事内容について

医師会の事務は、医療現場の最前線ではなく、その裏側で地域医療を支える大切な役割を担っています。
事務職に就職・転職を考えている人や、医師会の事務はきついのかどうか調べている人にとって、「医師会の事務の仕事内容について」理解することは、仕事選びの判断材料になります。
日々の業務では、会員医師への案内業務や、研修会の準備、電話応対といった庶務を通じて、医療環境をスムーズに支えることが求められます。
ここでは、その具体的な医師会の事務の業務内容を、主に3つ丁寧に紹介します。
【内容1】会員医師への連絡調整や案内業務
医師会の事務として働く中でも、とくに気を使うのが「会員医師への連絡や案内」の仕事です。医療現場で日々忙しくしている先生方へ、研修会や会議の予定を正確に届けることは、思っている以上に繊細で緻密な作業になります。
例えば、福井市医師会では健診や予防接種の申込受付から、医師宛の事務連絡まで事務職が幅広く対応しているようです。また、青森県医師会では講師のスケジュール管理や周知文書の作成など、調整業務が非常に多岐にわたることがわかります。
日程が変更になった際には、すぐに修正を加え、誰にどう伝えるかを瞬時に判断しなくてはいけません。ミスひとつで混乱が起こるため、丁寧さとスピードのバランス感覚が求められる場面も多くあります。
単なる「お知らせ」ひとつでも、その裏には多くの確認と配慮が詰まっている——そんなふうに思えるようになったのは、この業務に本気で向き合ってからです。
【内容2】研修会や会議の企画準備と受付対応
研修会や会議の準備って、正直かなり気を使います。医師会で事務として働いていた知人も「この業務こそ現場の信頼を左右する」と話していたほど。単に日程を決めて案内を出すだけじゃなくて、講師との連絡、資料の用意、座席の配置、受付対応まで一手に引き受けるからです。
実際、福井市医師会では会議の企画から進行サポートまで事務職が関わっていて、青森県医師会でも、スケジュール調整や会場設営など幅広く任されているそうです。つまり、会の裏方というより、進行の土台を整える“縁の下の現場ディレクター”なんですよね。
当日、参加者の表情がほっと緩む瞬間を見ると、「無事に整えられてよかった」と心の中でひと息つける。派手さはないけれど、確かに必要とされている仕事だと感じられる時間です。
【内容3】電話応対や文書作成などの庶務全般
「庶務」とひとくちに言っても、実際は見た目以上に気力を使います。特に医師会の事務では、電話応対や文書作成が単なる“作業”で終わることはありません。声ひとつ、言い回しひとつが、相手との関係性を左右することもあるからです。
たとえば、墨田区医師会では会議録や郵送書類の手配に加えて、Zoomでのオンライン会議サポートまで担当しているとのこと。中央区医師会の募集要項にも、来訪対応や会議準備など、まさに“なんでも屋”のような役割が記載されていました。こうした業務は一見地味に思えるかもしれませんが、どれも「誰かの動きやすさ」をつくる仕事です。
実際、かかってきた一本の電話にどう返すかで、相手の印象はがらりと変わります。「安心できる」「丁寧だな」と思ってもらえたとき、ようやく自分の仕事が少しだけ報われるような気がします。
文書も同じで、送る相手の立場や気持ちを想像しながら、言葉を整えていく作業の連続。手を抜こうと思えばいくらでも抜ける。でも、そこに気を配れる人がいるからこそ、医師会全体の信頼は保たれているのだと感じています。
医師会の事務はきついと言われる7つの理由
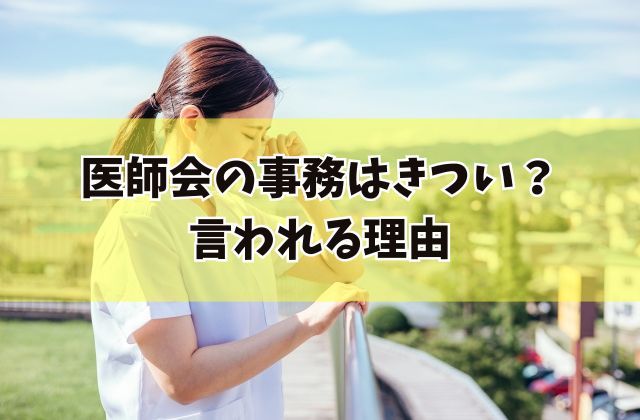
医師会の事務は一見すると穏やかに見えますが、実際には多岐にわたる業務を限られた人数でこなす必要があり、精神的にも体力的にも負担がかかりやすい職場です。
特に医師や地域の関係者と日常的にやり取りするため、常に緊張感を持って対応する場面も多くあります。
ここでは、「医師会の事務はきついと言われる7つの理由」について具体的に掘り下げていきます。
【理由1】電話応対や文書作成など雑務が多く雑然とするから
医師会の事務は、誰が見ても“裏方”です。でも、その裏側には、見えないほど細かい雑務が無数に転がっています。
たとえば、朝イチで来たファックスに対応しながら、研修案内の文書をつくって、途中で会員医師からの電話が鳴る。内容を聞いていたら、今度は「今から来客があるので対応してほしい」と声がかかる。そんなふうに、いくつもの業務が同時進行で動き出すのです。
福井県医師会の求人では、資料の作成、データ入力、電話受付、さらには庶務まで幅広く担当すると明記されていました。また、ある地区医師会では、名簿の更新や会議資料の差し替えなど“気づいた人がやる”スタイルが色濃く残っているという声もあります。
そうなると、目の前のタスクを片付けるだけで精一杯。整然と机に向かって書類仕事をする……というイメージとは、だいぶかけ離れているのが実情です。
「医師会の事務はきつい」と言われる理由のひとつには、こうした“終わりが見えない細かい雑務の山”があるのかもしれません。
【理由2】会議やイベント準備で時間外業務が発生しやすいから
医師会の事務で何より大変だと感じるのは、定時を過ぎたあとに始まる“本番の準備”です。表には出ませんが、夕方以降からがむしろ忙しいという日もあります。
会議の資料を人数分揃え、座席表を確認し、プロジェクターの動作確認まで行う。日中の通常業務と並行してこれらをやるのは、正直しんどいです。ある求人票には「研修・講演会の準備や進行管理あり」と書かれていて、遅い日は21時頃まで勤務と明記されていました。これは決して例外ではありません。
月に10時間前後の残業が出ることもあるようですが、それよりもきついのは、仕事の“終わりどき”が自分で決められないことかもしれません。誰かのスケジュールやイベントに合わせるのが前提の職場なので、準備に区切りをつけにくいのです。
もちろん全部が毎日ではありません。ただ、こうした勤務の積み重ねが、「医師会の事務ってきついよね」という声につながっているのは言うまでもありません。
【理由3】少人数体制で一人当たりの負担が大きいから
医師会の事務は、「人が少ないわりに、やることが多い」。実際に働く人の口から、そんな声をよく聞きます。
例えば千葉県医師会のとある求人には、部署内の人数が6名と明記されていました。その中で、文書作成から会員対応、外部との連絡まで幅広く担うことを求められるとのこと。目黒区の事務局では、わずか数名のスタッフで健診や地域の診療所運営まで支えていると紹介されています。どちらも共通しているのは「少人数で全体をまわしている」という点です。
誰かが休んだ日、電話が立て込んだ日、資料が山積みになった日——。そんなとき、誰の手も借りられず、ひとりでいくつもの役割を引き受けることになります。「できる人がやる」ではなく、「やれる人しかいない」。そんな職場のリアルがあります。
一人ひとりが頼られ、そして背負う。そういう意味で、医師会の事務は甘くない仕事だと断言できます。
【理由4】会員への対応一つひとつに責任が伴い緊張するから
「たった一言でも、伝え方を間違えたら大問題になる」——医師会の事務に就いた人が、口を揃えてそう語る理由はここにあります。日々のやり取りの相手は、多くが医師や医療関係者。忙しい中での連絡や依頼には、正確さと気遣いが欠かせません。
特に医師会のような公的色の強い組織では、会員に配布する通知文書ひとつ取っても、誤字や伝達ミスが大きな信頼損失につながります。実際、医師会事務局では、法制度の改正内容を会員へ分かりやすく伝えるための資料作成を担うこともあるとされています。
このように、一文一語に神経を使う仕事が医師会の事務では日常的に求められるのです。
電話の声色、メールの文面、すべてが「会の代表」としての立場になる以上、どこか気が抜けない。それが、医師会の事務が「きつい」と言われる根っこの部分かもしれません。
【理由5】医師や地域関係者とのコミュニケーションが難しいから
「医師会の事務って、なんだか地味で穏やかな仕事に見えるよね」と言われることがあります。でも実際に中に入ってみると、その印象は良い意味でも裏切られることが多いんです(出典:参考資料)。
というのも、日々向き合う相手は、地元の開業医や大学病院の医師、行政職員や地域の医療関係者など、多岐にわたります。それぞれに立場も考え方も違うから、ひとつの連絡をとるにも神経を使います。たとえば、研修会の日程を調整するだけでも、「この時期は外してほしい」「こっちは別の会議と重なる」といった要望が飛び交い、まるでパズルを組むような感覚になります。
さらに、医師と接する場面では、“言葉の選び方”が問われる瞬間が多々あります。伝えたつもりの内容が、意図とは異なる形で受け取られてしまうと、信頼関係にヒビが入ることさえあります。それが一番こわい。だからこそ、言葉だけでなく、「温度」や「間合い」にも気を配りながら対応しなければなりません。
決して派手ではない。でも、じわじわと体力も気力も使う。医師会の事務が「きつい」と言われる理由のひとつには、こうした“対人調整力”の難しさがあるのだといえそうです。
【理由6】医療知識の習得・学習が常に求められるから
医師会の事務に就くと、単なる書類仕事だけでは終わりません。医療や制度のことを「知らないでは済まされない」場面が、想像以上に多くあります。たとえば会員医師から「〇〇研修の要件って今年から変わってたよね?」と訊かれたとき、正しく答えられないと信頼を損なう恐れもあるのです。
実際、日本病院会が提供する「医師事務作業補助者研修」は、32時間の基礎講座に加え、診療録の知識、医療法規、電子カルテ操作など幅広く網羅されています。必要とされる知識の厚みは、民間企業の一般事務とは次元が異なります。
「医療に関わるからには、自分も勉強を怠れない」。そんな気持ちが自然と芽生える職場です。簡単ではないけれど、学ぶことに前向きな人にとっては、成長できる環境でもあります。
【理由7】制度変更や書類申請対応に継続的な更新が必要だから
「また変わったのか…」というのが、医師会の事務をしていると本音として出てしまう瞬間です。医療制度は年単位、時には数ヶ月単位で細かく改定され、そのたびに書類の様式や提出先、締め切りなどが微妙に変わります。何年も慣れた業務フローが、翌年には通用しないなんてことも、珍しくありません。
特に「認定医の申請手続き」や「保険制度に関する資料作成」は、最新の要領に沿っていなければ門前払い。例えば、現在では医師会会員情報システム「MAMIS(マミス)」の導入が進んでおり、紙の申請書類と電子申請の双方に対応する必要がある時期もありました(出典:参考資料)。厚労省の資料では、2025年中に完全電子化を見込んでいるため、今はその過渡期。二重対応で現場が混乱するのも無理はありません(出典:参考資料)。
しかも制度変更は通知一枚で突然やってきます。会員から「どうなってるの?」と電話が入る前に、こちらが先に把握して、丁寧に説明できるよう準備しなければなりません。地味に見えるかもしれませんが、情報収集力と柔軟な対応力が問われる、かなり“神経を使う仕事”なのです。
本当にきつい?医師会の事務で働く5つの魅力

医師会の事務と聞くと「きつい」という声に目が向きがちですが、その一方で実は多くの魅力が詰まった仕事でもあります。
安定性や地域医療への貢献、やりがいのある人間関係など、働く中で得られる価値は決して小さくありません。
本当にきつい?医師会の事務で働く5つの魅力を通じて、実際の働き方や感じられる充実感について紹介します。
ネガティブなイメージだけで判断する前に、プラスの側面にも目を向けてみてください。
【魅力1】安定した職場環境で将来も安心して働ける!
「転職するなら、長く続けられる場所がいいよね」。医療業界に詳しい知人が、ぽつりと漏らした言葉が今も耳に残っています。実際、医師会の事務職はその言葉を体現したような職場でした。
たとえば、新宿区医師会の求人では、年間休日120日以上、土日祝休みの完全週休2日制に加え、賞与は年4.6ヶ月分と明記されています。残業も月平均10時間程度と控えめで、事務職としてはかなり働きやすい条件です。ほかにも川崎市医師会では、未経験からでも安心して始められる体制が整っており、福利厚生も民間企業並みに充実しています。
実務はもちろん簡単ではありませんが、「腰を据えて働ける環境がある」というのは、日々の不安を和らげてくれる大きな支えになります。派手さこそないものの、着実に日々を積み重ねられる安心感。医師会の事務は、そんな“地に足のついた安定”を求める人にこそ向いている仕事かもしれません。
【魅力2】福利厚生や休暇制度が整い安心して働ける!
「事務職として長く続けたい」と考える人にとって、福利厚生と休暇制度は、給与以上に大きな安心材料になるかもしれません。医師会の事務はその点で、かなり恵まれた環境だと感じます。
実際、たとえば益田地域医療センター医師会病院では、完全週休2日制に加えて年間休日が123日。誕生日休暇や積立傷病休暇など、ちょっと珍しい制度も用意されています。単に休めるだけでなく、「いざという時に守ってもらえる」という安心感があるんです。
他にも、鹿児島市医師会病院では、出産・育児に関する制度が非常に手厚く、院内に託児所を完備。さらに職員のキャリアアップ支援まで行っており、ライフステージが変わっても働き続けられる仕組みが整っています。
こうした制度の背景には、長く働いてもらいたいという組織の本気度が見え隠れしています。「休める・支え合える・挑戦できる」そんな三拍子がそろった職場であれば、事務職としてのキャリアに安心して踏み出せるはずです。
【魅力3】地域の医師と連携し地域医療に貢献できる!
「自分の仕事が、誰かの命を守る一助になっている」——そんな実感を持てる職場は、そう多くありません。けれど、医師会の事務として働いていると、その重みをふと感じる場面があるのです。
たとえば、地域の開業医と総合病院の間で患者さんの紹介を調整したり、医療機関同士の連絡をつないだり。電話の一本、メールの一文が、患者さんの命をつなぐ大事な橋渡しになることも少なくありません。日々の事務仕事は一見地味ですが、その先には確かに“医療の現場”が息づいています。
青森県医師会の広報資料でも、スタッフのひとりが「医師や医療機関をサポートし、間接的に地域医療に貢献できる」と語っています。実際、病院の連携室や地域医療部門では、事務職が担う役割がとても大きいのです。
派手な成果が目に見えるわけではないけれど、「ありがとう」と言われる瞬間がある。地域に必要とされる実感がある。そんな静かな誇りを感じながら働けるのが、医師会事務の仕事の大きな魅力だと思います。
【魅力4】多彩な業務で事務スキルと対応力が身につく!
医師会の事務というと、なんとなくデスクに向かって淡々と書類を処理する仕事をイメージするかもしれません。けれど、実際にその現場に足を踏み入れると、そのイメージは軽く裏切られます。
たとえば、ある日は医師向けの研修会の運営に関わり、別の日には行政との調整役になっていたり。もちろん、電話応対や文書作成などの基本業務もこなすわけですが、そのどれもが決して“ルーティン”には収まりません。
実際、大阪府医師会など一部の地域では、5~6年ごとに担当部署が変わる体制がとられており、そのたびに違う業務領域に携わることで自然と視野も広がっていくそうです。いわば、一つの組織にいながら、複数の職場経験を積んでいくような感覚。これは、事務職としてはなかなか珍しい環境です。
変化に富んだ毎日を通して、段取り力や柔軟な対応力はいつの間にか鍛えられていきます。そして気づけば、「こういう場面では、こう動けばうまくいく」という自分なりの引き出しが、少しずつ増えていくのです。単なる事務では終わらない、この仕事の“深さ”こそが、医師会で働く面白さのひとつと言えるでしょう。
【魅力5】感謝される機会が多くやりがいを実感できる!
「事務なんて裏方でしょ?」とよく言われます。でも実際に医師会の事務として働いてみると、その印象は大きく変わります。会議の準備や資料作成、スムーズな連携を支える日々の調整──そうした地道な仕事の積み重ねに対して、現場の医師から「本当に助かったよ」と声をかけられる瞬間があるんです。そのひと言に、肩の力がふっと抜けて「また明日も頑張ろう」と思える。そういう実感が、確かにあります。
実際、医師事務作業補助者として働く方々の声を集めたインタビュー記事でも、「先生の手を少しでも空けられるように支えるのが自分の役割」と前向きに語る人が多く見られます。また、「仕事の中で感謝されると、自分の存在意義を感じられる」と答えるスタッフも複数いました。
直接医療を行うわけではないけれど、関わる人たちの“ありがとう”に日々支えられ、誇れる仕事になっていく──医師会の事務には、そんな静かなやりがいが宿っています。
きついと言われても医師会の事務に向いている人の特徴
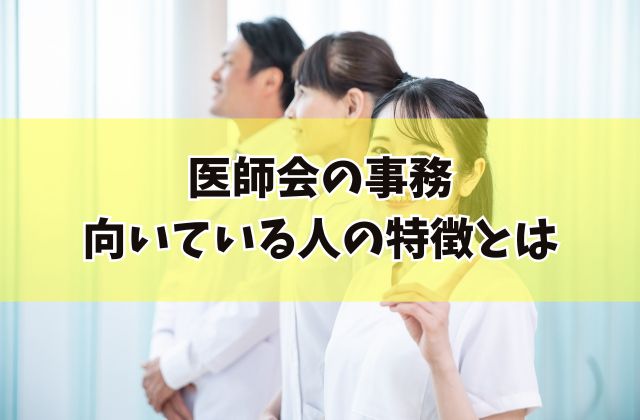
医師会の事務は「きつい」と言われることが少なくありませんが、それでも前向きに続けている人たちがいます。
共通しているのは、業務の大変さ以上に「やりがい」や「達成感」を感じている点です。
向いている人の特徴を知ることで、自分が適性に合っているかどうかを見極める手がかりになります。
これから紹介する内容を通して、医師会の事務という仕事に対する理解が深まるはずです。
早速、その具体的なきついと言われても医師会の事務に向いている人の特徴を紹介していきます。
【特徴1】コミュニケーションを大切にできる人
医師会の事務職に向いているのは、手際のよさよりも「人とのやりとりを丁寧に重ねられる人」かもしれません。というのも、この仕事では医師や患者さん、自治体職員など、さまざまな立場の人と関わる場面が日常的にあるからです。
たとえば電話対応ひとつとっても、「ただ伝える」だけでは終わらない場面に多く出会います。話す相手がご年配の方なら、聞き取りやすい声のトーンに気を配ったり、言葉をかみ砕いて説明したり。相手の表情が見えない分、想像力が試される仕事でもあります。
さらに、医療関係者の方は忙しさのあまり、つい言葉が強くなることもあります。そうしたときに感情で返すのではなく、一度気持ちを受け止めてから、冷静に対応できること。それが信頼につながり、円滑な関係を築いていく礎になるのです。
つまり、医師会の事務職では「話す技術」よりも「聴く力」が重要になります。相手の言いたいことを汲み取りながら、柔らかく対応できる人は、きっとこの仕事で大きな力を発揮できるはずです。
【特徴2】正確な作業が得意で責任感がある人
医師会の事務職は、いわゆる「事務作業だけ」では収まりません。たとえば、医師向けの通知文や研修会の案内を作る際、一文字のミスが混乱を招くこともあります。誰かのスケジュールや行政の手続きに関わるような業務も少なくないため、「なんとなく」で済ませられるような場面はほとんどありません。
実際に、大阪府医師会の採用情報では、資料作成や会議の運営、行政対応など、細かい作業が求められる業務が並んでいます。しかも、そうした業務の多くは「ミスが許されない」前提で進みます。資料を印刷してから誤字に気づいたり、提出後に記載ミスが発覚すれば、関係者全体に影響が出かねません。
もちろん、完璧な人間はいませんが、「少しでも正確に」「任されたことはしっかりやり遂げたい」と思える人は、この仕事にぴったりです。失敗を恐れるより、責任を持ってやり切ることに喜びを感じられる──そんな人が、医師会の事務では信頼され、頼りにされていきます。
【特徴3】協調性を持ちチームで働ける人
医師会の事務に携わるうえで、スキルや経験ももちろん大事ですが、それ以上に「人と歩調を合わせて動けるかどうか」が鍵になります。というのも、医師会の仕事は、一見すると裏方のように思われがちですが、実際は医師、行政、地域住民との間に立つ“調整役”のような立ち位置で動くことが多いからです。
たとえば、地域の医療イベントや会議の準備では、複数の関係者と連携を取りながら、細かな変更や要望にも柔軟に対応する必要があります。ある現場では、直前に医師のスケジュールが変わり、案内状や配席をすべて差し替えることになったという話もあります。そのとき求められたのは、事務作業の速さだけでなく、「誰とでも穏やかに話を進められる力」だったそうです。
実際、求人票でも「チームワークを大切にできる方」「周囲と協調しながら対応できる方」といった表現が多く見られます。これは裏を返せば、「自己主張が強すぎる方」や「周囲を見ずに突っ走るタイプ」には向かない仕事でもあるということです。
医師会の事務は、決して華やかな仕事ではありません。しかし、誰かと協力し合いながら一つの仕事を形にしていく過程に、やりがいを感じるタイプの方には、間違いなくフィットする職場です。
医師会の事務に就職して「きつい」と感じないための事前対策
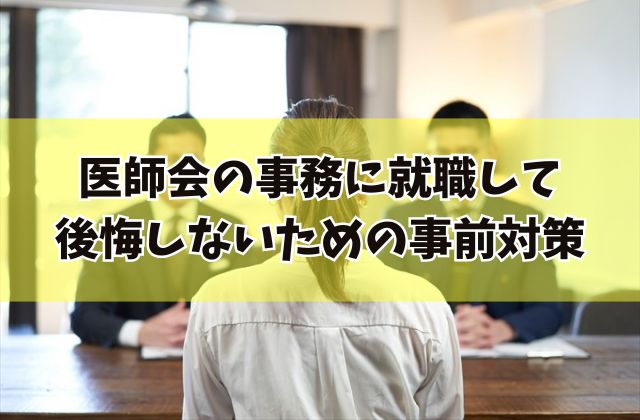
医師会の事務に挑戦したいと考えている方にとって、「きつい」という評判は気になるところです。
ただし、多くの場合は事前の準備不足や仕事内容への理解不足が原因で、そう感じてしまうケースが目立ちます。
実際には、しっかりと対策を講じておくことで、職場への不安やギャップは大きく減らすことが可能です。
ここでは、医師会の事務に就職して「きつい」と感じないための事前対策について、具体的に解説します。
【対策1】応募前に仕事内容や役割をしっかり理解しておく
「医師会の事務はきついって聞くけど、実際どうなんだろう?」
そんな不安を抱えているなら、まずやるべきことはシンプルです。応募前に、仕事内容を自分の目でよく見て、どういう役割を任されるのかをきちんと把握しておくこと。このひと手間を惜しむと、入職後に「こんなはずじゃ…」とつまずいてしまいがちです。
たとえば、地域の医師会では、電話応対や書類作成だけではなく、行政機関や医師とのやり取り、イベントの運営など、想像以上に人と関わる業務が多くあります。単なる「事務」の枠に収まらないからこそ、仕事内容に対する理解不足が「きつさ」の原因になりやすいのです。
求人情報だけで判断せず、医師会の公式サイトや、実際に働いた人の体験談などもチェックしてみてください。「こういう業務があるのか」「この雰囲気ならやっていけそう」──そんな感覚を持ってから応募するだけで、心の準備がまるで違ってきます。準備が整っていれば、自信を持って面接に臨めるはずですし、入職後のミスマッチも防げます。
【対策2】自身の志望動機と強みを明確にして応募準備をする
医師会の事務職を本気で目指すなら、「どうしてその職場を選んだのか」「自分には何ができるのか」を、自分の言葉で語れるようにしておくことが大切です。単に“安定しているから”“事務職をやりたいから”といった理由では、採用担当の心には響きません。
では、どんな準備が効果的なのでしょうか。たとえば、家族が地域医療でお世話になった経験がある、医師や患者を支える仕事にやりがいを感じる——そんなきっかけがあったなら、それは立派な志望動機になります。それを自分の体験として、無理に飾らずに伝えること。そこに信頼感が生まれます。
加えて、自分の「強み」も忘れずに棚卸ししておきましょう。たとえば、「人の話をじっくり聞ける」「決められたルールの中でコツコツ作業するのが得意」「相手の立場を考えて動ける」。こうした特性は、医師会の事務において大きな強みになります。
志望理由と強みがブレずに伝えられれば、面接では自然と自分の言葉で話せるはずです。背伸びをせず、自分がどう貢献できるかに正直になって準備を進めることが、合格への一歩になります。
とはいえ、自分一人で強みを見つけられるほど簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【対策3】面接で聞かれる質問を想定して回答を準備する
医師会の事務職に応募するにあたって、面接でどんな質問が飛んでくるのか——そこが気になって手が止まる人も多いのではないでしょうか。結論から言えば、「なぜ医師会なのか?」「何を強みにして働きたいのか?」といった本質的な質問が中心です。
医師会の業務は、地域医療に密着している分、事務職であってもその“想い”や“目的意識”が問われます。「どんな業務に関心があるか」「どんな姿勢で向き合うか」は、あらかじめ整理しておくことで、面接時の受け答えに自信が持てます。
実際、採用担当者が重視しているのは、完璧な回答よりも、自分の言葉で誠実に話せるかどうかです。たとえば「細かい作業が得意なので、文書管理や受付対応などの正確さを活かしたい」といった具体性があれば、伝わり方は格段に変わります。
「自己紹介」や「志望動機」「長所・短所」「業務への姿勢」といった定番の質問だけでなく、「忙しい時期の対応にどう向き合うか」など、実務に即したやり取りも想定しておくと安心です。医師会は一般企業と違い、医師や関係者との連携が多く、社会性や柔軟な対応力も求められます。
事前準備といっても、難しく考える必要はありません。大切なのは、自分の想いを正直に、そして具体的に伝えること。それができれば、面接という場の「きつさ」は、むしろチャンスに変わるはずです。
【対策4】コミュニケーションと事務処理スキルを意識的に磨く
医師会の事務は、一見すると「資料作成や電話応対が中心でしょ?」と軽く思われがちですが、実際に働いてみると“人との関わりの深さ”に驚かされます。相手は医師や医療関係者。つまり、プロ同士のやり取りの中で、こちらも一定の理解力と礼節を求められるのです。
たとえば、電話一本。単に「●●先生はいらっしゃいますか?」と伝えるだけでも、言葉の選び方や声のトーン一つで印象が大きく変わります。コミュニケーション力とは、スムーズに話せるかよりも、「どう伝わるか」を考え続ける姿勢に近いのかもしれません。
一方、事務処理に関しては“早く正確に”という言葉に尽きます。診療報酬の申請や会議資料の作成など、どれもミスが許されない緊張感が伴います。ただしこれは、裏を返せば“信頼”を積み重ねるチャンスでもあるのです。
この2つのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。ただ、日々の業務を“こなす”のではなく、“育てる”感覚で意識していけば、気づけば自然と身についているもの。完璧じゃなくていい。でも、丁寧に、誠実にやる。それが結局、一番の近道です。
※
【対策5】転職エージェントなど第三者の相談も活用する
「医師会の事務って、実際どうなの? 本当にやっていける?」——こんな不安を抱えているなら、一度プロの転職エージェントに相談してみてください。自分ひとりで求人情報とにらめっこするより、よっぽど視界が開けてきます。
実際、医療事務に強いエージェントを活用すれば、非公開求人にアクセスできたり、応募書類の添削や面接対策まで細かくフォローしてもらえます。中でも「ジョブメドレー」は、現場事情に詳しい担当者が付き、働く職場の“裏側”まで教えてくれると評判です。初めてこの業界に飛び込む方にとって、これはかなり心強い味方になります。
さらに、大手の「リクルートエージェント」なら、求人数が圧倒的。条件交渉や入職タイミングの相談もできるので、希望の働き方を叶えやすくなります。エージェントとの会話を通じて、ぼんやりしていたキャリアの輪郭がハッキリしてくる感覚を味わえるはずです。
医師会の事務は、たしかに簡単な仕事ではありません。でも、外から見ただけじゃわからない情報や、自分に合うかどうかの“温度感”は、現場を知る第三者から聞くのが一番です。独りで抱え込まず、信頼できるエージェントを味方につける——それだけで、転職活動はぐっと楽になりますよ。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
医師会の事務に応募する志望動機を考える際のポイントと例文
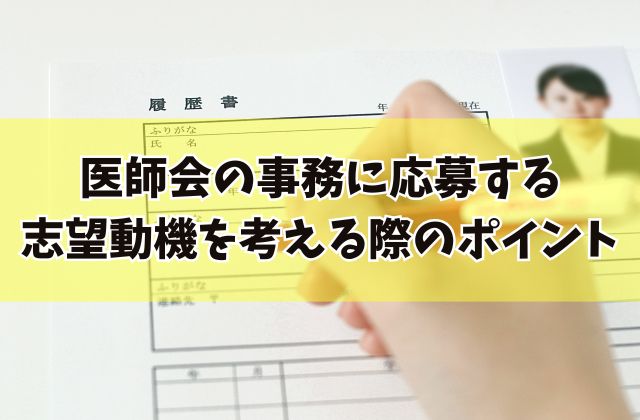
医師会の事務職に関心を持ち、応募を検討している方にとって、書類選考や面接で最も重視されるのが志望動機です。
なぜ医師会で働きたいのか、どのように自分の経験を活かせるのかを明確に伝えることが、選考突破の鍵になります。
ここでは「医師会の事務に応募する志望動機を考える際のポイントと例文」を紹介します。
採用担当者の心に届く文章を仕上げるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
【ポイント1】なぜ医師会で働きたいのか動機を具体的に書く
「医師会で働きたい」と一言で言っても、その動機が漠然としていては伝わりません。採用担当者が本当に知りたいのは、“なぜ数ある事務職の中で医師会を選んだのか”という部分です。ここが曖昧だと、どれだけスキルがあっても心に響かないものです。
たとえば、「地域医療に関心があり、裏方として支える役割に魅力を感じた」「前職で培った調整力を、医師と行政の橋渡し業務に活かしたい」といったように、自分の経験や価値観と仕事の内容をしっかり結びつけて言葉にすることが大切です。
具体的に志望動機の例文を示すと、
地域医療を支える医師会の活動に以前から関心があり、医師の皆様を事務面から支えるという役割に魅力を感じ、志望いたしました。前職では来客対応やスケジュール調整など幅広い庶務を担当し、正確かつ丁寧な対応を心がけてきました。こうした経験を活かし、医師の方々が安心して地域医療に専念できるよう、陰から支える存在として貢献していきたいと考えています。
医師会の仕事はただの事務ではありません。患者ではなく、医師や医療関係者をサポートする立場に立ち、会議の運営や地域連携など幅広い業務を担います。だからこそ、「誰のために」「なぜこの環境で働きたいのか」を自分の言葉で掘り下げて書くことで、想いの深さが伝わります。
派手さや技巧に走る必要はありません。けれど、「自分だからこそ、この場所で力を発揮できる」という芯のある理由を丁寧に言葉にすること。それが、強く、そして温かく響く志望動機になります。
【ポイント2】自分の経験がどのように貢献できるか明確にする
自分のこれまでの経験が、次の職場でどう活かせるのか——それを言葉にするのは、案外むずかしいものです。でも、実際に医師会の事務として働くことを考えたとき、過去の出来事が「今こそ活きる」と思えた瞬間があるなら、それが志望動機の核心になるはずです。
たとえば、以前の職場でクレーム対応に追われていた経験があるなら、それを“嫌な過去”と捉えるのではなく、「冷静に話を聞いて相手の感情を受け止める力が身についた」とポジティブに掘り起こしてみてください。医師会の事務では、医師や地域の方とのやりとりが日常です。何気ない調整ひとつにしても、対話力や気配りが求められます。
具体的に志望動機の例文を示すと、
私は前職で地域密着型の医療事務に携わり、来院者や関係機関との調整業務を通じて、丁寧な対応と正確な事務処理を大切にしてきました。特に多忙な中でも冷静に優先順位を見極め、円滑な運営を支えることにやりがいを感じていました。医師会の事務では、医療従事者との連携や地域全体を支える業務が多く、自分の経験や対応力をさらに広いフィールドで活かせると感じ志望いたしました。事務方としての立場を超えて、地域医療に貢献できる存在になりたいと考えております。
実際、求人情報サイトでも、事務職では“細やかな配慮”や“関係構築力”が評価されると記載されています。つまり、目立つ成果よりも“どう働いてきたか”が問われる職種なのです。
完璧な経歴は必要ありません。むしろ、少し泥臭くても「こんなとき、自分はどう動いたか」を語れる人こそ、現場では信頼される存在になります。過去の経験に胸を張ってください。その中に、あなたにしか語れない強みが、きっとあります。
【ポイント3】自身の目標や将来のキャリアビジョンを示す
「この職場で何を目指して働いていくのか?」——採用側が知りたいのは、スキルや経験だけではありません。未来に向けて、どんな姿を描いているのか。そのビジョンが、あなたの本気度を映し出します。
たとえば、医師会の事務職であれば、「地域医療を支える一員として、円滑な会議運営や調整業務を通じて信頼される存在になりたい」というような、仕事と地域社会のつながりを意識した言葉が響きます。
具体的に志望動機の例文を示すと、
医療現場を陰から支える存在として、地域社会に貢献できる仕事を探しており、医師会の事務職に強く惹かれました。これまで培ってきた事務処理や調整業務の経験を活かし、会員医師の方々が安心して業務に集中できるよう、円滑な事務対応を行いたいと考えています。将来的には、地域の医療を支える要として信頼される存在になることを目標に、制度や医療関連知識の習得にも意欲的に取り組んでいきたいと思います。
人材系サイトの採用担当者インタビューでも、「キャリアビジョンがある人は、入社後に迷わず自走できる」と評価されていました。これは、言い換えれば、組織にとって安心して任せられる人材だということです。
大切なのは、立派な夢を語ることではありません。「何を大事にして、どう働いていきたいか」を、あなた自身の言葉で、できるだけ具体的に伝えること。それだけで、志望動機に深みが生まれます。
完全未経験でも事務職デビューが叶うおすすめ求人サイト3選
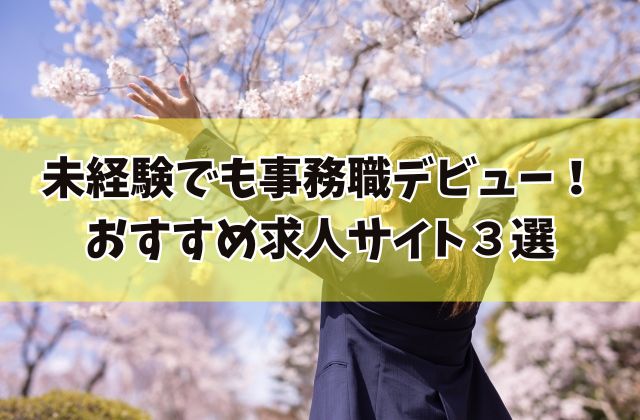
事務の経験がなくても事務職を目指せるチャンスは十分にあります。
大切なのは、未経験者歓迎の求人に的確にアクセスすることです。
そこで「完全未経験でも事務職デビューが叶うおすすめ求人サイト3選」を厳選しました。
サポート体制が整っている信頼性の高いサービスを紹介します。これから応募を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
【おすすめ1】マイナビキャリレーション
事務職が未経験でも、本気でキャリアを築きたい——そんな想いを支えてくれるのが『マイナビキャリレーション』です。大手マイナビが運営するこのサービスは、正社員型の派遣という形で雇用が安定しているだけでなく、事務に必要なスキルを“最初の一歩”から身につけられる仕組みが整っています。
特に魅力的なのが、「MOVICATION(ムビケーション)」という独自の研修制度。たとえば、電話応対やビジネスマナーといった基本から、Word・Excelの実践操作まで、配属前に学べるのです。座学ではなく、手を動かしながら身につけられるスタイルなので、実務に入っても戸惑うことが少なくなります。
さらに、就業後もキャリアアドバイザーがしっかり伴走。どんな職場が向いているのか、どんな強みがあるのかを丁寧に一緒に探してくれます。「事務は初めてだから不安…」という方も、一歩ずつ着実に成長できる環境です。未経験から事務職に就職するなら、最初の土台作りとして心強い選択肢になるはずです。
【おすすめ2】ランスタッド
未経験から事務職を目指すなら、最初にぶつかるのは「経験がない」という壁。そこを無理なく乗り越えられる手助けをしてくれるのが、『ランスタッド』です。
実際、ランスタッドの求人には「未経験OK」や「パソコンスキル不問」といった条件のものが多く、事務職が初めてという人でもチャレンジしやすい案件がそろっています。たとえば、医療事務や受付事務など、初歩からスタートできる職場が豊富に掲載されています。
さらに注目したいのは、登録後のサポート体制の手厚さです。担当者が相談に乗ってくれるのはもちろん、就業後も状況を気にかけてくれるフォローがあるため、長く働き続けやすいという声もあります。特に子育て世代にとっては、福利厚生や時短勤務の相談など、安心材料が揃っているのも大きな魅力です。
「経験はないけれど、医療の現場を支える仕事に就きたい」と思っている方にとって、ランスタッドは背中を押してくれる存在になるはずです。
【おすすめ3】テンプスタッフ
「未経験だけど、医師会のような落ち着いた環境で事務職にチャレンジしてみたい」──そんな人にこそ、『テンプスタッフ』は一度チェックしてみてほしい存在です。
派遣会社というと、やや機械的な対応を想像するかもしれません。でも、テンプスタッフはちょっと違います。実際に利用した人の声を見ると、職種別の丁寧なサポートや、初めてでも安心して相談できる雰囲気が好評のようです。事務職のなかでも、医療や公的機関系の求人が豊富にそろっていて、「残業なし」「駅チカ」「未経験歓迎」といった条件付き案件も多く見つかります。
たとえば、東京エリアでは、医療事務アシスタントや総務系ポジションで未経験OKの募集が目立ち、時給も1,600円~1,800円と比較的高め。登録後は、専属のキャリアコーディネーターが職場の雰囲気や仕事内容まで詳しく教えてくれるため、「現場に出てから話が違った…」なんてズレも防げます。
気軽に始められて、手厚い支援もある──テンプスタッフは、「医師会の事務に興味はあるけれど、いきなり正職員は不安」という人にとって、現実的かつ安心できる入口となってくれるはずです。
【Q&A】きついと囁かれる医師会の事務に関するよくある質問
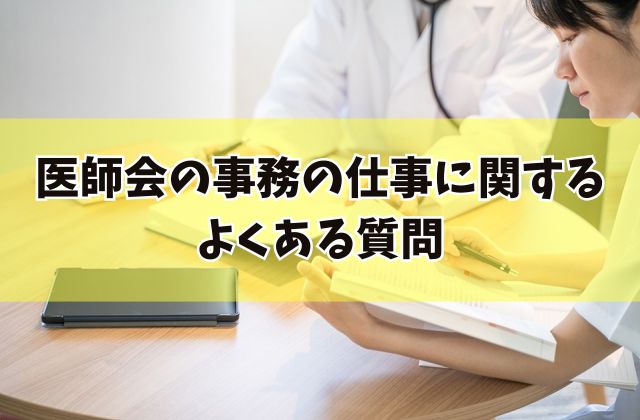
最後にきついと囁かれる医師会の事務に関するよくある質問をまとめました。
年収の目安や口コミ、面接で聞かれる内容など、気になる疑問をわかりやすく解説します。
【質問1】医師会の事務の年収はどのくらい?
医師会で働く事務職の年収については、地域や組織規模によって差はあるものの、いくつかの求人や口コミからおおよその相場が見えてきます。
たとえば、日本医師会の正職員募集では、初年度から500万円台の提示が見られましたし、東京都医師会の口コミでは年収430万~500万円程度との声もありました。民間企業の事務職と比べて決して高給ではないものの、賞与や昇給制度が安定しており、給与の「見通しの良さ」が魅力と言えそうです。
【質問2】医師会の事務の口コミは実際どうなの?
実際に医師会で働いた人たちの声をいくつか拾ってみると、評価は良い面と厳しい面がはっきり分かれている印象を受けました。
「産休・育休がしっかり取れて、育児と両立しやすい」「定時で帰れる日も多い」など制度面を評価する声がある一方で、「イベント前は残業が続く」「仕事量が多く、慣れるまでが大変」といった現場ならではの声も見られます。働く環境は整っていても、業務の濃さはそれなりにある——そう受け止めておいたほうがギャップが少ないかもしれません。
【質問3】医師会事務の面接でよく聞かれることは?
医師会の面接では、「なぜこの仕事を選んだのか」という根本的な問いが特に重視されているようです。
過去の応募者の体験談によると、「学生時代に頑張ったこと」や「医師会を志望した理由」、「自分が入職後にどんなことをしてみたいか」など、人柄や価値観を探る質問が多かったとのこと。福岡市医師会では「意見を最後まで貫くタイプかどうか」など、思考のスタンスを問う質問もあったようです。正解のある質問ではなく、“どう考えているか”に注目される面接といえます。
まとめ:医師会の事務はきついと言われる理由と働く魅力
医師会の事務はきついと言われる理由と働く魅力をまとめてきました。
改めて、医師会の事務は本当にきついのか?5つの結論をまとめると、
- 雑務や電話応対が多く、業務が煩雑になりやすい
- イベント準備などにより時間外労働が発生することもある
- 少人数体制のため、一人の業務負担が重くなる傾向がある
- 会員医師や地域関係者との調整業務に神経を使う
- 一方で安定性ややりがい、スキル習得といった魅力も多い
医師会の事務は「きつい」と感じる場面もあるものの、安定性や地域医療への貢献といったやりがいも大きい仕事です。
仕事内容を事前に理解し、自分に合った働き方を選べば、長く活躍できるフィールドといえるでしょう。