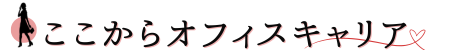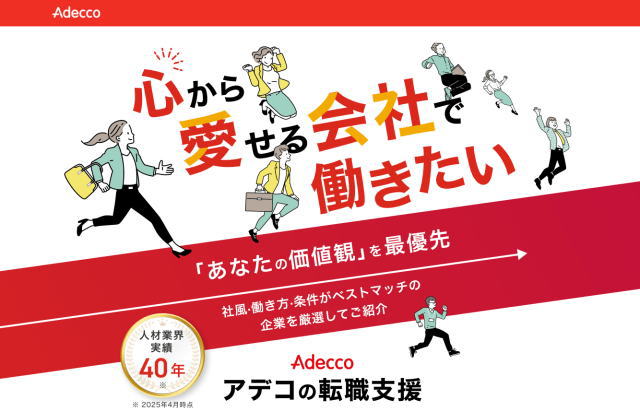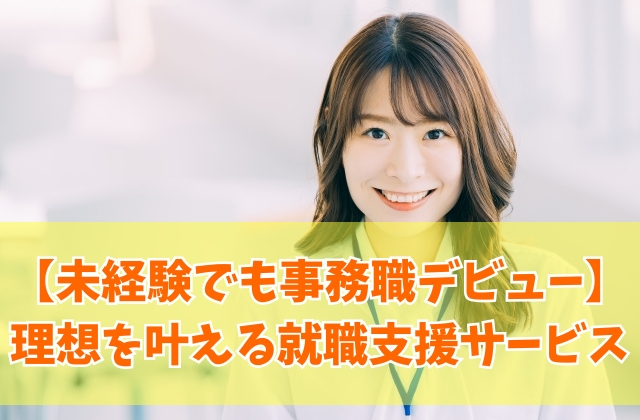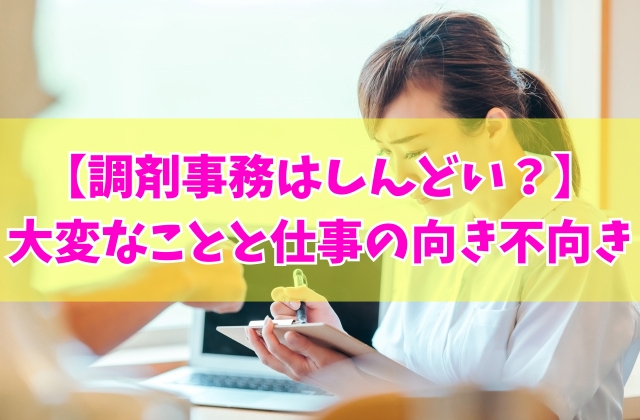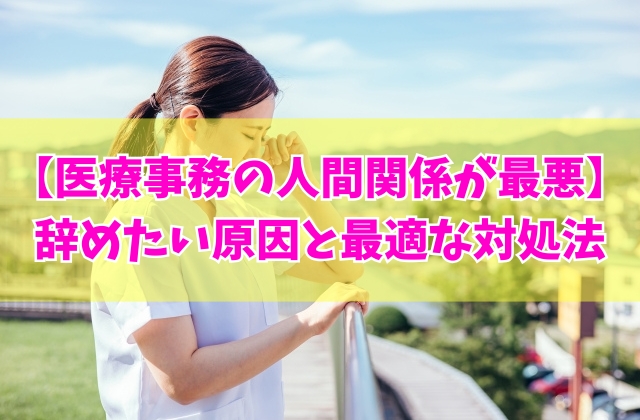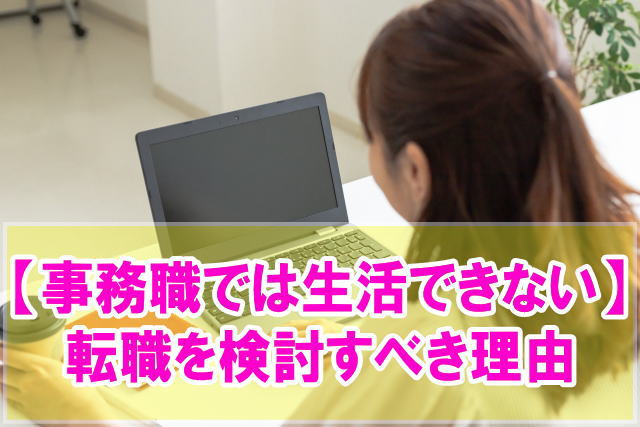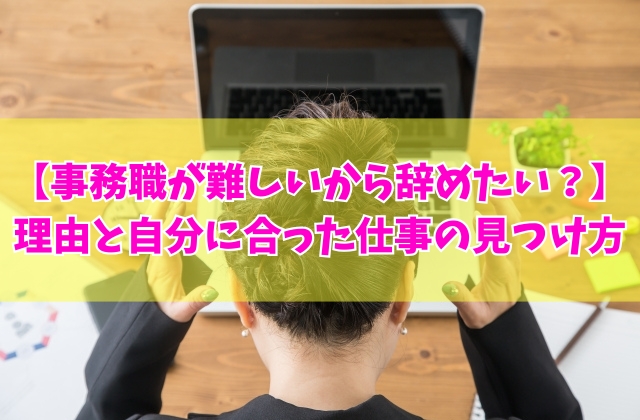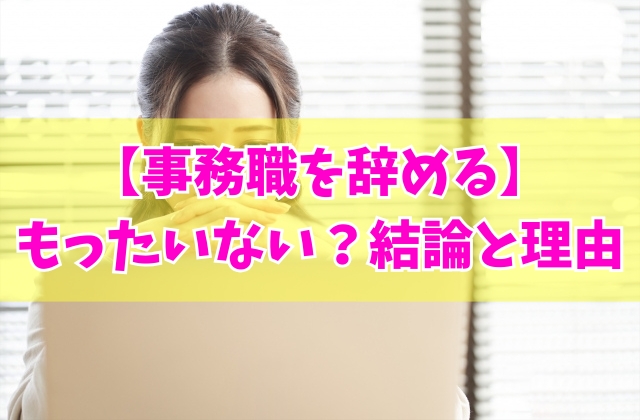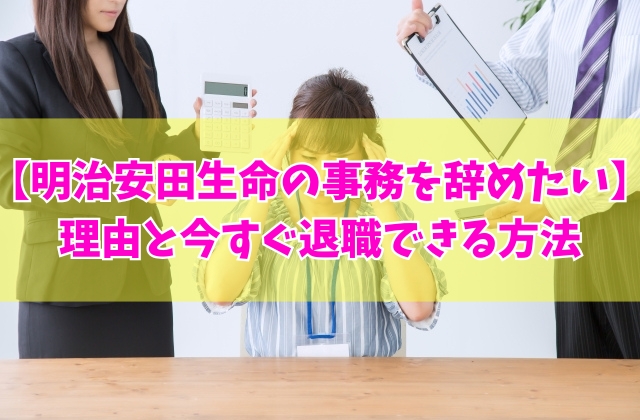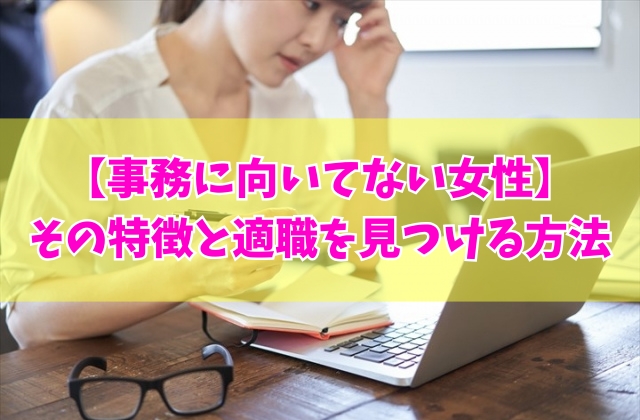
「事務に向いてない女性の特徴は?」
「このまま続けるか、転職するか悩む。。私の適職はどうやって見つけたらいい?」
「どうして自分だけがうまくできないの?」——事務職として働きながら、毎日そう感じていませんか。
PC操作や細かい作業、人間関係のストレスに疲れて、「やっぱり自分は事務に向いてない」と思ってしまう女性は少なくありません。
でも、その悩みにはちゃんと理由があります。そして、仕事で向き不向きがあるのは当然のこと。
あなたにも向いている「適職」は必ずあります。ただ、まだ出会っていないだけなんです。
この記事では、事務に向いてない女性が感じやすい特徴や悩みを整理しながら、自分らしい働き方を見つける方法を丁寧に解説していきます。
- 事務が苦手な女性には特定の傾向やストレスの原因がある
- 向いていなくても事務職にはメリットや学べるスキルがある
- 転職や適職探しには自己分析や専門家のサポートが有効
女性が「事務に向いてない」と感じることは恥ずかしいことではありません。合わない理由を明確にし、次に進むための手段を見つけることが大切です。自分らしく働ける環境は必ずあります。
そして、「今の仕事、本当にこのままでいいのかな?」——そんな疑問が頭をよぎったとき、自分ひとりで抱え込まず、転職エージェントに相談してみるという選択肢があります。
大手や女性向け専門のサービスでは、ただ求人を紹介するだけでなく、キャリアの棚卸しから書類の添削、面接対策まで、思っている以上に手厚いサポートをしてくれます。
たとえば「アデコ」は、事務職に特化した求人を豊富にそろえており、女性のライフスタイルや希望条件に合わせたマッチングが強みです。担当コンサルタントの丁寧なヒアリングが口コミでも高く評価されています。
ほかにも「リクルートエージェント」では、非公開求人が多く、幅広い業界の情報を収集できるため、自分では思いつかなかった選択肢に出会える可能性もあります。実績データによると、転職成功者の約62%が年収アップを実現しているとのことです。
職場で感じる違和感や、働き方に対する不安。その正体をはっきりさせたいとき、プロの視点はやはり頼りになります。自分では気づけなかった強みを掘り起こしてくれたり、意外なキャリアの道を示してくれたりすることも。今のもやもやを「行動」に変えるための、一つの確かな手段です。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
とはいえ、今後のキャリア形成はすべての社会人が悩む重大イベント。誰かに相談したいのが本音ですよね。
そんな、今まさにキャリアについて悩んでいる人は、累計相談者数が35,000人を超える実績豊富な『ポジウィルキャリア』の活用がおすすめです。
『ポジウィルキャリア』は、あなた専属のトレーナーがマンツーマンで伴走し、自己理解・人生設計・意思決定まで一緒に考えてくれる“キャリアのパーソナルトレーニング”です。
心理学に基づいたプログラムと実績あるサポート体制で、あなたの「本音」を引き出し、理想のキャリアを現実に変えていきます。
初回は、45分の無料カウンセリングから。未来のあなたのために、まずは一歩踏み出してみませんか?
事務に向いてない女性の特徴8選

事務職は一見すると誰にでもできそうな仕事に見えますが、実際には向き不向きがはっきり分かれる職種でもあります。
特に、毎日の業務に違和感やストレスを感じている場合、自分が「事務に向いてない」と悩んでしまうこともあるでしょう。
ここでは、事務に向いてない女性の特徴8選を紹介します。自分に当てはまる点がないかを知ることで、今後の働き方を見つめ直すヒントになるはずです。
【特徴1】PCやOffice操作に苦手意識がある女性
パソコンやExcel、Wordの操作に自信が持てず、事務の仕事がつらく感じている女性は少なくありません。とくに新しいソフトや社内システムが導入されたとき、周りがサクサク作業をこなしているのに、自分だけ取り残されたように感じて落ち込む…そんな経験はないでしょうか。
実際、内閣府の資料をみても、女性社員の方が職場でのITスキル習得の機会を逃しがちだという結果も出ています(出典:女性デジタル人材の育成について)。特に「PCが苦手」という意識があると、ちょっとしたエラーや操作ミスでも過剰に焦ってしまい、ますます苦手意識を強めてしまう傾向があります。
たとえば、関数の使い方があいまいなままExcel業務を任されると、それだけで何倍も時間がかかってしまいますし、上司に確認するのも気が引けて、ひとりで抱え込んでしまうという声もよく聞きます。
ただ、心配はいりません。今はパソコン初心者向けの講座や、女性向けのIT研修なども充実しています。誰にでも分かる言葉で教えてくれる内容が多いので、少しずつ学び直せば、苦手意識は自然と薄れていきます。「私は向いてない」と思い込む前に、一度ゆっくり基礎を振り返ってみるだけでも、気持ちが大きく変わることがありますよ。
【特徴2】数字や計算を扱うのが苦手な女性
事務職に就いたものの、数字を扱う場面で毎回プレッシャーを感じてしまう…。そんな女性は少なくありません。とくに売上や経費、在庫管理のような数字が絡む作業は、「間違えたらどうしよう」と不安が先に立ち、集中力が続かなくなるという声をよく耳にします。
実際に、ファイナンシャル・タイムズの調査では、3分の1以上の女性が「数字やデータを扱う業務には応募しない」と答えています。これはスキルの問題ではなく、「自信のなさ」が大きな要因になっているという指摘もあります。
例えば、Excelで関数を使って集計するような場面で、ほんのわずかなミスを繰り返してしまい、「自分は向いていないんじゃないか」と感じた経験はないでしょうか。しかも周囲がスムーズにこなしているように見えると、よけいに自己嫌悪に陥りやすくなります。
ただ、数字が苦手だからといって、事務全体を諦める必要はありません。計算に対する苦手意識は、簡単なステップから練習するだけでもかなり薄れていきます。たとえば、日常の買い物で暗算を意識してみたり、スマホの学習アプリで「たし算」や「わり算」をゲーム感覚で繰り返すだけでも、驚くほど気持ちに変化が出てきます。
「できない」と思い込む前に、ちょっとずつ慣れてみる。それだけで、事務の仕事がずっと穏やかに感じられるようになるかもしれません。
【特徴3】大雑把で細かい確認作業が苦手な女性
事務の仕事は「ミスなく丁寧に」が基本。でも、もともと大雑把な性格の人にとっては、その“丁寧さ”を毎日求められること自体が大きなストレスになりますよね。小さな数字のズレや日付の記載ミスなど、「確認すれば防げた」と言われるような失敗に、心がすり減っていく…そんな経験をしてきた方も多いのではないでしょうか。
実は、国際的な調査(OECDなど)でも、女性は細かな処理や数的スキルを必要とする業務に触れる機会が少ない傾向があるとされています。つまり、“苦手”と感じるのは能力の問題ではなく、慣れる場面が少なかっただけという可能性が高いのです。
たとえば、請求書の金額や日付を確認する仕事で、何度も見直しているのに誤字を見逃してしまうと、「自分は事務に向いてない」と落ち込みたくなる気持ちもよく分かります。上司にやんわり注意された日なんて、帰り道ずっと頭の中で反省会…ということもあるかもしれません。
そんな方におすすめしたいのが、「完璧を目指す」よりも「仕組みでミスを防ぐ」発想です。手書きのチェックリストや付箋を使って、自分だけの確認フローを作るだけでも驚くほど心がラクになります。作業スピードより“確実さ”を意識して、ひとつずつこなしていけば、少しずつ自信も取り戻せます。
細かい作業が苦手でも、工夫次第で乗り越えられるものです。自分を責めすぎず、向き合い方を変えることが、働きやすさの第一歩になるはずです。
【特徴4】単調なルーティン作業に飽きやすい女性
同じ作業を、毎日同じように淡々と繰り返す——それが苦手だと感じるなら、事務の仕事はしんどくなって当然かもしれません。集中が続かず、ふとした瞬間に「何のためにこれをしてるんだろう」と考え込んでしまう…。そんな気持ち、きっと少なくないはずです。
実際、海外の調査では79%~87%の働く人が「日常業務に退屈さを感じる」と答えています。しかもその“飽き”は、ただの気分の問題ではなく、うつや不安、仕事へのモチベーション低下に直結するという指摘もあります。
たとえば、午前中に50件分のデータを同じフォーマットに打ち込み終えたとき、心がまるで空っぽになったような感覚に襲われることはありませんか?「今日も、昨日とまったく同じだったな…」と感じる日が増えると、やがて仕事そのものが重たく感じられるようになります。
けれど、単調な作業との向き合い方を少し変えるだけで、気持ちはラクになります。たとえば、「10件ごとに休憩を入れる」「お茶を飲む時間を“ごほうびタイム”にする」など、小さな区切りを作って作業にリズムを持たせるだけでも違います。深呼吸やストレッチを間に挟むのもおすすめです。
淡々とした業務の中に、ほんの少し自分だけの「変化」を入れてみる——それが、飽きとの付き合い方のコツなのかもしれません。
【特徴5】対人対応や電話応対にストレスを感じる女性
電話が鳴るたびに、少し胸がざわつく——そんな感覚を抱えたまま、日々の事務仕事をこなしていませんか?特に、代表電話やお客様対応を任される事務職にとって、「話すこと」そのものが小さなプレッシャーになることは珍しくありません。
ある調査によれば、実に約75%のビジネスパーソンが電話対応にストレスを感じていると回答しています。その中でも「業務を中断されるのが嫌だ」と感じる人が全体の42%以上。つまり、“電話が苦手”という気持ちは、あなただけではなく多くの人が抱えているものなのです。
たとえば、Excelでようやく集中し始めたタイミングで電話が鳴り、手が止まる。内容をメモしながらも、相手の言い回しやニュアンスを読み取ろうと必死になっているうちに、次の業務の段取りが頭から抜け落ちてしまう…。そんな経験、心当たりはありませんか?
もし電話や対人対応に強いストレスを感じているのなら、まずは“自分のペース”を作ることが何より大切です。たとえば、午前中は電話応対に集中し、午後はメールや資料作成にじっくり取り組むといった時間配分を決める。あるいは、内線の取次ぎフローを手書きでまとめて、思考を簡略化する。
「苦手なことほど、整えてしまう」。これは、事務に限らず長く働き続けるための知恵でもあります。電話が怖い、対応に緊張する——その気持ちは、ほんの少しの仕組みで和らげることができるのです。
【特徴6】優先順位を決められず混乱しやすい女性
やるべき仕事はある。けれど、どれから手をつけていいのかわからない…。目の前にあるタスクが全部「急ぎ」に見えて、何も進まず、ただ焦ってしまう——そんな日が続くと、「自分には向いてないのかも」と感じてしまうのも無理はありません。
実際、厚生労働省のストレス対処に関する資料でも、優先順位を決めずに業務を抱え込むことは、心身への負担を強める原因になると指摘されています。さらに、業務過多の時期には「タスクの棚卸し」や「再配分」が有効であるとも言われており、無理に全部を自分で抱える必要はないという考え方が広がっています(出典:参考資料)。
たとえば朝の時点で「今日だけはこの3つだけ終わらせる」と決めておく。終わったら線で消す。それだけでも、ずいぶん気持ちが楽になります。余裕があれば、午後に残ったタスクを整理して、翌日のスケジュールに回してしまえばいい。優先順位が見えると、やるべきことの「重さ」が整理されて、自然と頭もすっきりします。
優先順位がうまくつけられないのは、性格のせいでも能力の問題でもありません。情報の整理が追いついていないだけなんです。ちょっとした仕組みを持つだけで、日々の仕事に感じる混乱は、ぐっと静かになります。
【特徴7】臨機応変な対応が苦手だと感じる女性
いきなりの電話、急ぎの書類変更、上司の「これ今日中でお願い」——そんな“予定外”が重なると、頭の中が真っ白になる。事務の現場で働いていると、マニュアル通りでは済まない場面によく出くわします。
そして、そのたびに「私って向いてないのかも」と落ち込んでしまうこと、ありませんか?
ある調査によると、事務職に求められるスキルのひとつに「臨機応変な対応力」が挙げられています。また、エン・ジャパンが行った意識調査では、女性の7割以上が「その力を身につけたい」と考えているとのこと。つまり、誰もが“苦手だな”と感じながらも、少しずつ習得していくものだということです。
たとえば、営業事務で「急ぎで見積もり変更、すぐ送って」と言われた場面。テンプレもなし、手順も不明。そんなときに焦ってパンクしてしまうのは、珍しいことではありません。むしろ最初からスムーズに対応できる人の方が少ないはずです。
だからこそ、「いつもこう来たら、こう返す」といった“自分だけの対応パターン”を持っておくと心が落ち着きます。やり方はシンプルで、困った対応や質問があったらその都度メモしておく。そして、それをノートや付箋にまとめて見返すだけ。繰り返すうちに、自分だけの“即答マニュアル”ができ上がっていきます。
臨機応変が苦手だと悩むなら、万能な人を目指すのではなく、自分なりの「慌てない準備」を持っておくこと。それが、事務の仕事をラクに続けるための小さな武器になります。
【特徴8】評価されにくくモチベーションが続かない女性
「今日も頑張ったのに、誰にも気づかれなかった…」そんな寂しい思い、感じたことはありますか?事務の仕事は、地味な作業ほど必要とされながら、見た目には成果が見えにくいものです。だからこそ、「評価されない=自分は必要とされていない」と感じやすく、モチベーションが消えていくのは無理のないことです。
実際、海外の調査によると、働く人の約74%が「仕事が面白いと感じること」、約69%が「上司や同僚からの承認・評価」をモチベーションの源泉として重視していると報告されています。特に、NCBIに掲載された研究では、女性は「承認されること」が男性以上に動機づけに大きく影響すると指摘されています。
これらの結果から、女性は仕事にやりがいや意義を感じられない環境では、働き続けることは難しいという実情が浮き彫りになっています。
職場環境の具体例を示すと、伝票の整理や備品管理など誰かの役に立っているのは明らかなのに、誰からも「ありがとう」を言われないと、次第に「私の仕事って意味あるのかな」と考えてしまうかもしれません。
ここで大切なのは、「ありがとうを自分で増やす工夫」です。業務報告に「今日のサポートでこんな成果に繋がりました」を添える、ちょっとした目に見える形で自己アピールするだけで、「やっててよかった」と思える瞬間が増えます。上司やチームへ感謝の声を投げかけることも、小さな承認を呼び込むコツです。
“評価されにくくてモチベーションが続かない”と感じているなら、自ら承認を生み出す仕組みづくりを試してみてください。じわじわと心に灯りがともるような働き方が、きっと見えてくるはずです。
女性が事務は向いてないし難しいと感じてしまう理由
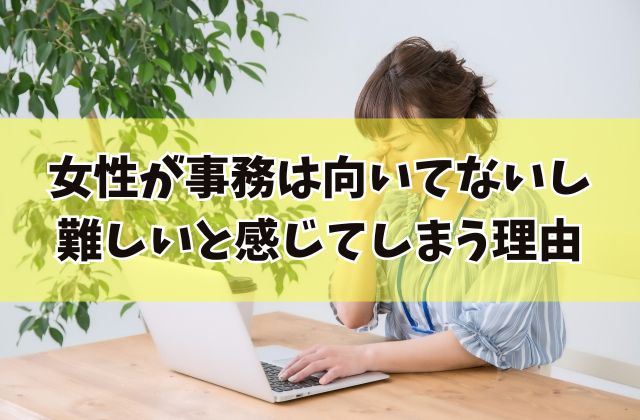
事務職は「誰にでもできる」と思われがちですが、実際に働いてみると想像以上に細かい気配りや柔軟な対応が求められます。
業務の多さや人間関係の気疲れにより、女性が事務は向いてないし難しいと感じてしまうのも自然なことです。
ここでは、なぜそのように感じやすいのか、女性が事務は向いてないし難しいと感じてしまう理由を丁寧にひもといていきます。
【理由1】マルチタスク要求がストレスになるから
あれもやらなきゃ、これも後回しにできない——事務の仕事は、ひとつの作業に集中しにくい環境が多く、それが大きなストレスになりやすいです。頭の中は常に散らかったまま、終業時間が近づくにつれて焦りばかりが募っていく…そんな状態が続いている方も多いのではないでしょうか。
実際、ある調査によると、働く女性のうち約74%が「マルチタスクに強いストレスを感じている」と回答しています(※)。加えて、ある研究では「人間の脳は同時に複数のことを効率よく処理できるようにはできていない」と明記されており、タスクを切り替えるたびに生産性は30~40%も落ちるという結果もあるほど。
たとえば、資料作成に取りかかった途端、内線が鳴って中断。電話の対応を終えたと思ったら、メールの返信が山積みになっている。気づけば、最初にやっていた作業がどこまで進んでいたのか分からなくなっている…。こんな一日を過ごした後、「自分には向いてないのかも」と感じるのは、決して珍しいことではありません。
そんな時は、“あえて一つずつ片付ける”意識に切り替えてみてください。たとえば「10時~10時半は請求書の入力だけ」「11時からはメール整理」と時間で区切るだけでも、心の中が整い始めます。効率よりも“思考の余白”を大切にするだけで、気づけば仕事への向き合い方も変わっていくはずです。
【理由2】急な依頼で時間管理が難しくなるから
午前中に立てた予定表が、午後にはすっかり形を変えてしまう。事務職に多い「急ぎでお願い」と言われる仕事が積み重なると、どんなに段取りを組んでも、思った通りには進みません。
特に経験が浅い時期には「全部に応えなきゃ」と無理をしてしまい、自分のタスクがどんどん後回しになる悪循環に。焦りや疲れが積もって、「私、向いてないかも…」と感じるのも無理はありません。
実際に、ある調査によると、働く女性の90%以上が「仕事にストレスを感じている」と答え、その中でも“突発的な依頼や指示”が大きな負担になるという声が目立ちます。さらに、心理学の研究でも、マルチタスクは集中力や生産性を大幅に下げるとされています。
そんな時は、自分の作業を“時間で区切る”方法が役立ちます。たとえば「10時~10時半は請求処理だけ」「11時からはメール整理」と、あらかじめ短くブロック分けすることで、予想外の依頼にも余裕を持って対応できるようになります。
思うように進まない日があっても、自分を責めすぎないでください。予定通りにいかないのが、むしろ普通のこと。完璧を目指すより、“崩れても立て直せる”力をつけることの方が、長く働く上ではずっと大事なのです。
【理由3】人間関係に気を遣い続けるのが負担だから
「今日もまた、あの人の機嫌を気にしながら仕事か…」
そんなふうに朝から気が重くなること、ありませんか?事務職は外回りが少ない分、社内での人間関係が濃くなりがちです。上司、同僚、時には他部署とのやりとりまで、“空気を読む力”が仕事の一部のように求められます。
実際、連合の調査によると、職場でストレスを感じる理由のトップが「人間関係」。その割合は74%以上にものぼります。エン・ジャパンが行った調査でも、女性の9割以上が「人間関係がストレス」と答えているほどです。
何気ない会話の裏を読んだり、無言の圧を察したり。自分なりに気をつけていても、「あの言い方、まずかったかも…」と帰宅後に一人反省会。そんな日が続けば、「自分には向いていないのでは」と感じてしまうのも無理はありません。
もし疲れを感じたなら、無理に“いい人”を演じる必要はありません。話しかけづらい空気を作ってもいいんです。自分を守ることも、立派な働き方の一つです。無理をしすぎない、それが続けるためのコツかもしれません。
【理由4】座りっぱなしで体調面に不安を感じるから
事務仕事では、気がつけば何時間も椅子に座ったまま。ふと立ち上がろうとしたとき、脚がむくんでいたり、腰に違和感を覚えたりした経験はありませんか?
これはあなただけの悩みではありません。実際、日本の成人は平日に1日平均7時間以上座っているというデータがあり、長時間座りっぱなしの生活が心身に及ぼす影響は、喫煙や過度な飲酒にも匹敵するほどだと警鐘を鳴らす専門家もいます。
特に女性の場合、冷え性や血流の悪化からくる不調に悩まされやすく、肩こりや頭痛、場合によってはうつ症状につながるケースもあります(出典:参考資料)。ある調査では、1日12時間以上座る女性は、そうでない人に比べてメンタル面の不調リスクが約3倍に上るという結果も報告されています。
だからこそ、30分に一度は席を立ち、軽く体を動かすことが大切です。トイレに行くついでに腕を回したり、給湯室まで少し遠回りして歩いたり。たったそれだけで、午後の集中力が戻り、気分もすっと軽くなることがあります。
仕事の合間に少しだけ自分の身体と向き合う時間をつくる。それが、事務仕事と上手に付き合う第一歩になります。
【理由5】将来AIに仕事を奪われる不安があるから
ふとした瞬間に、「この仕事、あと何年持つんだろう…」と考えてしまうことはありませんか?特に事務職のようにルーティンが多い仕事をしていると、AIに置き換えられるという話題が頭をよぎるのも無理はありません。
実際に、野村総合研究所とオックスフォード大学の調査では、日本人の仕事の約49%が、今後10~20年でAIやロボットに取って代わられる可能性があるとされています。なかでも、経理や医療事務などの定型業務は“特に危ない”と名指しで挙げられているほどです。
そんな話を聞くと、「私は何を目指せばいいの?」と不安になるのも当然です。でも安心してほしいのは、すべての事務職がAIに奪われるわけではないということ。逆に、今こそ“人にしかできないこと”を磨くチャンスでもあります。
たとえば、人とのコミュニケーション、感情のくみ取り、柔軟な対応力。こういったスキルはAIにはできません。地味に思えるような「ちょっとした気配り」や「曖昧な依頼に対する工夫」こそが、あなたの仕事の価値を高めてくれます。
つまり、「AIに負けない人」になる鍵は、“今やっている仕事の中にある人間らしさ”に、少しだけ意識を向けること。それだけで、将来への不安は驚くほど小さくなっていきます。
向いてないと思っても女性が事務として働くメリット

「自分には事務が向いてないのかも…」と感じたとしても、すぐに諦めてしまうのはもったいないかもしれません。
実は、向いていないと悩む女性でも、事務という仕事だからこそ得られる恩恵があります。
働き方や環境の柔軟さ、スキルの習得など、”向いてないと思っても女性が事務として働くメリット“には、見逃せない価値が詰まっています。
ここから、その具体的な事務職として働く魅力を丁寧に解説していきます。
【メリット1】土日祝休みで家事や子育てと両立しやすい
「本当に続けられる仕事ってなんだろう」——そう思いながら、子育てや家事と格闘している女性にとって、土日祝が休みという事務職の働き方は、想像以上に救いになります。
実際、ある調査では、「子育てしながら働きやすい職種」として事務職を選ぶ女性は全体の約25%。その理由の多くが「カレンダー通りの休日が取れるから」というものでした。運動会や保育園の行事と仕事がバッティングしない安心感は、働き続けるうえで何より大切です。
また、平日は保育園に預けながら働き、週末はしっかり子どもと向き合える——そんな生活リズムが整うことで、無理に“完璧な母親”を目指さず、自分のペースで働く余裕も生まれます。マイナビの調査結果(育児離職と育休の男女差実態調査(2025))をみても、育児経験のある女性の4割以上が「退職を検討した」一方で、“土日休みの確保”が最も重視されており、両立のカギとされています。
「事務は向いてないかも…」と悩む気持ちがあっても、生活全体とのバランスで見ると、この働き方が持つメリットは無視できません。向き不向きだけで判断せず、「今の暮らしに合う仕事かどうか」で考えてみるのも一つのヒントです。
【メリット2】基本的なPCやビジネスマナーが自然に身につく
「事務の仕事は地味だ」と思っていたのに、いつの間にかパソコン作業も、敬語の使い方もスムーズになっていた——そんな声は少なくありません。実際、毎日エクセルやメール対応に触れていれば、専門的な勉強をしなくても操作やマナーは自然と体に染み込んでいきます。
事務職の多くでは、社外とのやり取りや社内調整が業務の一部です。そのため、新人向けにビジネスマナー研修を実施している企業も多く、「電話応対が苦手」「言葉遣いが不安」という悩みも、現場での実践を重ねるうちにクリアできます。
HR総研が実施した「人材育成に関する調査」、実に84%のビジネスパーソンが「ビジネスマナーの研修は必要」と答えており、きちんとした対応が信頼につながることを実感しているそうです。こうした環境で働くことで、自分のスキルに手応えを感じ始める方も多いです。
「自分には向いていない」と悩んでいる方こそ、習得した基本スキルを一つの成果と捉えてみてください。その経験は、次の職場でも確実に役立ちますし、事務以外の働き方を探すときにも、大きな自信になるはずです。
【メリット3】社内外でサポート力を実感できてやりがいがある
「自分の仕事って、誰かの役に立ってるのかな?」そんなふうに感じていた女性が、ふとした瞬間に変わることがあります。営業スタッフから「ありがとう、助かった」と笑顔で声をかけられたり、ミスを防げたことで上司に感謝されたり。そうした小さなやり取りの中で、「ああ、私の仕事にはちゃんと意味があるんだ」と実感するんです。
事務職は、表に出ることは少ないかもしれません。でも、だからこそ裏側からチームを支える“縁の下の力持ち”としての存在感は、想像以上に大きいのです。サポートが誰かのスムーズな仕事につながる。その循環の中で、自然とやりがいが生まれてきます。
一見、淡々とした業務に見える事務仕事。でもその裏側には、人と人との信頼がちゃんと息づいています。そう思える場面に出会えたとき、自分の役割がちょっと誇らしく感じられるはずです。
【メリット4】福利厚生や時短制度など柔軟な働き方が多い
事務職の魅力のひとつは、働き方の自由度が高い点にあります。とくに子育てや家庭との両立を考えている女性にとって、これは大きな支えになるでしょう。
なぜなら、育児や介護といった家庭の事情を考慮した制度を整備している企業が多く、厚生労働省のガイドラインに沿って「時短勤務」「在宅勤務」「フレックス制度」などを導入している会社も少なくないからです。
たとえば、損保ジャパンでは、女性社員の割合が高く、産休・育休・時短の実績も豊富。働きやすさを重視した環境づくりが徹底されています(出典:人的資本)。他にも、在宅ワークと通勤を選べるハイブリッド型の制度を導入する企業も増えてきました。
「もう事務は無理かも…」と感じている方も、一度立ち止まって、自分に合う働き方ができる環境かどうかを見直してみてください。制度を味方につければ、今の仕事をもう少しだけ続ける選択もできるかもしれません。
【メリット5】スキルを活かして別職種への転職も視野に入る
事務職で積み重ねた経験は、意外にも幅広い職種で評価される武器になります。たとえば、日々の業務で培ったPCスキルや、部署間のやり取りを円滑にする調整力などは、営業アシスタントやカスタマーサポート、広報など多くの職場で重宝されます。事実、転職支援サイトでも「事務経験が活かせる未経験歓迎の求人」は数多く掲載されており、特に“縁の下の力持ち”としての力を求める企業が少なくありません。
なぜ事務経験が他職種でも評価されるのかというと、事務職は“現場の実務”を裏で支える仕事だからです。社内の誰よりも多くの部署と関わり、細かい変化に気づきながら状況を整理していく力は、プロジェクト進行やクライアント対応などの業務でも即戦力になります。「指示されたことを淡々とこなす」だけではない柔軟性や応用力が、実は多くの仕事に求められています。
実際、資料作成やスケジュール管理のスキルがあれば、広告代理店の進行管理や営業企画職などでも通用しますし、総務や人事などのバックオフィス系へのキャリアチェンジも現実的です。「どうせ事務しかやってないし…」と思ってしまう方こそ、自分のやってきたことを一度じっくり振り返ってみてください。
「事務が向いていない」と感じている人ほど、実はそのスキルを活かせる場が他にたくさんあります。自分の可能性を狭めず、転職サイトで気になる求人を眺めてみるだけでも、新しい一歩が見えてくるかもしれません。完璧でなくても、コツコツ積み上げてきた経験は必ず誰かにとっての“即戦力”です。
事務に向いてない女性でも今すぐ実践できる効果的な対処法
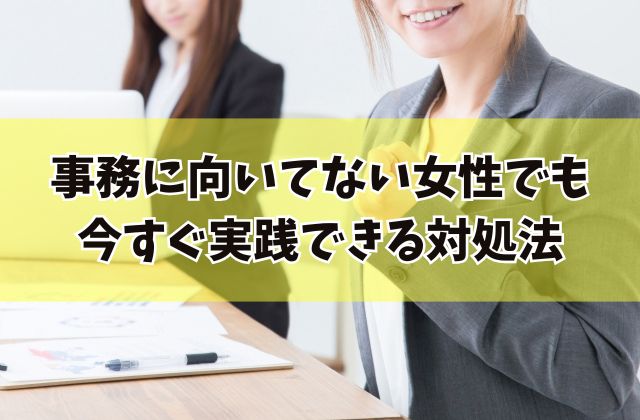
「自分は事務に向いてないかも」と悩みながらも、今すぐ辞めるわけにもいかない現実に直面している女性は多くいます。
ですが、日々の小さな工夫や行動を積み重ねることで、苦手意識をやわらげて前向きに働ける可能性も広がります。
ここでは、事務に向いてない女性でも今すぐ実践できる効果的な対処法を、わかりやすく紹介していきます。
【対処法1】苦手な作業を一覧にして可視化する
「なんだか毎日疲れる」「やることが多すぎて、どこから手をつけていいか分からない」。そう感じたら、まずは頭の中にある“もやもや”を紙に書き出してみてください。特に、事務の仕事でつまずきやすい場面や苦手な作業を、ひとつひとつ棚卸しするのがおすすめです。
実際に「入力作業が遅い」「書類の誤字脱字が多い」「電話対応で緊張する」など、自分の苦手ポイントを目に見える形にして並べていくと、不思議と気持ちが整理されてきます。そして、それぞれに対して「緊急性が高いか」「他人に相談できるか」といった観点で優先順位をつけていくことで、心の負担もグッと軽くなります。
例えば、ToDoリストアプリやカンバン方式の管理ツールを使えば、可視化と同時に進捗も確認できるようになります。手帳やノート派なら、付箋や色分けを使って直感的に整理していくとスムーズです。
苦手は「恥」ではなく「把握すべき特徴」です。無理に克服しようとせず、まずは“苦手なことを見える形にする”という一歩が、事務職での毎日を確実にラクにしてくれます。
【対処法2】作業手順を自分用にマニュアル化する
「なんとなく手をつけると、気づけば何をやっているのか分からなくなる」──事務職でそんなふうに感じたことがあるなら、一度立ち止まって“自分のためだけの手順書”を作ってみてください。面倒に思えるかもしれませんが、これは思考の整理と再確認のための一番シンプルで確実な方法です。
たとえば、毎週やっている経費精算の流れ。領収書の回収、金額の入力、上司への確認依頼…。頭の中だけで処理している作業を一つひとつ言葉に起こしてみると、「この手順、無駄かも」と気づいたり、「この項目だけは忘れがち」と再確認できたりします。チェックリストにしておけば、時間に追われても冷静に対応できますし、誰かに引き継ぐ際の資料にもなるので一石二鳥です。
実際、ある業務改善コンサルティングの調査では、手順を文書化するだけで業務効率が20~30%改善したケースも報告されています。それだけ、目に見える「仕組み」にしておくことは、仕事の安定感を大きく左右するのです。
事務職に向いていないと感じている方こそ、この“自己流マニュアル化”が強い味方になります。完璧なものを作る必要はありません。まずは、今日行った作業の順番を書き出してみる。そこから一歩ずつ整えていくうちに、苦手が「慣れ」に変わっていく感覚をきっと実感できるはずです。
【対処法3】周囲に助けを求めて負担を分散する
「全部ひとりでやらなきゃ…」と頑張りすぎてしまう人ほど、事務職がつらく感じやすいものです。でも、実はその頑張りが自分を追い詰めている原因かもしれません。
たとえば業務で行き詰まったとき、ほんの一言「この部分だけ教えてもらえますか?」と声をかけるだけで、意外なほどスムーズに物事が進んだ経験はありませんか?実際、アメリカのビジネス系メディアが発表した調査でも、タスクを委ねたり相談したりするだけでストレスレベルが約30%下がるという結果が出ています。
「頼る=甘え」ではありません。むしろ、助けを求めることがきっかけで、職場での信頼やコミュニケーションが深まることもあります。小さなことでも言葉にしてみると、周囲も「相談してくれてよかった」と感じてくれるはずです。
負担をひとりで抱え込まず、ほんの少し“分け合う”意識を持つだけで、心の余裕がまるで違ってきます。無理をしすぎず、周囲の力も借りながら前に進んでみてください。
【対処法4】PCやOfficeの基礎講座でスキルアップする
事務の仕事に苦手意識があるなら、PCスキルの底上げから始めてみるのがおすすめです。特にExcelやWordは、基本的な関数や書式設定を理解するだけでも、作業効率が大きく変わります。例えば、ExcelのIF関数やVLOOKUPなどの基礎を知っているだけで、集計業務が手作業から自動化に近づきます。
ヒューマンアカデミーやハローワークの職業訓練でも「パソコン基礎科」は定番で、事務職を目指す多くの女性が受講しています。実際、Microsoft Office Specialist(MOS)といった資格を取ることで、履歴書にも自信が持てるという声も多いですし、「パソコンが使える」と言える裏付けにもなります。
かつて事務職で「自分だけやたら時間がかかる…」と落ち込んでいた女性が、週1回のOffice講座に通っただけで、3か月後には「仕事が前よりずっとスムーズ」と感じるようになったという話も珍しくありません。最初の一歩さえ踏み出せば、苦手は確実に減っていきます。
スキルは裏切らない、とよく言われますが、まさにその通りです。PC操作に自信が持てるようになると、自然と他の業務にも余裕が出てきます。「向いてないかも」と思っていた気持ちも、いつの間にか変わっているかもしれません。
【対処法5】定期的に休憩し軽いストレッチを取り入れる
気づけば何時間も座りっぱなし…という方、多いのではないでしょうか。事務仕事をしていると、ずっと同じ姿勢で作業を続けてしまいがちです。そうなると、肩こりや腰痛はもちろん、集中力もガクンと落ちてしまいます。
実際にある研究でも、「30分に1度の立ち上がり」が疲労や生産性に良い影響を与えると報告されています。デスクに座っている時間が長い人ほど、こまめな“リセット”が必要なのです。
例えば、1時間に1回、軽く背伸びをしたり、椅子に座ったまま足首を回してみたり。大げさな運動でなくても十分です。オフィスで目立たずにできる簡単なストレッチでも、体も気分も驚くほど軽くなります。
「ただ座って頑張る」だけでは、仕事の質も体調もどこかでガタが来ます。だからこそ、意識的に小休憩を挟む習慣をつくってみてください。ストレッチは、あなたの味方になってくれます。
事務に向いてないと感じたら?女性の適職を見つける方法5選

事務の仕事に違和感を覚え、
「自分には向いていないかもしれない」
と感じたときは、無理に耐え続けるよりも、自分に合った働き方を見つけることが大切です。
ここでは、事務に向いてないと感じたら?女性の適職を見つける方法5選として、前向きにキャリアを考えるための具体的なヒントを紹介します。
迷いや不安を整理し、自分にフィットする働き方を見つける一歩にしてください。
【方法1】自己分析で好きや得意を整理する
事務の仕事がしんどい、合ってない気がする——そう感じたときは、一度立ち止まって「自分が何を好きで、どんなことが得意なのか」を整理してみてください。この作業を「自己分析」と呼びます。
というのも、自分の軸がはっきりしないまま働き続けると、「なんとなく毎日がつらい」状態が続いてしまいます。
たとえば、転職サービスdodaでは「過去の経験から強みを洗い出す自己分析」が紹介されていますし、「価値観→得意なこと→好きなこと」の順に紐解く方法が実践されています(出典:参考資料)。好きと得意が交わる部分に、向いている職種のヒントが隠れているのです。
実際に、旅行好きな女性が「人と話すのが得意」「スケジュールを組むのが好き」という理由から、旅行会社のカウンター業務に転職し、やりがいを感じながら働いているケースもあります。
まずは紙に書き出してみることから始めてみましょう。感情が動いたエピソード、夢中になった作業、褒められた経験などを振り返ってみると、自分では気づいていなかった「適職のヒント」が浮かび上がってくるかもしれません。
とはいえ、自分一人で自己分析を進めるのは簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【方法2】無料の適職診断を利用して客観的に自己評価する
「今の仕事、正直向いてない気がする…」そう感じたときに、頼れるのが“無料の適職診断”です。
たとえば、「ミイダス」や「アサイン」といったサービスでは、性格や強み、適した働き方まで、数分の診断で見えてきます。中には、職務適性だけでなく、ストレスの感じやすさや組織内での立ち位置まで教えてくれるものもあり、自分では気づかなかった側面にハッとさせられることもあります。
実際、事務職が「合わない」と悩んでいた女性が診断を通して、自分がアイデア発信や人との関わりを重視するタイプだと知り、広報や企画職に転身した例もあります。自分を知るって、案外キャリアの第一歩なんですよね。
とはいえ、診断結果だけを鵜呑みにする必要はありません。いくつかの診断を比べたり、信頼できる人に感想をもらったりしながら、自分の納得感を大事にしてください。誰よりも、自分の働き方に納得できるかどうかが、一番の判断基準ですから。
【方法3】診断結果をもとに実際の求人をチェックしてみる
適職診断を受けて「自分に向いている仕事」が見えてきたら、ぜひ一度、その診断結果を片手に求人サイトを見てみてください。診断はあくまでスタート地点。実際にどんな仕事があるのかを具体的に見ることで、「自分に本当に合いそうな仕事」がよりクリアになります。
たとえば、dodaの無料診断では「コツコツ進める仕事が向いている」と出た方が、事務の求人だけでなく“管理部門アシスタント”や“オペレーター業務”など、似た傾向の職種にも目を向けるようになります。求人情報を読む中で、自分の得意や苦手と向き合うきっかけにもなりますし、「これなら続けられそう」と感じる仕事に出会える可能性も高まります。
自分の適性とマッチする仕事がどういう求人として出ているのかを知ることは、転職の第一歩です。診断で得たヒントを実際の職探しに活かすことで、やみくもな応募を避け、ミスマッチも減らせます。焦らず、一つひとつ確かめていく姿勢が、自分らしい働き方への近道になります。
具体的な求人の紹介は、転職エージェントの活用が便利です。転職エージェントは求人の紹介に加えて、キャリアの棚卸しや応募書類の添削、面接対策までしっかりサポートしてくれます。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
【方法4】不満や不安を書き出して向いてない理由を明らかにする
「なんかこの仕事、私には合ってないかも」。そんな風に感じたとき、モヤモヤをそのままにしていませんか?頭の中でぐるぐると悩みを抱えているだけでは、いつまでたっても出口は見えてきません。だからこそ、一度立ち止まって、心にひっかかっていることを紙に書き出してみてください。
たとえば、「上司の指示が曖昧でいつも後手に回ってしまう」とか、「業務が多すぎて休憩する余裕がない」といったような、日々感じている小さなイライラや不安。箇条書きでもいいので、とにかく書く。誰かに見せるわけじゃないから、思ったことを素直に書くだけでOKです。
実は、こうした“書くこと”には科学的な裏付けもあります。日本心理学会でも紹介されている「筆記開示」という方法は、頭の中の感情や悩みを外に出すことで、ストレスが軽減されることが分かっています。つまり、感情が整理され、何に悩んでいるのかがはっきりするのです。
大切なのは、「自分には何が合っていないのか」「何が辛いのか」を曖昧なままにしないこと。向いていない理由が見えてくると、次に何をすべきかが自然と見えてきます。たとえ今すぐ転職しなくても、「どんな働き方なら気持ちが楽か」を知ることができれば、それだけで視界がぐっと開けますよ。
【方法5】転職エージェントを使ってプロの意見を聞いてみる
「今の仕事、本当にこのままでいいのかな?」——そんな疑問が頭をよぎったとき、自分ひとりで抱え込まず、転職エージェントに相談してみるという選択肢があります。大手や女性向け専門のサービスでは、ただ求人を紹介するだけでなく、キャリアの棚卸しから書類の添削、面接対策まで、思っている以上に手厚いサポートをしてくれます。
たとえば「アデコ」は、事務職に特化した求人を豊富にそろえており、女性のライフスタイルや希望条件に合わせたマッチングが強みです。担当コンサルタントの丁寧なヒアリングが口コミでも高く評価されています。
ほかにも「リクルートエージェント」では、非公開求人が多く、幅広い業界の情報を収集できるため、自分では思いつかなかった選択肢に出会える可能性もあります。実績データによると、転職成功者の約62%が年収アップを実現しているとのことです。
職場で感じる違和感や、働き方に対する不安。その正体をはっきりさせたいとき、プロの視点はやはり頼りになります。自分では気づけなかった強みを掘り起こしてくれたり、意外なキャリアの道を示してくれたりすることも。今のもやもやを「行動」に変えるための、一つの確かな手段です。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
事務ができない女性向けの転職エージェントおすすめ3選
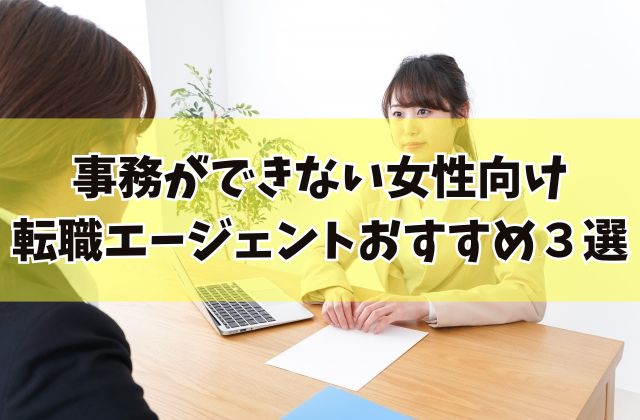
事務の仕事に限界を感じている女性にとって、次の一歩が見えないことはとても不安なものです。
ですが、仕事の選択肢を増やすことで、働き方が柔軟になればこれらの悩みや不安は解消できることは往々にあります。
そこでここからは、事務ができない女性向けの転職エージェントおすすめ3選を厳選して紹介していきます。
転職エージェントを活用することで、将来の可能性がぐっと広がります。
自分に合った職場を見つけたい、環境を変えたいという気持ちが芽生えたとき、頼れるエージェントの存在は心強い支えにもなります。
ここでは、サポートが丁寧で女性に人気の高い転職サービスを厳選してご紹介します。ぜひ、今後のキャリア選択にお役立てください。
【おすすめ1】あなたの価値観を最優先に考える転職支援「アデコ」
『アデコ』は、日本で40年以上にわたり人材紹介を行ってきた実績のある転職エージェントです。特徴のひとつは、正社員として働きたい人に向けたサポートが手厚いこと。担当者が一人ひとりの希望を丁寧に聞き、条件に合う求人を提案してくれます。
特に、子育てやブランクがある女性の転職にも力を入れており、在宅勤務やフレックス対応の職場など、家庭との両立を重視した求人が豊富にそろっています。柔らかく相談できる雰囲気も魅力のひとつです。
履歴書の添削や面接の準備、自分に合った働き方の整理まで、全部無料でサポートしてもらえるので、転職が初めての人にも心強い存在になるはずです。非公開求人も多く、可能性を広げやすい点も見逃せません。
【おすすめ2】約8万人の20代が利用中「第二新卒エージェントneo」
『第二新卒エージェントneo』は、20代の転職を専門に扱う就職サポートサービスです。前職の経験が少ない方やフリーターだった方も対象で、履歴書の添削や面接準備、自己PRの整理まで丁寧に寄り添ってくれます。費用はかかりません。
未経験から挑戦できる求人が多く、取引先の企業は約1万社。その中から希望に合う仕事を紹介してもらえるため、選択肢が広がるのも魅力のひとつです。実際の求人は1万件以上にのぼり、職種や働き方の幅も広めです。
利用者一人あたり平均8時間かけてカウンセリングを行うなど、サポート体制は非常に手厚い印象です。いわゆるブラック企業を避けて紹介する方針もうれしいポイントです。就職に不安がある方でも、一歩踏み出しやすい環境が整っています。
【おすすめ3】転職支援実績NO.1「リクルートエージェント」
『リクルートエージェント』は、1977年から続く実績を持つ老舗の転職支援サービスです。なんと公開求人だけで約38万件、非公開求人も27万件以上という規模で、業界最大級の情報量を誇ります(※2024年3月31日時点の情報)。働き方や業界にこだわりがある方にとって、選択肢が広がるのは大きな魅力です。
担当のアドバイザーは、求職者の希望をじっくり聞き取りながら、履歴書や職務経歴書の作成、面接対策までを丁寧にサポートしてくれます。過去の採用実例や傾向まで共有してくれるため、実践的な準備ができるのも心強いポイントです。
また、登録者専用のシステムでは、応募状況の管理やスケジュール調整がスムーズに行えます。実際に利用した人のうち、およそ65%が「転職先に満足している」と回答している点も、信頼性を裏づけています。
事務に向いてないから今すぐ辞めたい女性への最適な解決策
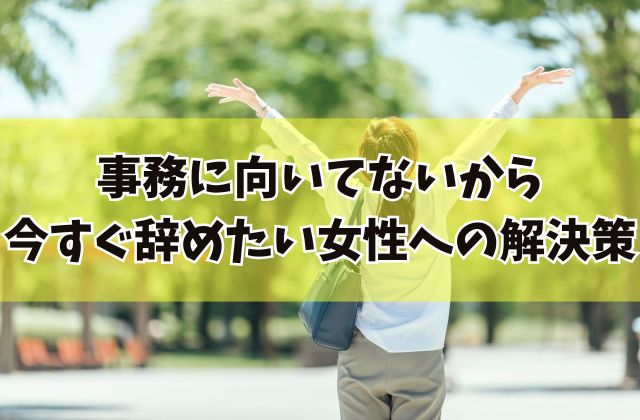
もう無理かも……そう感じた瞬間が、あなたの限界点です。
「事務の仕事がどうにも合わない」「明日も会社へ行くのが憂うつで仕方ない」。そんな時、自分の心と体を守るために使える手段のひとつが“退職代行サービス”という選択肢です。
最近では、LINEで手軽に相談できるサービスも増えており、24時間365日対応可能で依頼件数も年々増加しています(出典:参考資料)。退職成功率はほぼ100%。
中でも「トリケシ」などは、相談のしやすさやアフターサポートの充実度でも支持を集めています。費用はかかりますが、長引くストレスや心の疲弊を考えれば、十分に検討する価値があります。
そもそも日本の職場文化には「辞めづらさ」が根深くあります。「辞めたい」と口にしただけで白い目で見られる。引き止めがしつこく、罪悪感ばかり背負わされる。そんな空気に、心が潰されそうになった人が選んでいるのが退職代行です。
もちろん、最初から使う必要はありません。信頼できる人に相談したり、部署異動をお願いするのも立派な一歩です。でも、あらゆる手段を試しても前に進めないなら、自分の人生を守るための最終手段として、退職代行を使うのは「逃げ」ではなく「自衛」です。
静かに、でも確実に人生を動かしたい——そんなとき、代行という選択肢があなたの背中をそっと押してくれるかもしれません。
ここでは、実績豊富な人気の3社を厳選して紹介します。いずれも24時間相談可能で、いつでもあなたの悩みに寄り添ってくれます。「退職を切り出せずに毎日憂うつ…」そんな状況から、今すぐ抜け出しませんか?
✅24時間いつでも対応!LINEで相談もOK!退職代行サービスおすすめ3選
- 退職成功率100%!完全後払い制の『ヤメドキ』|退職成功総件10,000件以上!24時間365日対応&LINEを通じた無料相談も可能で、退職後2ヶ月間のアフターフォローも提供し離職票などの書類対応をサポート。
- 無期限のアフターフォローも提供する『弁護士法人みやび』|弁護士が直接対応!即日退職や有給消化、未払い給与・残業代・退職金の請求など法的交渉が可能な全国対応の退職代行サービス。
- 全額返金保証付き!最短即日でスピード退職なら『トリケシ』|LINEで24時間相談可能!労働組合が運営する弁護士が監修する安心の退職代行サービスで、即日退職や有給消化の交渉も対応。
【Q&A】事務に向いてない女性に関するよくある質問
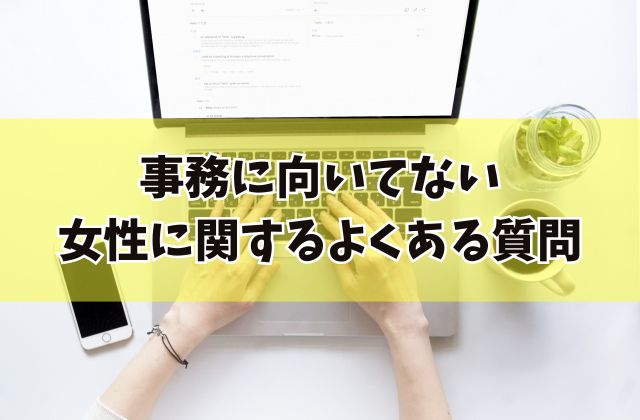
最後に事務に向いてない女性に関するよくある質問をまとめました。
経験談や具体的な対処法を交えて紹介していきます。読んでいく中で、自分の気持ちに素直になれるヒントが見つかるかもしれません。
【質問1】女性にとって一番楽な仕事は何ですか?
結論から言えば、「楽」とされる仕事に絶対的な正解はありません。ただ、多くの女性が「座ってできる」「体力的な負担が少ない」「残業が少ない」といった条件を“楽”の基準にしています。
その視点で人気なのが、データ入力や一般事務といったルーティンワーク系。特に、電話対応が少ない職場での事務職は「精神的にも落ち着いて働ける」といった声が目立ちます。実際、求人サイトでは「女性に人気のラクな仕事」として、事務職・図書館スタッフ・受付などが上位に並びます。自分にとっての“楽”を見つけるには、働き方と性格の相性がヒントになります。
【質問2】ADHDでも事務が苦手なのはなぜ?対処法はある?
ADHDの傾向がある方にとって、事務作業はとにかく“集中が続かない”ことがネックです。
何件もの処理を並行して進めるマルチタスクや、電話が突然鳴る環境は、予測が立てづらく気持ちが乱れがち。けれど、「事務が向かない=働けない」わけではありません。作業を小さく区切ってToDoリスト化したり、チェックシートを活用して抜け漏れを防ぐことで、少しずつ仕事の負担を軽くできます。自分にとって“やりやすい形”を探すことが、事務職を継続するカギになります。
【質問3】事務も接客も向いてない私に合う仕事はある?
事務も苦手、接客もストレス…。そんな悩みを抱えていても、大丈夫です。実際に「人と関わらず静かに働きたい」と考える女性は少なくありません。
最近注目されているのが、モクモクと作業できる軽作業系や、警備スタッフ、倉庫内作業、図書館業務など。人と話す機会が少なく、決められた作業を淡々とこなす仕事には、向き不向きの振れ幅が小さいというメリットがあります。どれも「仕事はきちんとしたいけれど、人間関係に疲れたくない」人にとっては救いになります。
【質問4】「仕事ができない女」の末路って本当に悲惨?
「仕事ができない」と自分で感じてしまった時、それだけで将来が詰むような気持ちになるのはよくあること。でも、実際のところ「悲惨な末路」なんて、ほとんどが思い込みです。
誰にも評価されない仕事に疲れ切ってしまった時は、“見える化”することが効果的。たとえば、1日の作業数を数字で記録するだけでも「ちゃんとやってるじゃん」と自分を認められるようになります。他人の評価より、まずは自分の満足感を取り戻すこと。それが脱・自己否定の第一歩です。
【質問5】ガルちゃんで話題の事務に向いてない女性の特徴は?
ガールズちゃんねるでは「事務に向いてない人って、じっと座ってるのが苦痛」「確認作業が雑で注意される」といったリアルな声が多く見られます。
中には「電話対応で頭が真っ白になる」「毎日が同じでしんどい」という投稿も。こうした特徴に共感するなら、「向いてない」と感じるのも自然です。でもそれって“ダメな人”というわけじゃなくて、ただ向く場所が違うだけ。向いていないことに気づけたなら、今後は自分にとってストレスの少ない仕事選びができます。
まとめ:事務に向いてない女性の特徴と適職を見つける方法
事務に向いてない女性の特徴と適職を見つける方法をまとめてきました。
改めて、事務に向いてない女性の適職を見つける方法をまとめると、
- 自己分析で好きや得意を整理する
- 無料の適職診断を利用して客観的に自己評価する
- 診断結果をもとに実際の求人をチェックしてみる
- 不満や不安を書き出して向いてない理由を明らかにする
- 転職エージェントを使ってプロの意見を聞いてみる
そして、事務に向いてないと感じる女性が知っておくべきポイントもまとめると、
- 事務に向いてないと感じる理由は性格や得意不得意に起因することが多い
- 単調作業やマルチタスク、対人対応へのストレスが苦手意識の原因になる
- 向いていなくても土日祝休みや時短勤務など働きやすさのメリットは大きい
- 自己分析や適職診断で本当に向いている仕事を客観的に探すことができる
- 限界を感じたときは退職代行サービスなどの選択肢で心身を守ることが大切
- 事務が苦手でもサポート力や基礎スキルを活かし、他職種に転職できる可能性がある
「事務に向いてない」という女性の悩みは、決して珍しいものではありません。
誰かにとっての向いてないは、別の誰かにとっての強みでもあります。今の違和感を大切にしつつ、自分に合った働き方や職場を探す一歩を踏み出しましょう。選択肢は必ずあります。