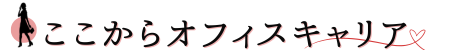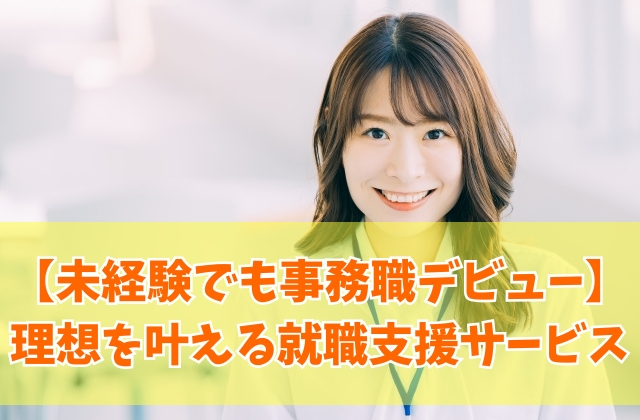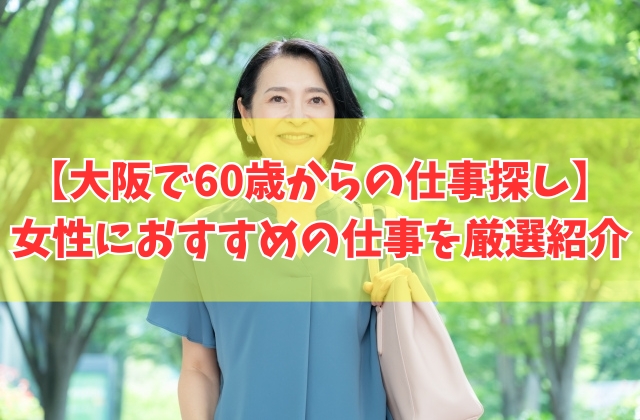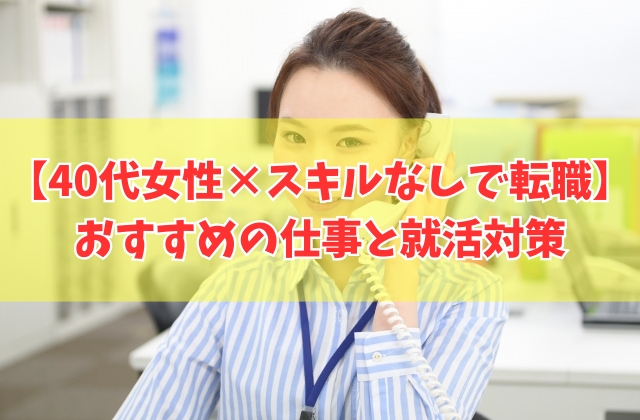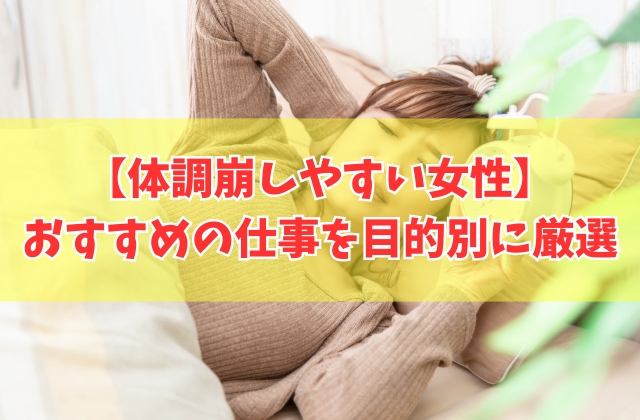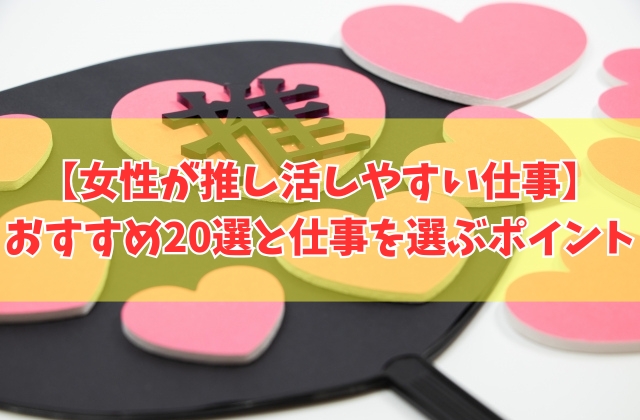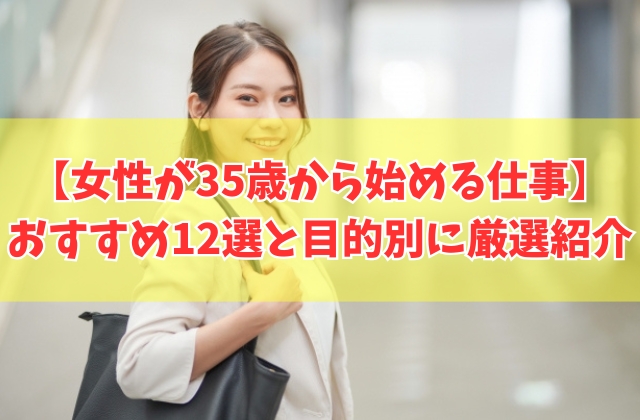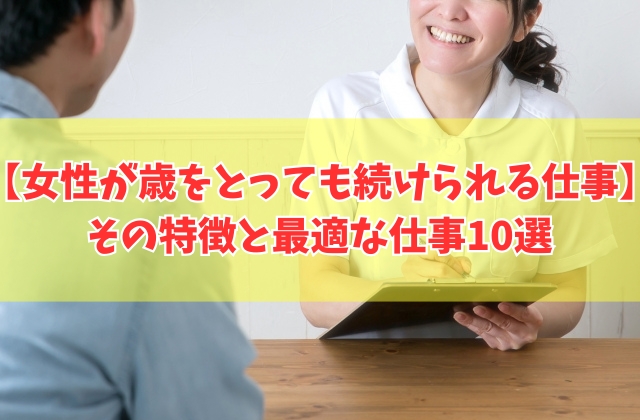
「女性が歳をとっても続けられる仕事には何がある?」
「仕事選びのポイントは?求人はどうやって探せばいいの?」
「年齢を重ねても、まだ働きたい。でも、どんな仕事なら続けられるのだろう?」と不安に感じていませんか。
家庭との両立、体力の変化、将来の安定。女性が長く働き続けるためには、仕事内容や働き方の選び方がとても大切です。
実際に、今の時代には年齢に関係なく活躍できる選択肢が増えています。
この記事では、女性が歳をとっても続けられる仕事の特徴や具体的な職種、求人の探し方までをわかりやすく解説します。
自分らしく働きたいと考える女性の方に、きっと役立つ内容です。ぜひ最後までご覧ください。
- 体力や年齢に左右されにくい働き方を選ぶことが長く働く秘訣
- スキルを活かせる仕事は年齢を重ねても価値が落ちにくい
- 求人探しは派遣会社や専門サイト、自治体の相談窓口も活用
女性が歳をとっても続けられる仕事を見つけるには、自分の得意や経験を活かせる職種を選びつつ、働き方に柔軟性があることが大切です。年齢に縛られず、自分らしい働き方を目指しましょう。
女性が歳をとっても続けられる仕事の特徴5つ
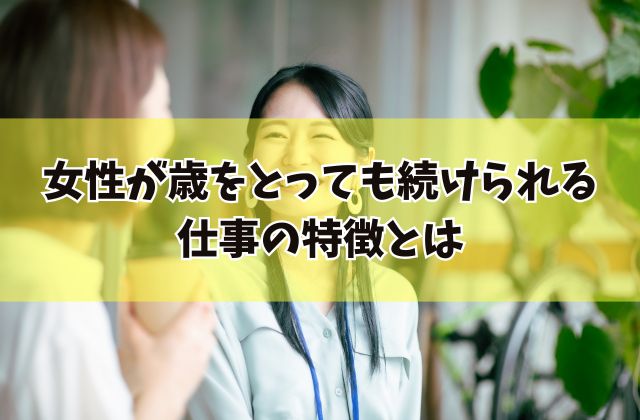
女性が歳をとっても続けられる仕事の特徴を把握することで、将来を見据えた働き方を見つけやすくなります。
体力の変化や家庭の事情に左右されず、長く安心して働ける仕事には共通するポイントがあります。
ここでは、年齢や性別に関係なく働きやすい環境や、将来も安定して続けられる仕事の選び方について、重要な5つの特徴を紹介します。
選択肢を広げるヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
【特徴1】男女・年齢を問わない働きやすさ
「年齢を重ねても仕事を続けたい」と考える女性にとって、いちばん大切なのは年齢や性別に左右されない環境です。
実際、厚生労働省の調査では、誰もが有給休暇を取りやすい職場や人間関係の良さが、長く働ける会社の共通点として挙げられています。
さらに、女性活躍が進んでいる企業では、制度を女性専用にせず「全社員対象」にする方針が多く、性別に関係なく昇進や育休を取れる体制が整っているのが特徴です(出典:令和6年度「なでしこ銘柄」レポート)。
具体的には、フレックスタイムや在宅勤務、時短勤務の導入、成果に基づく昇進制度、介護休業などを年齢や性別を問わず利用できる会社が増えています。こうした環境であれば、家庭や体調の変化があっても仕事を諦める必要がありません。
年齢を重ねても安心して働ける仕事を探すなら、待遇や給与だけでなく、こうした柔軟な制度や文化があるかどうかを一緒に見ておくことが、長く続けられるかどうかを左右する大きなポイントです。
【特徴2】身体的負担が少ない仕事内容である
年齢を重ねても仕事を続けたいと思う女性にとって、最初に考えたいのが体への負担です。若いころは問題なかった長時間の立ち仕事や力仕事も、筋力や柔軟性が落ちてくると一気にしんどくなります。
実際、ある調査では高年齢者を雇う企業の多くが「体力・健康面への配慮」を課題に挙げており、シニア世代の過半数、現役世代の約4割が「体に無理のない働き方」を重視しているという結果が出ています。
体力の消耗を抑えられる仕事には、座ってできるパソコン業務や相談業務、講師・管理系の仕事などが多くあります。また、医療・介護分野では介護補助具やロボット支援機器が普及し、持ち上げ作業や移乗支援の負荷を減らす取り組みが広がっています(出典:教職員介護職イメージ調査と介護職の現状)。
こうした背景を考えると、「女性が歳をとっても続けられる仕事」を探すときに“身体的負担の少なさ”は外せない条件です。仕事内容が自分の体力に合っていれば、気持ちにも余裕が生まれ、長く安定して働き続けやすくなります。
【特徴3】働く時間や場所の自由度が高い
家事や介護、通院など、年齢を重ねるほど暮らしの中に「時間の制約」が増えていくものです。そんな中でも仕事を続けたいと考える女性にとって、時間や場所に縛られない働き方は大きな味方になります。
マイナビの調査によると、リモートワークを経験した人のうち6割以上が「プライベートの時間の使い方が良くなった」と回答しています。さらに女性に限って言えば、その割合は68.9%にまで上昇しており、時間の自由さが日々の生活に与える良い影響の大きさが伺えます。
在宅勤務やフレックスタイム制度など、働き方の選択肢が広がる職場では、体調や家族の都合にも柔軟に対応できます。ただし、「自由」がある分だけ自己管理の力も必要になります。実務上のサポート体制や明確な業務ルールがあるかどうかも、働きやすさを左右するポイントになるでしょう。
時間や場所に縛られない仕事は、年齢に関係なく、自分のペースで無理なく続けられる仕事の代表格です。働き方そのものを見直すことが、「女性が歳をとっても仕事を続けていく」ための第一歩になるのかもしれません。
【特徴4】安定した需要が見込める業界・職種である
将来を見据えて仕事を選ぶなら、「その仕事が10年後も求められているかどうか」を一度立ち止まって考えてみてほしいのです。どんなに条件が良くても、需要が先細る分野では、長く続けるのが難しくなります。
その点、介護や医療、IT業界のように社会基盤を支える業界は、時代が変わっても人の手を必要とし続ける分野です。たとえばIT分野では、2030年までに最大で約79万人の人材が不足すると経済産業省が発表しており、これは一時的なブームではなく、構造的な人手不足を意味しています(出典:IT人材需給に関する調査)。
一方で、介護の世界もまた深刻です。日本の高齢化は止まる気配がなく、介護職における有効求人倍率(令和6年1月分)は7.42倍。つまり、求人数が求職者の7倍以上あるという状態です。IT技術職でも3.16倍(出典:職種別有効求人・求職状況)と高い水準を保っており、両方とも慢性的な人材不足に悩まされています。
今後のキャリアをどう築いていくかを考えるとき、こうした“なくならない仕事”に目を向けておくことは、とても現実的な選択肢になります。とくに歳を重ねてからの再就職や転職では、「安定して働き口があるかどうか」が精神的な安心感にも直結します。
【特徴5】AIや機械に代替されにくいスキルが関わる
「この仕事、将来も必要とされるのかな?」と感じたことはありませんか。近年、AIや自動化技術の進化が加速するなかで、そうした不安を持つのは決して特別なことではありません。
実際、データ入力や単純な事務処理といった作業は、すでにAIに置き換わり始めています。定型的でマニュアル通りの仕事は、スピードも正確さもAIの方が勝る場面が増えました(事務職タスクの24%が高い自動化曝露、58%が中程度曝露。出典:参考文献)。
けれど、だからといってすべての仕事が奪われるわけではありません。むしろ、AIでは対応が難しい仕事こそ、これからの時代に必要とされ続けるのです。たとえば、カウンセラーや介護職、教育やクリエイティブ系の仕事など、人と人との関わりや感情の読み取りが求められる職種は、その典型例です。
感情の機微を汲み取ったり、相手に寄り添った言葉を選んだりする力は、どれだけテクノロジーが進歩しても人間ならではの能力です。また、状況に応じて柔軟に判断したり、細やかな気配りを自然にできることも、AIには真似できない強みといえるでしょう(出典:参考文献)。
将来を見据えて仕事を選ぶなら、こうした「代替されにくいスキル」が活かせる分野に目を向けてみてください。資格や経験だけではなく、“人としての感性や判断”が武器になる仕事こそ、年齢を重ねても長く活躍できる場所になります。
女性が歳をとっても続けられる仕事10選

ここまで、女性が歳をとっても続けられる仕事の特徴を5つ紹介してきました。
年齢を重ねても無理なく働ける職業には、いくつかの共通点があります。たとえば、身体的な負担が少ないことや、働く時間の柔軟さ、人と接する機会の多さなどが挙げられます。
ここでは、そうした共通する特徴を踏まえた「女性が歳をとっても続けられる仕事10選」を紹介します。
どんなライフステージにあっても、女性が自分らしく働き続けたいと考える方に役立つ職種ばかりです。ぜひ、仕事選びの参考にしてみてください。
【仕事1】結婚相談所経営
年齢を重ねても無理なく続けられる仕事の一つに、結婚相談所の経営があります。大きなオフィスを構えなくても、自宅の一室やレンタルスペースを使って始められるため、初期費用を抑えられるのが魅力です。入会金や月会費、成婚料など複数の収益ポイントがあり、うまく仕組みを整えれば安定的に利益が見込めます。
実際、会員20名規模の運営でも年間600万円程度の売上が見込めるという事例が公開されていますし、本業として会員50名規模まで拡大すると年間1,380万円に達するケースも紹介されています。
数字だけを見ると華やかに思えますが、肝心なのは「人の幸せ」を支えるという視点です。成婚に向けた丁寧なサポートや信頼関係の構築が欠かせず、その積み重ねが経営の土台を強くしてくれます。
「人生の節目に寄り添う仕事」として、結婚相談所の経営は単なる収益モデルにとどまりません。人との出会いが好きで、相手の気持ちに寄り添える女性の方にとっては、年齢を重ねても誇りを持って続けられるやりがいのある仕事です。
※
【仕事2】介護福祉士・介護職
「いくつになっても、誰かの役に立てる」。そんな気持ちを大切にできる仕事が、介護福祉士という職業です。実際、令和4年度時点で介護職員は全国で215万人を超え、2026年には240万人以上が必要になると言われています(出典:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について)。
つまり、介護福祉士・介護職は年齢や経験を問わず、常に求められている仕事なのです。
もちろん、身体的に大変な場面もあります。ただし今は、現場の負担を減らす工夫やサポート体制も進んでいますし、体力面が心配な方には生活援助や事務系の業務を中心としたポジションも用意されています。実際、現場では50代・60代の女性も多く活躍していて、「若い人にはない視点で寄り添える」と高く評価されていることも報告されています(出典:参考資料)。
さらに、2024年には介護報酬が改定され、処遇改善加算の一本化や賃金の底上げも実施されました(出典:令和6年度介護報酬改定に関する審議報告)。これにより、やりがいだけでなく収入面でも安定を感じられる環境が整いつつあります。年齢を重ねた今だからこそ生きる優しさや気づき——その力を、介護の現場は必要としています。
※
【仕事3】販売・接客スタッフ
「販売や接客の仕事って、若い人向けじゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、実は年齢を重ねた女性にこそ向いている一面があります。接客経験が長い人ほど、お客様の表情やちょっとした仕草からニーズを読み取るのが上手になりますし、丁寧な言葉遣いや落ち着いた雰囲気は、むしろ年齢を重ねた方ならではの強みです。
実際、2024年7月の求人データによれば、販売・接客職の求人数は16万件以上にのぼっています(出典:一般職業紹介状況)。コロナ前ほどではないとはいえ、需要が安定している証拠です。一方、年収は平均339万円と全体平均よりやや低め(出典:doda調べ)ではありますが、接客スキルを磨けば店長やエリアマネージャーといった道も見えてきます。
注意点を挙げるなら、立ち仕事が多く、体への負担を感じやすいこと(出典:小売業・飲食店における労働災害防止の進め方)。また、セルフレジやAI接客の普及により、単純な販売業務は減る傾向にあります(出典:参考資料)。だからこそ、ただ売るだけでなく「あなたから買いたい」と思ってもらえる接客スキルを持つ人が、今後ますます重宝されるでしょう。
派手ではないかもしれませんが、「人と接するのが好き」「ありがとうと言われると嬉しい」と思える女性の方にとって、販売・接客の仕事は長く付き合える仕事になり得ます。
※派遣
【仕事4】Webデザイナー
「パソコン1台で、一生食べていけたら」──そんな風に考えたことがある女性の方に、Webデザインの仕事はとても相性がいいかもしれません。
実際、ネット広告やECサイトは今やどの業界でも必須。新しいお店ができればホームページが要る。イベントを開くにも告知が必要。こうしてWebデザインの需要は、景気に左右されにくいかたちで増え続けています(出典:電子商取引に関する市場調査)。今の世の中、どんな小さな事業でも「見せ方」が問われる時代です。
ただし、最近ではAIやテンプレートツールも進化していて、単純なバナーやレイアウトだけなら自動生成も可能になっています。でも、だからこそ人にしかできない部分──たとえば「依頼主の想いを形にする力」や「誰かの心を動かす工夫」が、かえって重視されるようになっています(出典:参考文献)。
年齢を重ねてきたからこそ磨かれる観察力や言葉の選び方は、大きな武器になります。流行に振り回されず、“伝わるもの”を丁寧に作りたい。そんな方にとって、Webデザイナーは長く続けられるどころか、年を重ねるほどに深みが増す仕事と言えるでしょう。
※
【仕事5】ITエンジニア
「手に職をつけて、年齢に左右されずに働ける仕事がいい」。そんな思いを抱く女性に、ITエンジニアという選択肢は現実的で力強い道です。
実際、経済産業省の予測では、2030年には国内で最大79万人ものIT人材が不足するとされ、需要は今後も伸び続ける見通しです。人が減っていく社会のなかで、技術に携わる仕事が必要とされるのは自然な流れでしょう(出典:参考文献)。
特にクラウドやAI、ビッグデータ、セキュリティのような先端分野は、新しいサービスが次々に生まれるため、経験を積むほど仕事の幅が広がります(出典:デジタルスキル標準)。スキルアップの機会が多い分、収入面やキャリア面で長く活躍できるのも強みです。
もちろん、プログラミングだけできればいいわけではありません。依頼する企業の意図を読み取り、全体像を描き、課題を整理して提案する力が必要です。ここはAIではなく人間にしかできない部分で、年齢とともに磨かれる視点や調整力がむしろ活きます。
「女性が歳をとっても続けられる仕事」として、ITエンジニアは単なる専門職にとどまらず、人生のステージが変わっても頼れる武器になります。経験と学びを重ねることで、むしろキャリアに深みが出る仕事です。
※
【仕事6】Webライター
年齢を重ねても、自分のペースで働き続けられる仕事を探しているなら、Webライターという選択肢は意外と穴場かもしれません。特別な資格は必要なく、パソコン1台とネット環境があればどこでも始められます。
しかも、実際の現場では「書ける人材が足りない」という声がいまだに多く、2024年の今もWebライターへのニーズはしっかり存在しています(出典:エンタメ・クリエイティブ産業戦略)。SEO対策やブログ運営、ECサイトの商品紹介など、求められる文章の種類は多岐にわたり、案件数も決して少なくありません。
特に、生活経験や主婦目線を活かした記事には独自の強みがあり、年齢がむしろ“味”になるケースもあります。もちろん最初は少し勉強が必要ですが、地道に実績を積めば、年齢に関係なく信頼される仕事に育てていけます。
「女性が歳をとっても価値を出せる仕事」として、Webライターは現実的で心強い選択肢と言えるでしょう。
※クラウドワークス
【仕事7】コールセンター
「年齢を重ねても働き続けたい」──そんな気持ちを支えてくれる選択肢のひとつが、コールセンターでの仕事です。実はこの職種、意外と幅が広く、パートや派遣、契約社員といった多様な働き方が可能で、自宅近くの職場を選びやすい点も魅力です(出典:コールセンターオペレーター)。
特に中高年層の女性からのニーズは根強く、実際に求人倍率も高めです。たとえば、全国でもコールセンターが集まるエリアでは、有効求人倍率が1.22倍というデータも出ています(出典:一般職業紹介状況(令和7年7月分))。企業側としても「人材が足りない」という声が多く、求職者にとっては選択肢が広がっている状態です。
もちろん、電話対応が続く中でのストレスや、クレーム処理などに苦労することもあるかもしれません。でも最近は、夜勤なし・ノルマなし・相談体制が整った職場も増えてきました。自分の体力や生活リズムに合った職場をきちんと選ぶことで、「無理なく」「長く」続けていける現実的な仕事になり得ます。
※派遣
【仕事8】清掃スタッフ
「今の体力でも無理なく働けて、人の役にも立てる仕事がしたい」──そんな気持ちに寄り添えるのが、清掃スタッフという働き方です。特別なスキルや資格がなくても始められ、週に1~2回、短時間から働ける募集も多く見つかります。実際、特定の清掃業の有効求人倍率は2~3倍と高く、ほかの職種に比べて求人数が多いのも特徴です(出典:厚生労働省調べ)。
ただし、仕事の内容は意外と幅広く、床やトイレ、エントランスの掃除、ゴミの回収など、黙々と体を動かす場面が中心になります。とくに大型施設や病院では、衛生管理のルールが厳しく、丁寧な対応が求められます。身体にかかる負担もゼロではありません。
そのため、続けやすい環境を見極めることが何より大切です。たとえば、室内中心の現場や、作業が分担されていて重い荷物の持ち運びがないところ。勤務時間が短めだったり、シフトに融通が利いたりする職場なら、年齢を重ねても無理なく続けられる可能性が高くなります。
「きれいになって気持ちいい」と感じられる女性の方にとっては、長く付き合っていける仕事になるはずです。
【仕事9】家事代行スタッフ
「家庭での経験をそのまま活かせる仕事を探している」——そんな女性にぴったりなのが家事代行の仕事です。料理や掃除、洗濯など、日々当たり前のようにこなしてきた家事のスキルが、実は仕事として強みになります。未経験からスタートする人も多く、丁寧な研修を用意している企業が多いので安心です。
さらにこの仕事の魅力は、何といっても働き方の自由度。平日だけ、午前中だけ、月に数回など、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができます。小さなお子さんがいる方や、親の介護と両立したい方にも向いています。
ただ、他人の家に入って作業をする仕事なので、礼儀や清潔感はもちろん、相手の価値観を尊重する姿勢も欠かせません。限られた時間のなかで効率よく動く段取り力や気配りも求められます。
無理のない範囲で少しずつ始め、続けられるペースを見つけていくこと。それが、年齢を重ねても長く続けられる秘訣です。
※派遣
【仕事10】図書館スタッフ・資料整理
図書館の仕事に惹かれる理由は人それぞれですが、「落ち着いた場所で、本と関わる仕事がしたい」と考える方は少なくありません。なかでも資料整理や本の配架といった業務は、黙々と作業に集中できるため、人と関わる仕事が少し苦手な方にも向いています。
実際の求人を見ると、司書の資格がなくても「図書館スタッフ」として働ける募集が多く見られます。雇用形態もパートや契約職員など柔軟で、週3日から無理なく働けるケースも少なくありません。もちろん、資格を持っていると任される業務の幅が広がるので、現場経験を積みながら資格取得を目指す方もいます。
ただし、図書館の仕事は座ってばかりではありません。書架の整理や蔵書点検など、意外と体を動かす場面も多く、腰を使う作業が続くこともあります。とはいえ、喧騒のない静かな空間で本と向き合える仕事は、年齢を重ねても続けやすいという声が多く聞かれます。
「本が好き」という気持ちがあれば、図書館の仕事は年齢に関係なく取り組める魅力的な選択肢です。焦らず、無理せず、自分のペースで働きたいと考える女性にとって、まさに理想の職場と言えるでしょう。
女性が歳をとっても続けられる仕事を選ぶメリット
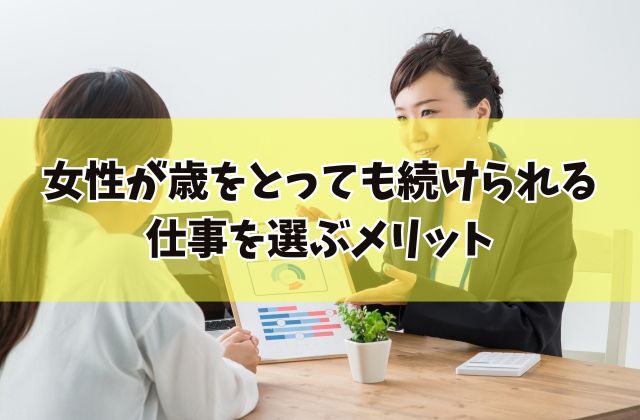
ここまで、女性が歳をとっても続けられる仕事を具体的に紹介してきました。
歳を重ねても働き続けられる仕事には、単なる収入源以上の価値があります。
たとえば、過去の経験や積み重ねてきたスキルを無理なく活かせたり、家庭との両立がしやすかったりと、年齢に応じた働き方が実現しやすい点が大きな魅力です。
このような「女性が歳をとっても続けられる仕事を選ぶメリット」について、次の項目で具体的にご紹介します。
【メリット1】経験やスキルが長く活きる
年齢を重ねても仕事を続けていくうえで、「これまでの経験がそのまま武器になる」環境は何より心強いものです。
たとえば事務のスキルや接客で培った対応力は、一朝一夕で身につくものではなく、現場では即戦力として重宝されます。実際、40代以降を積極的に採用する企業も少なくありません(出典:令和5年 雇用動向調査 結果の概況)。
さらに、ある程度の年齢になると、単なる作業ではなく「人を支える」「全体を整える」といった視点で動けるようになります。これは若手にはなかなか真似できない強みです。ITや医療など特定分野では、知識を深めるほど仕事の幅が広がり、歳をとっても現役で働く女性が多く活躍しています(出典:労働力調査)。
とはいえ、ただ昔のやり方を繰り返していては取り残されます。必要なのは「もう一度学ぶ」という姿勢です。環境や技術の変化にしなやかに対応できれば、年齢はむしろ味方になります。だからこそ、「女性が歳をとっても続けられる仕事」として、自分の経験やスキルを活かせる場を選ぶことは、安心して長く働くうえで大きな意味を持つのです。
【メリット2】ライフイベントと両立しやすい
結婚、出産、子育て、親の介護——女性の人生には、何かと「立ち止まらざるを得ない瞬間」が訪れます。そんなとき、キャリアを中断せずに続けられる仕事があると、心の余裕もまるで違ってきます(出典:男女共同参画白書)。
たとえば、在宅勤務ができる環境なら、子どもが急に熱を出しても、そばにいて様子を見ながら仕事を進めることができます。今ではフレックス制を導入する企業も増え(前年比+1ポイント、出典:参考資料)、通院や家族の都合にも柔軟に対応できるケースが目立ちます。
とはいえ、制度があるだけでは不十分です。実際に使える雰囲気がなければ、結局「我慢して働く」状態になってしまうからです。制度が機能している職場かどうかは、社員の口コミや実際に使っている人の存在で見えてきます。
無理をしないで働ける。家族を優先しても後ろめたくない。そんな働き方ができる職場を選ぶことが、「歳をとっても仕事を続けていくための強さ」に繋がるのではないでしょうか。
【メリット3】精神的なやりがいを感じやすい
年齢を重ねても続けられる仕事を探すとき、多くの女性が口をそろえて言うのが「やっぱりやりがいがないと続かない」という声です。これは、単なる理想論ではありません。内閣府が行った調査でも、仕事にやりがいを感じている人は、職場や働き方に対する満足度が明らかに高いという結果が出ています。
では、「やりがい」とは何なのでしょうか?
たとえば、誰かの悩みに寄り添い感謝の言葉をもらったとき、あるいは地道に積み重ねてきた経験が実を結んだ瞬間。そうした出来事が心の芯を温かく満たし、「また頑張ってみよう」と思わせてくれます。特に、年齢とともに体力や時間に制約が出てくるなかで、精神的な充足感は働き続ける上で欠かせない原動力になります(出典:参考資料)。
とはいえ、やりがいだけに頼りすぎるのも少し危うい側面があります。感情の波が激しい職場や、常に気を張りつめているような仕事では、心が擦り減ってしまうからです。大切なのは、「無理をせずに、自然体でやりがいを感じられるか」。自分の価値観やペースに合った仕事なら、年齢を問わず、穏やかに長く続けていけます。
女性が歳をとっても続けられる仕事を選ぶ際の注意点
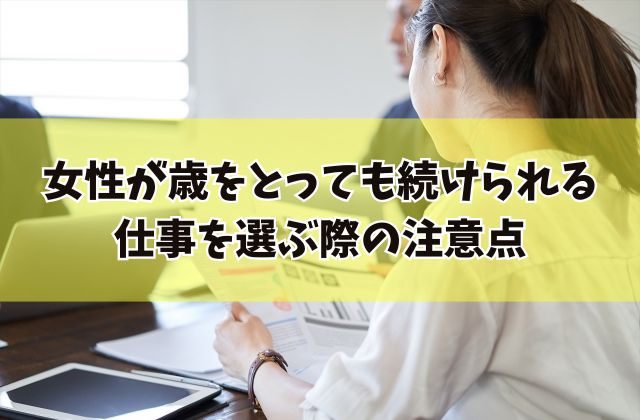
年齢を重ねても働き続けるには、「女性が歳をとっても続けられる仕事を選ぶ際の注意点」をきちんと押さえておくことが大切です。
どれほど魅力的に見える職種でも、体力や健康への負担、収入と年金の兼ね合い、そして時代の変化による影響などを見落としてしまうと、長く安定して働き続けることが難しくなる可能性があります。
ここからは、特に気をつけたいポイントを具体的に紹介します。
【注意点1】仕事内容が体力的・精神的に負荷にならないか注意する
年齢を重ねてからの働き方を考えるうえで、「体と心に負担がかかりすぎないか」は避けて通れないチェックポイントです。若い頃は平気だった立ち仕事や力仕事も、50代・60代になると無理がきかなくなり、疲労が長引くようになります。
実際、リクルートワークス研究所の報告書によると、50代では「仕事量」、60代では「仕事の質」に対するパフォーマンスが大きく低下する傾向があるといいます。これは、身体的・精神的な負荷の蓄積が、目に見える形で現れはじめるタイミングでもあるのです。
そこで、仕事を選ぶときには以下のような点をきちんと確認しておくと安心です。
- 重い荷物を運んだり、長時間立ちっぱなしになる作業が含まれていないか
- 電話やクレーム応対など、ストレスのかかる対人業務が多すぎないか
- 自分のペースで作業できる環境か(分割作業・小休憩などが取りやすいか)
こうした要素に気を配ることで、体力の変化や生活のリズムにも無理なくフィットする仕事と出会いやすくなります。年齢に左右されず、穏やかな気持ちで仕事を続けるには「働きやすさ」に目を向けることが何より大切です。
【注意点2】健康状態が仕事に追いつかないリスクを把握する
年齢を重ねれば、誰しも体のどこかにガタがくるもの。若い頃と同じペースで働けると思っていても、疲労の回復が遅くなったり、思わぬ病気にかかってしまったりと、心身の変化に気づく瞬間が増えてきます。
実際、厚生労働省の統計では、60歳以上の労働者が関わる4日以上の休業を伴う労働災害の割合が上昇しています(出典:高年齢労働者の安全衛生対策について)。
さらに、加齢に伴う筋力や平衡感覚の衰えが、転倒やケガのリスクを高めるという指摘も専門家の間で増えています(出典:参考文献)。
だからこそ、仕事を選ぶときには、以下のような点に注目することがとても大切です。
- 重たいものを持つ作業や長時間の立ち仕事がないか
- 急なシフト変更や夜勤など、身体への負担が大きすぎないか
- 作業量を調整できる職場環境や、こまめな休憩が取れる体制があるか
今の自分の体に正直になって、無理のない働き方を選ぶ。それが、将来にわたって安心して仕事を続けるための大切な準備になります。「頑張りすぎない働き方」を意識することが、長く働くための第一歩なのです。
【注意点3】収入と年金のバランスが崩れないようにする
「年金をもらいながら少しだけ働きたい」と考える女性にとって、思わぬ落とし穴になりやすいのが“収入と年金のバランス”です。実は、働いて得られる給与額によっては、せっかくの年金が減額されたり、場合によっては支給停止になることもあります。
たとえば、「在職老齢年金制度」では、月収と年金を合わせて約50万円を超えると、その超えた分の一部が年金から差し引かれる仕組みです(出典:在職老齢年金制度の見直しについて)。つまり、高収入な仕事を選んだつもりが、結果として手取り額が変わらない、あるいは減ってしまうというケースも珍しくありません。
だからこそ、働く前に以下のようなポイントをきちんと整理しておくことが大切です。
- 給与と年金の合計が減額ラインを超えないかを確認する
- 在職老齢年金の制度をあらかじめ理解しておく
- 増えた収入によって、どのくらい年金に影響が出るかを把握しておく
収入を増やすことだけに気を取られず、「トータルでどのくらい生活にプラスになるのか?」という視点で仕事を選べば、年金と両立しながら、無理なく長く働き続けられる道が見えてきます。
【注意点4】将来の技術変化で仕事が消える可能性を検討する
今ある仕事が、10年後も存在しているとは限りません。特にAIやロボットの進化が目覚ましい近年、「気がつけば自分の仕事が機械に取られていた」なんて話も現実味を帯びてきました(出典:参考文献)。ルーティン中心の作業や、マニュアル通りに進められる業務は、すでに代替の波がじわじわと押し寄せています。
一方で、今後も人間の手が必要とされる仕事もあります。たとえば、誰かの気持ちを汲み取って対応する接客や介護、あるいは経験と判断力がものをいう現場管理など、機械には真似できない領域がまだまだ多く残っています(出典:参考資料)。
これから長く働いていきたいと考えるなら、「人間ならではの強みが活かせるかどうか」に注目して仕事を選ぶのがおすすめです。ポイントとしては、
- アイデアを生み出す仕事(企画やデザインなど)
- その場の判断が求められる仕事(介護・接客・現場対応など)
- 技術や環境の変化にあわせて柔軟に学べる余地があること
変化が激しい時代だからこそ、「変わらない自分の価値」を見つけて、それを軸に働き続ける道を選んでいきたいですね。
【注意点5】スキル・知識の陳腐化に備えて学び直しを検討する
「昔とった杵柄」がいつまでも通用する時代は、残念ながら終わりを迎えつつあります。実際、IT業界を中心に、多くの分野で“スキルの寿命”は年々短くなっており、平均して4年ほどで陳腐化するとまで言われています(出典:参考資料)。とくに変化の激しい業界では、2~3年で役に立たなくなることもあるのが現実です。
だからこそ、「今のままで大丈夫かな」と感じたときこそが、動き出すタイミングです。年齢に関係なく、自分のペースで学び直す環境はいまやたくさん整っています。
- オンライン講座やYouTubeで手軽に学べる
- 興味のある資格取得を目指してみるのも◎
- 図書館や地域の講座でコストをかけずに知識をアップデートできる
一度キャリアの土台を築いた人ほど、ほんの少しの学び直しで可能性が広がります。「学び続ける力」こそが、どの年齢でも働き続けられる最大の武器です。仕事を長く続けたいと考えているなら、ぜひ“自分をアップデートする習慣”を意識してみてください。
女性が歳をとっても続けられる仕事の求人を探す最適な方法
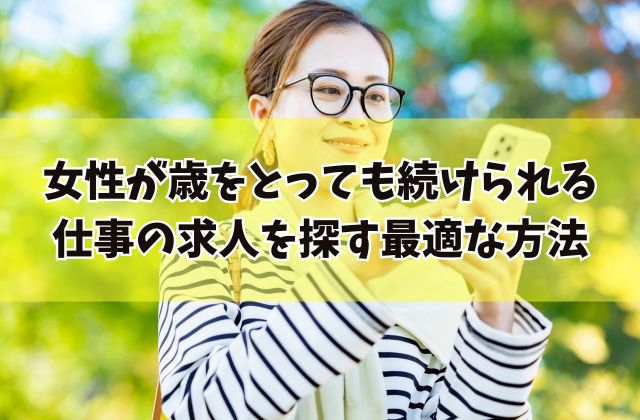
年齢を重ねても安心して働き続けたいと考えるなら、求人の探し方にも少し工夫が必要です。
働く場所や条件にこだわるだけでなく、将来を見据えて選ぶ視点が大切になります。
そこで、女性が歳をとっても続けられる仕事の求人を探す最適な方法をまとめました。
仕事の探し方を知っておくことで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。
次の項目では、具体的にどのような探し方が効果的なのかをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
【方法1】在宅勤務・リモート可の求人を優先的に探す
年齢を重ねても無理なく働き続けたいと考えるなら、「在宅勤務OK」や「リモート可」といった条件に注目するのがおすすめです。実際、dodaの公開データを見ると、2023年以降リモートワーク対応の求人は右肩上がりで増えており、今では決して珍しい働き方ではなくなりました。
さらに、2024年時点で日本全体のテレワーカー比率は24.6%にまで上昇。そのうち女性は16.9%を占めているというデータも出ています(出典:令和6年度 テレワーク人口実態調査)。少し前までは一部のIT職種だけの働き方という印象があったかもしれませんが、今では事務職や営業サポート、カスタマー対応など、幅広い分野でリモート求人が出ています。
ただし注意点もあります。「リモートOK」と書かれていても、実際は週に1~2回の出社が条件になっていることもあります。応募前に、どの程度の出社が求められるかを確認しておくことが大切です。自宅での仕事が中心で、時間にも体にも無理がない働き方を目指すなら、在宅・リモート可の求人は積極的に探す価値があります。
※
【方法2】派遣会社に登録して非公開求人を紹介してもらう
もし「歳を重ねても安心して働ける職場を探したい」と感じているなら、派遣会社に登録するのも一つの手です。なぜなら、派遣会社に登録している人だけに紹介される「非公開求人」という特別な求人があるからです。
実際、非公開求人には条件が良い案件や人気企業の募集が多く含まれています。企業側が「多くの応募を避けたい」「ミスマッチを防ぎたい」といった理由で、公開せず信頼できる派遣会社を通じて人材を絞っているのです。
ただし、誰でも紹介してもらえるわけではありません。希望する職種や勤務地、これまでの経験などが求人内容と合致しているかがカギになります。それでも、プロのキャリアアドバイザーが希望や適性をしっかりヒアリングしてくれるため、合う案件があれば提案してもらえる可能性は十分にあります。
年齢を重ねた今だからこそ、自分のスキルや希望をきちんと理解してくれる“人を介した”サポートは心強いもの。求人サイトだけでは出会えない仕事が、派遣会社を通じて見つかることもあるのです。
※派遣
【方法3】業界・職種別の専門求人サイトをチェックする
どんな仕事が合っているのか、漠然と探しているうちはなかなかピンと来る求人に出会えません。そんなときに頼りになるのが、業界や職種に特化した専門求人サイトです。
たとえば、ITやクリエイティブ分野なら「Green」※、女性向けの求人を多く扱うサイトなら「女の転職type」などが知られています。こうしたサイトは、業界ごとの細かい条件や働き方に配慮した求人が多く、希望に合った仕事が見つかりやすいという特徴があります。
総合求人サイトでは埋もれてしまいがちな情報も、専門サイトならピックアップされて表示されるため、「歳を重ねても無理なく働ける仕事」と出会える確率がぐっと上がります。
もちろん、扱う業種が限定されている分、求人数は少なめに感じることもありますが、そのぶん“合う仕事”に早く出会える可能性は高くなるメリットもあります。
求人探しで迷っているなら、まずは自分の希望する業界に強いサイトから覗いてみてください。
【方法4】クラウドソーシングで自分のスキルに合う案件を探す
「自分のペースで働きたい」「外に出るのは難しいけれど、何かできる仕事はないか」──そんな思いを抱えている方にこそ、クラウドソーシングは心強い選択肢です。
代表的なサービスであるクラウドワークスには、なんと500万人以上が登録しており、掲載されている仕事の種類も250ジャンル以上。在宅で完結する仕事が豊富に揃っています。
ただし、やみくもに応募するのではなく、「自分に何ができるか」を意識して探すことが、満足のいく案件に出会う第一歩です。例えば文章を書くのが得意ならライティング案件、趣味で画像編集をしてきたならバナー制作など、自分の経験を活かせる仕事に絞るだけでも、当選率がぐっと上がります。
最初から高単価の案件を狙うのは難しいかもしれません。でも、小さな仕事で実績を積み重ねていけば、評価がつき、仕事の幅も広がります。年齢に関係なく、自分の経験を活かしながら働ける環境として、クラウドソーシングは非常に有効な手段です。
【方法5】地域のハローワークやシニア相談窓口を利用する
「年齢的にもう無理かも…」と不安になったとき、まず足を運んでほしいのが地元のハローワークです。特に、再就職を目指す60代女性にとっては、一般の求人サイトでは出会えない情報や支援が詰まっています。
たとえば、東京都新宿のハローワークには「シニア応援コーナー」という専用窓口があり、55歳以上の方を対象にした丁寧な個別相談が受けられます。全国的にも「生涯現役支援窓口」が300カ所以上に設置されており、60歳以上でも働きたい人を後押しする体制が整っています。
求人紹介はもちろん、履歴書の添削や面接の準備までしっかりサポートしてくれるので、ブランクがある方や初めての転職にも安心です。「もう歳だから…」とためらわず、一度相談してみるだけで視野が大きく広がるはずです。
【Q&A】女性が歳をとっても続けられる仕事に関するよくある質問
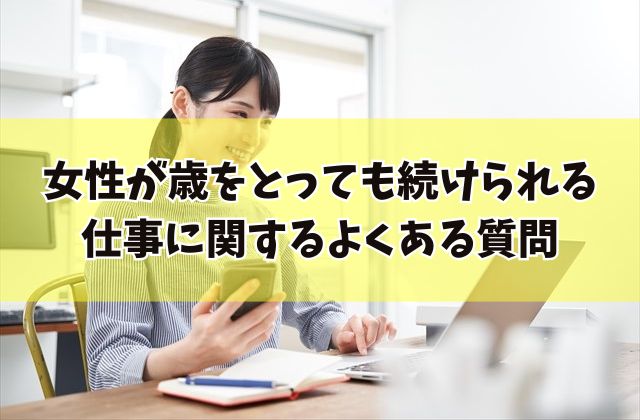
女性が歳を重ねても安心して働き続けるためには、仕事内容だけでなく、将来の働き方や自分に合った選択肢を知っておくことが大切です。
そこで、女性が歳をとっても続けられる仕事に関するよくある質問として、よく寄せられる悩みや疑問をひとつずつ整理し、わかりやすくお答えしていきます。
長く続けられる仕事探しや再スタートを考える女性の方にとって、きっとヒントになるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
【質問1】女性が長く続けられる仕事になる資格は?
年齢を重ねても活かせる資格を選ぶなら、やっぱり「安定性」と「実務性」がキーワードになります。
たとえば介護福祉士は、超高齢化社会を迎える日本ではこれからもっと必要とされる職種。国が出しているデータでも、2022年度と比べて約57万人の人材が追加で必要になる見込みです(出典:介護人材確保に向けた取組)。
また、登録販売者も注目です。医薬品を扱えるこの資格があれば、ドラッグストアや薬局など、地元で働きやすい職場の選択肢がぐっと広がります。派手さはないかもしれませんが、こうした「生活に根ざした資格」こそ、長く働くうえで頼りになる武器になります。
【質問2】女が一生独りで生きていける仕事は?
もしも人生を一人で切り開いていくなら、「この仕事なら絶対に食べていける」と思える分野を選びたいですよね。
たとえば医療・介護、飲食、小売などは、実際に高齢層の就業者がどんどん増えている分野。景気にそこまで左右されず、常に誰かの生活に直結している業種だからです(出典:高齢化の状況)。
もう一つの狙い目がIT。なんと2030年には最大で約79万人の人材が不足すると予測されており、スキルさえあれば年齢を問わず需要があります。たった一つに絞らず、複数の仕事を持つ「ゆるく分散した生き方」が、今の時代には無理なく長く働くためのカギになるかもしれません。
【質問3】長く続けられる女性向けのパートは何がありますか?
「年齢を重ねても無理なく続けられるパート」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?答えは案外シンプルで、身近な場所で需要が絶えない仕事です。
たとえば、販売スタッフ、清掃、介護サポートなど。これらは実際に、高齢の女性の就業者数が着実に増えている職種でもあります。地域のシルバー人材センターなどを活用すれば、ちょっとした事務やレジ業務、短時間の清掃といったお仕事にも出会えます。「まずは週2日から」と気軽に始めて、自分のペースで調整できる働き方こそが、長く続けられるコツです。
※派遣
【質問4】40代から定年まで働ける女性の仕事はありますか?
もちろんあります。むしろ、40代は「もう遅い」どころか「今から始めるのにちょうどいい」タイミングです。
最近では、企業に70歳までの就業機会を用意するよう努力義務が課されていることもあり、年齢にとらわれない働き方がどんどん浸透しています(出典:高年齢者雇用安定法の改正)。
注目すべきは、介護や福祉系などの人手不足分野、そしてスキルがあれば年齢関係なく活躍できるIT系の職種です。登録販売者のような比較的取得しやすい資格や、バックオフィス業務、コールセンターなども選択肢に入るでしょう。学び直しを恐れず、今こそ自分の働き方を作っていくチャンスです。
【質問5】50代からでも一生できる女性の仕事は何ですか?
50代から始められて、しかもずっと続けられる仕事って、実は意外とあるんです。大事なのは、体の調子に合わせて無理せず働けるか、そして自分の経験や強みを活かせるか。
たとえば介護福祉士や登録販売者といった資格職は、職場のニーズも高く、スキルさえあれば年齢は大きなハードルになりません。さらに、地域のシルバー人材センターを通じて、清掃や事務補助などの軽作業に就く方も多くいます。「週3日、午前中だけ」といった働き方も可能なので、自分の生活にフィットする形でキャリアを継続することができます。
※派遣
【質問6】70歳まで働ける女性の仕事には何がありますか?
「まだ働きたい」「少しでも収入が欲しい」——そう思ったとき、70歳という年齢はもう“引退ライン”ではありません。
実際、企業には高年齢者の就業機会を70歳まで確保するよう働きかける制度があり、雇用の選択肢は以前よりずっと広がっています(出典:参考文献)。清掃や事務補助、レジ業務など、地域のシルバー人材センターを利用して見つかる仕事も多いです。
また、電話対応やコールセンターなどの「人と話すこと」が中心の業務も、長年の経験が活きるフィールドです。「少しだけ」「週に数日だけ」——そんな柔軟な働き方が、70代の働く意欲を支えています。
まとめ:女性が歳をとっても続けられる仕事の特徴と最適な仕事
女性が歳をとっても続けられる仕事の特徴と最適な仕事をまとめてきました。
改めて、女性が歳をとっても続けられる仕事10選をまとめると、
- 結婚相談所経営
- 介護福祉士・介護職
- 販売・接客スタッフ
- Webデザイナー
- ITエンジニア
- Webライター
- コールセンター
- 清掃スタッフ
- 家事代行スタッフ
- 図書館スタッフ・資料整理
そして、女性が歳をとっても続けられる仕事の5つのポイントもまとめると、
- 年齢や性別を問わず、働きやすい職場環境が整っている仕事を選ぶことが重要
- 体力的な負担が少なく、無理なく長く続けられる仕事内容が望ましい
- 時間や場所にとらわれず、自分のペースで働ける柔軟性のある職種が最適
- 安定した需要があり、景気に左右されにくい業界・仕事を選ぶことが安心に繋がる
- 人間力や経験が活かされ、AIや機械に置き換えられにくいスキルが関わる仕事が長続きしやすい
「女性が歳をとっても続けられる仕事」を選ぶには、自分のライフスタイルや体力、スキルに合った働き方を見極めることが大切です。
年齢を重ねても、自分らしく働ける選択肢は確実に存在します。長く続けられる仕事を見つけることで、心も生活も豊かになっていきます。