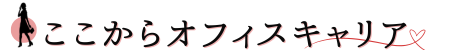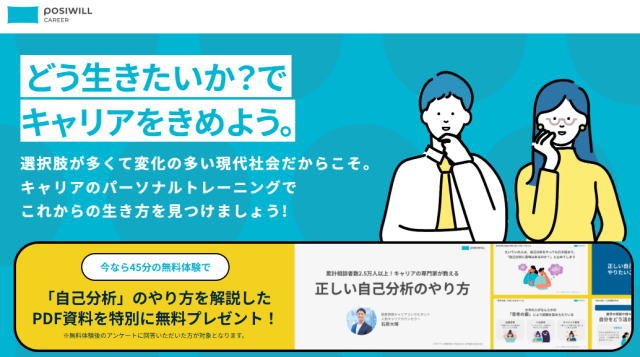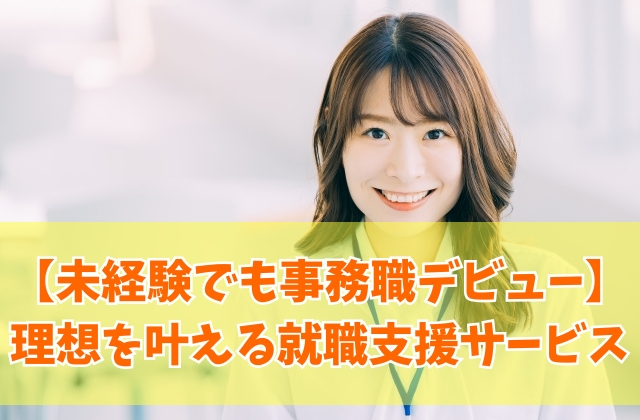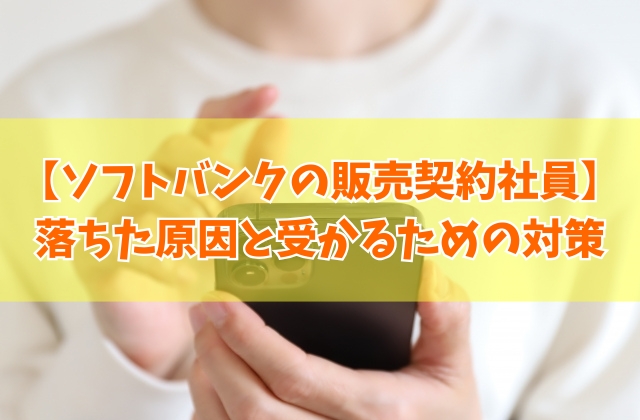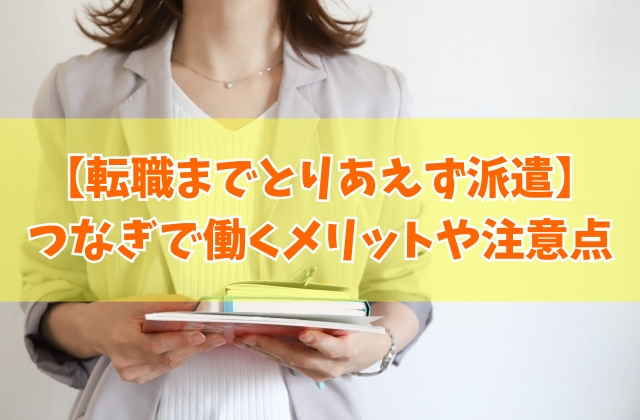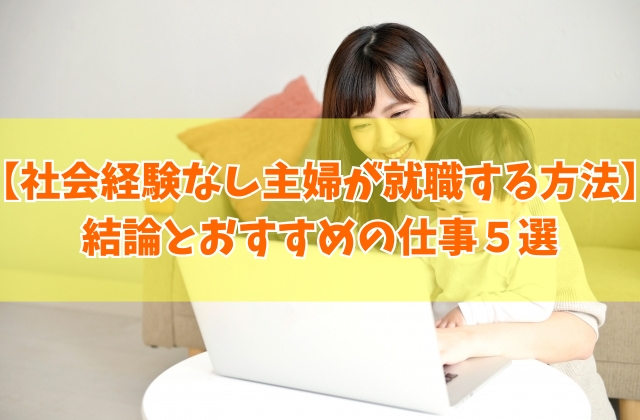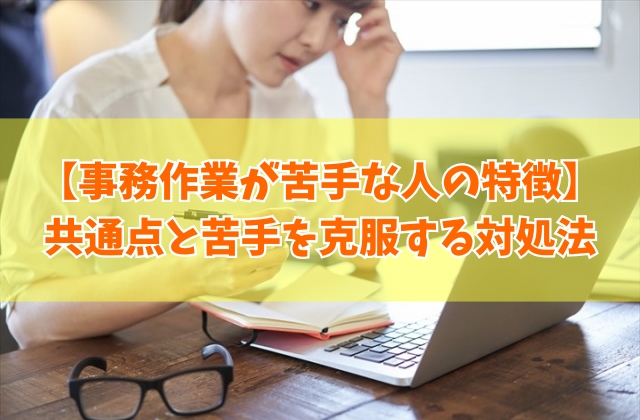
「事務作業が苦手な人の特徴は?」
「苦手を克服する対処法は?どんな仕事が私には向いてる?」
事務職に就いたものの、細かい作業やルーティンワークが苦痛に感じる日々。
パソコンに向かって数字を追い、書類のミスを気にしながら過ごす時間が増えると、「自分は事務作業が苦手なのかもしれない」と悩みを抱えてしまう人は少なくありません。
でも、それは決して珍しいことではありませんし、自分を責める必要もありません。
なぜなら、事務作業に苦手意識を持つのは、向き不向きがあるからこそ。
この記事では、事務作業が苦手と感じる原因や、自分に合った対処法、そして新しい選択肢を見つけるためのヒントをご紹介します。
- 事務作業が苦手と感じる理由は、単調さや集中力の維持が難しいことにある
- 自分の得意分野や特性をしっかり理解し、働き方を見直すことが重要
- 苦手を感じたら、対処法や転職も視野に入れ柔軟に行動することが大切
事務作業が苦手だと感じるのは、あなただけではありません。
自分に合わない作業に無理して取り組むより、得意を活かした働き方に目を向けることが、ストレス軽減と前向きなキャリアの一歩につながります。苦手意識を否定せず、今できる行動から変えてみましょう。
とはいえ、今後のキャリア形成は誰もが悩む重大イベント。実際に、あなたも悩んではいませんか?
「自分の強みや適性が分からず、どの方向に進むべきか迷っている」
「結婚や出産などのライフイベントとキャリアの両立に悩んでいる」
「現在の仕事にやりがいを感じられず、将来のキャリアに不安を抱えている」
人生には、地図のない分かれ道が何度も訪れます。誰かに相談したくても、身近な人には言いづらい。かといって、一人で考えても堂々巡り。。
そんなとき、キャリアのプロに頼るという選択肢があることを知っていますか?
その方法というのが、累計相談者数が35,000人を超える実績豊富な『ポジウィルキャリア』です。
『ポジウィルキャリア』は、あなた専属のトレーナーがマンツーマンで伴走し、自己理解・人生設計・意思決定まで一緒に考えてくれる“キャリアのパーソナルトレーニング”です。
- 質の高いキャリアカウンセリング:専属のトレーナーとマンツーマンでキャリア相談ができ、自己理解を深めるサポートを受けられます。
- 転職以外の選択肢も提案:転職を前提とせず、現職での働き方の改善や副業など、多様なキャリアパスについてアドバイスを受けられます。
- 自己理解を深める独自の診断とワーク:ポジウィル独自の診断やワークを通じて、無意識下の認知に気づき、新しい視点を定着させることができます。
心理学に基づいたプログラムと実績あるサポート体制で、あなたの「本音」を引き出し、理想のキャリアを現実に変えていきます。
初回は、45分の無料カウンセリングから。未来のあなたのために、まずは一歩踏み出してみませんか?
事務作業が苦手な人の特徴10選
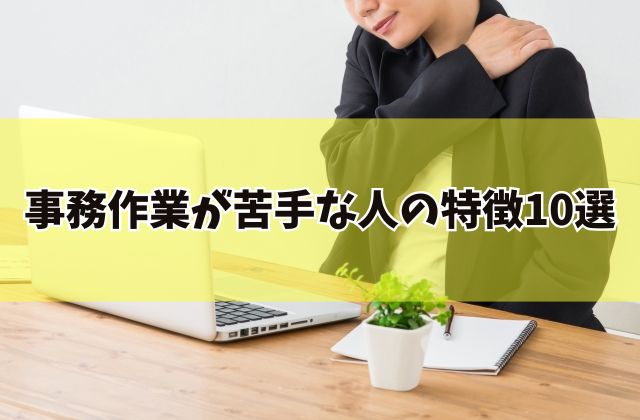
事務作業が苦手だと感じている人には、いくつか共通する特徴があります。
特に事務職やオフィスワークに就いている方にとっては、毎日の業務の中で「自分は向いていないのでは」と悩むこともあるでしょう。
この「事務作業が苦手な人の特徴10選」では、苦手意識の根本にある要因を具体的に整理しました。
パソコン作業が負担に感じる方や、細かなチェックがストレスになっている方にとって、自分自身の傾向を見つめ直すきっかけになります。
【特徴1】パソコン作業が苦手で手間を感じやすい人
パソコンに向かうたびに「どうしてこんなに時間がかかるのか」とモヤモヤしてしまう人は少なくありません。画面の動きが遅かったり、思い通りに操作できなかったりすると、作業がスムーズに進まずイライラが募ります。とくに、普段から事務作業に苦手意識がある方にとっては、この“ちょっとした遅れ”が集中力の妨げになりがちです。
実際、ある調査では、一度集中が途切れると元の状態に戻るまでに約23分かかるとも言われています。たった数秒のパソコンのもたつきでも、気持ちの面では大きな負担に感じるのです。さらに、新しいシステムや複雑な操作に直面したときには、知らないことへの不安から「やりたくない」「難しそう」と感じてしまい、手が止まってしまうこともあります。
たとえば、マウスのクリックが思うように反応しなかったり、どこを押せばいいのか分からずに時間だけが過ぎていく…そんな経験が積み重なると、自然と「私はパソコン作業に向いていないのかもしれない」と感じてしまうものです。
こうした負担を少しでも軽くするには、まずは作業環境を見直すことが大切です。パソコンの性能を整えることはもちろん、頻繁に使うツールに慣れておくことで、日々の事務作業に感じる“手間”は確実に減らせます。苦手を否定するのではなく、「どうすれば少し楽になるか」に目を向けることが、前向きな一歩につながります。
【特徴2】細かい確認作業や書類を扱うのが苦になる人
細かい書類を一枚ずつ確認したり、数字や文字の違いを見比べたりする作業。頭では「必要な仕事」と分かっていても、気が重くなる瞬間はありませんか? 特に几帳面すぎる性格の人ほど、「間違えてはいけない」というプレッシャーが強く、見落としがないか何度も見返してしまい、気づけば心も体もぐったりしていることがあります。
ある調査では、確認作業に対して約7割の人が「時間的な負担を感じる」と答えており、さらに6割以上が「心理的にも気を遣う」と答えています。たった一つの書類の確認であっても、その背後には“正確性”や“気遣い”が求められるため、思った以上に神経を使うのが実情です。
実際、社内資料で表記ゆれやミスを見つけたとき、「この程度で指摘すべきか?」と悩んだ経験がある人は多いはずです。相手の気分を考えて言い方を工夫したり、伝え方に気を遣ったりと、単なる確認にとどまらず“人間関係の気配り”まで求められる場面もあります。
だからこそ、「細かいことに気を取られて疲れてしまう」と感じる自分を責める必要はありません。苦手な作業には、それなりの理由があるからです。負担を感じているなら、チェックのやり方を見直したり、作業の分担やフローの簡略化を考えるなど、自分なりに“ラクにこなせる方法”を探してみることが大切です。
【特徴3】同じ作業の繰り返しに飽きやすい人
日々の事務作業で「またこの作業か…」とため息がこぼれる瞬間。決して珍しいことではありません。同じ操作、同じ確認、同じ入力。それが延々と続くと、どうしても心がすり減っていくのを感じます。やるべきことだと頭ではわかっていても、手が止まり、気持ちは宙ぶらりん。そんな自分に「集中力が足りないのかも」と落ち込んだ経験がある方もいるのではないでしょうか。
ある調査によれば、働く人の62%が「毎日こなしている業務の多くが繰り返しの作業」だと感じており、その中には“退屈”や“無力感”を抱える人も少なくないそうです。同じことの繰り返しが続くと、人は刺激を感じなくなり、モチベーションを維持するのが難しくなるものです。
たとえば、毎日決まった時刻に同じフォーマットに数値を入力する作業。やっている内容は簡単なのに、どうしてこんなに面倒に感じるのか…。実は「単純な作業だから楽」なのではなく、「単純だからこそ心が動かない」のです。人は新しい刺激や達成感がないと、どうしても気力を保ちにくくなります。
飽きを感じることは、決して怠けではありません。むしろ、それだけ感覚が繊細で、変化や工夫を求めている証です。同じ作業が続くときは、タスクの合間に小休憩をはさむ、順番を変える、環境を少し変えてみるなど、小さな変化をつくってみてください。気持ちが軽くなるだけでなく、仕事の質もきっと変わっていきます。
【特徴4】集中力が続かず作業をやり遂げづらい人
気づけば、やるべき作業が目の前にあるのに、心ここにあらず。始めるまでは重い腰を上げ、いざ始めてもすぐに通知音やちょっとした雑音に気を取られてしまう。気が散ったあとは、なかなか元に戻れず、集中し直すまでがひと苦労——そんな経験を繰り返していませんか?
ある研究調査によれば、知的労働者の多くは3分ごとにタスクが分断されており、一度集中が切れると、もとの作業に戻るまで平均で約25分もかかるといいます。一見、数秒の中断に見えても、頭の中ではその何倍ものロスが生まれているのです。
「集中力がない」と自分を責めがちな人ほど、まじめで責任感の強いタイプが多い気がします。でも実は、集中を維持する力よりも、集中を奪う環境のほうがずっと強力なんです。通知、話しかけられる気配、周囲の空気…。集中というのは、音もなく壊れる繊細なバランスの上に成り立っています。
まずは自分を責めるのをやめてみませんか?スマホの通知を切る、タスクの区切りに休憩を入れる、作業場所を変える。そんなささやかな対策でも、意外なほど集中しやすくなることがあります。「集中できない自分」ではなく、「集中しづらい環境」に目を向ける。そこに変化のヒントがあります。
【特徴5】注意が散りやすくミスしやすい人
ほんの少し目を離しただけなのに、気づけば入力ミス。集中していたはずなのに、どこかで抜け落ちる。そんな小さなミスを繰り返すと、「自分は向いてないのかも」と不安になってしまいます。でも実は、そう感じている人はあなただけではありません。
ある調査によると、知的労働者の多くは3分に一度タスクを中断しており、元の作業に戻るまでには約25分もかかることがあるそうです。集中を保つことそのものが、今の働く環境ではとても難しいという現実があります。
例えば、Excelで数字を入力していたとき、スマホに通知が入る。つい確認して戻ってみると、「さっきどこまでやったっけ?」と手が止まり、作業にムラが出てしまう。気づかないうちに、それがミスの原因になってしまうのです。
でも、それは注意力がないからではなく、注意力を削るものが多すぎるから。だからこそ、「集中できる仕組み」を自分の手で作ることが大切です。通知をオフにする、作業時間を区切る、机の上から気になるものを片づける。ほんの小さな調整でも、ミスの数は確実に変わっていきます。
【特徴6】物忘れや確認の抜けも気になり集中できない人
「さっきの資料、ちゃんと確認したっけ?」
そんなふうに頭の片隅にひっかかる違和感があると、今やっている作業にもなかなか集中できないものです。一度「気になる」が湧いてしまうと、その小さなモヤモヤに思考を引っ張られ、目の前のタスクに気持ちが乗らない。経験がある方も多いのではないでしょうか。
実はこの現象、心理学的にもよく知られています。「ツァイガルニク効果」と呼ばれるもので、完了していない作業や記憶ほど頭に残りやすく、注意を奪いやすいのです。つまり、確認漏れややり残しがあると、脳はそこに引き戻されてしまう。自然と集中力も奪われる構造になっているのです。
たとえば、確認したつもりの書類に「念のためもう一回見ておくか…」と繰り返し手を伸ばす。それでもどこかで「本当に大丈夫だったかな?」と気にしてしまい、ほかの仕事が止まってしまう。これでは、仕事が進まないのも無理はありません。
こうした状態を「自分の注意力が足りないせいだ」と感じてしまう方も多いのですが、本質はそこではありません。脳が“終わっていない”と認識している限り、自然と意識はそこに引き戻されるのです。
だからこそ必要なのは、「終わった」と自分に示す仕組みをつくること。たとえば、タスクを小さく区切って一つ終えるたびにチェックマークをつける、確認リストを目に見える場所に置くなど、シンプルでも効果は十分です。目で確認できる“完了”のサインが、意識を次に進める助けになります。
【特徴7】優先順位をつける判断がしづらい人
「どれから手をつければいいか分からない」
忙しさの中でふと立ち止まった瞬間、そんな気持ちに襲われることはありませんか? やらなければいけないことは山ほどあるのに、考えれば考えるほど頭が混乱して、結局どれも手がつかない。そんな状態に陥るのは、あなただけではありません。
実際、ある調査によると、98.2%の人が「優先順位の整理が難しい」と感じており、うち75%以上が「かなり苦手」と回答しているというデータもあります。つまり、ほとんどの人が“やることが多すぎて選べない”という状況に悩まされているのです。
たとえば、朝からメールが溜まっていて、同時に資料の提出期限も迫っている。上司には報告もしなければならず、その横でチャットの通知が止まらない。そうやって複数のタスクに囲まれると、頭の中はどんどん飽和していきます。結局どれも中途半端にしか手をつけられず、後味の悪い1日が過ぎていく──そんな日、誰にでもあるはずです。
だからこそ大切なのは、「まずは目の前にあることを、ひとつずつ整理する」こと。難しい分析はいりません。メモ帳に「今日やるべきこと」をざっくり書き出して、そこから重要な2~3個を選ぶ。たったそれだけでも、思考の渋滞が解けて、スッと行動に移せるようになります。
優先順位をつけるのが苦手なのは、能力の問題ではありません。頭の中だけで情報を整理しようとするから、こんがらがるだけなのです。「見えるようにする」「減らす」「並べる」。この3つの小さな整理だけで、日々の事務作業はぐっと楽になります。
【特徴8】マルチタスクが苦手で一つに集中したい人
「あれもこれも手をつけた結果、どれも中途半端になってしまった」——こんな後悔を抱えて帰宅した日、ありませんか?事務作業では複数のタスクが同時に舞い込む場面も多く、マルチタスクが得意でない人にとってはなかなか手強い状況です。
実際、心理学会の調査では、切り替え作業には「スイッチングコスト」がつきまとい、「人間の脳は一度に複数の作業を処理するようにはできていない」という研究結果が報告されています。特に注意力や判断力が問われる作業では、タスクを切り替えるたびに作業効率が最大40%も低下するという指摘もあるほどです(出典:PMC)。
もし「どうして自分だけがうまく回せないんだろう」と落ち込んでいたなら、それは能力のせいではありません。むしろ、ひとつひとつに集中するタイプの人のほうが、丁寧で質の高い成果を出せる傾向にあります。
だからこそ、作業の前に「やることリスト」を1本の道筋に並べるように書き出してみてください。必要ならアラームやタイマーで時間を区切って、“集中する枠”を自分でつくる工夫も有効です。頭の中の混雑をほどくように、タスクを整理していけば、自然と自信も戻ってくるはずです。
【特徴9】じっと座って同じ姿勢を続けるのが苦しい人
長時間のデスクワークが続くと、次第に背中が張ってきたり、腰にじんわりとした疲れを感じたりしてきませんか?「ただ座っているだけなのに、なんだか体がしんどい」——そう感じたことがあるなら、それはあなたの体がしっかりと反応している証拠です。
実際、座りっぱなしの生活が健康に及ぼす影響は小さくありません。世界保健機関(WHO)の調査では、長時間座り続ける習慣が死亡リスクを高めることが明らかになっています。中でも、55分以上座り続ける状態が長く続くと、心疾患や糖尿病のリスクが増すという報告もあるほどです。
ただ、「自分は体力がないからだ」と思い込む必要はありません。人間の体はもともと“動く”ことを前提にできているため、同じ姿勢を保ち続けること自体が負担になるのです。
だからこそ、日常の中に少しだけ“動き”を取り入れる工夫が大切になります。例えば、「30分に1度は立ち上がって伸びをする」「背もたれに頼らず姿勢を整える」「座面に浅く腰かけて骨盤を立てる」など、無理のない範囲で体を動かすだけでも違いが生まれます。
「座るのがつらい」と感じるのは、決して甘えではなく、体からの正直なサイン。無視せず、ほんの少し意識を変えるだけで、日々の事務作業がずいぶん楽になります。
【特徴10】黙々と人と話さず作業するのが苦手な人
静まり返ったオフィスで、一人きりのパソコン作業。何時間も無言で同じデスクに座っていると、ふと「誰かと少し話したいな」と感じることはありませんか?事務作業ではこうした“無言時間”が当たり前のように続くため、人と関わることでエネルギーを得るタイプの人にとっては、精神的にしんどくなる場面もあるでしょう。
実際、ある調査企業の調査結果によれば、人と一緒に働くことで生産性が最大50%向上するというデータもあります。人間関係や会話を通じてモチベーションが保たれる人にとって、黙々と作業に没頭する環境は相性が悪いのです。
とはいえ、事務職すべてが“無口な仕事”というわけではありません。チームで進める業務や、こまめな報告・相談が求められる職場を選べば、自分に合った働き方は見つけられます。
人と関わる時間がないと息が詰まりそうになる…そんなタイプの方は、「静かな環境だから集中できる」ではなく、「誰かの存在があるからこそ頑張れる」という、自分の特性を受け入れて働き方を調整してみてください。
なぜ「事務作業は苦手」と感じるのか?きつい原因
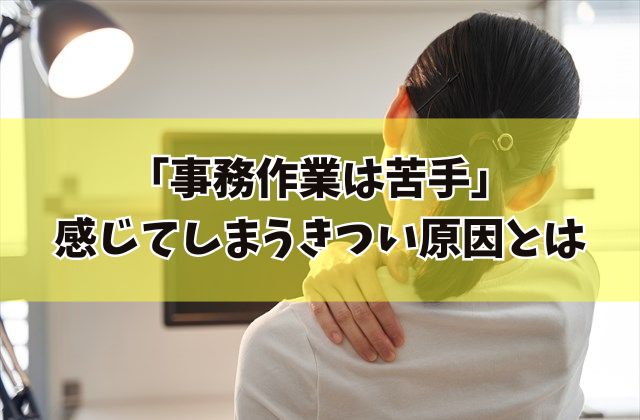
「なぜ自分は事務作業がこんなに苦手なんだろう」と感じている方は少なくありません。
単調な入力や確認作業が続いたり、電話対応やマルチタスクに追われる環境に疲れてしまったりと、さまざまな要因が重なって「きつい」と感じやすくなります。
ここでは、事務作業が苦手と感じる根本的な理由や背景に注目し、自分に合わないと感じるポイントを明確にするためのヒントを紹介します。
どんな場面でストレスを感じるのかを知ることが、今後の対処や働き方の見直しにもつながります。
【原因1】落ち着かず気が散りやすく集中力が続かない
「気が散って、いつの間にか作業が進んでいない」。事務仕事に取り組むなかで、こんなモヤモヤを感じたことはないでしょうか。実際、集中が続かず業務効率が落ちることに悩む人は多く、Economist Impactの2023年調査でも、ナレッジワーカーは通知や中断によって年間500時間以上の作業時間を失っているという結果が出ています。
SNSの通知、社内チャット、誰かの声。ちょっとしたきっかけで意識がそれてしまい、「さっきまで何してたんだっけ?」と頭が真っ白になる——そんな経験が積み重なると、自己嫌悪や「事務作業が向いてないかも…」という気持ちにつながるのも無理はありません。
とはいえ、こうした注意の分散は“本人の意志の弱さ”ではなく、誰もが陥る環境要因であることが多いのです。集中力の問題を「自分のせい」と抱え込まず、まずは通知をオフにしたり、作業の区切りに短い休憩を挟んだり、できるところから環境を整えることが、苦手意識を少しずつ軽くする第一歩です。
【原因2】毎日同じ単調な作業でやる気が出ない
「今日もまた、同じ作業の繰り返しか」——そんなため息が、ついこぼれてしまう日があるかもしれません。事務作業の多くはルーティンで、慣れれば効率は上がるけれど、そのぶん刺激や達成感が薄くなりがちです。
実際に、日本の働き手の約4人に1人が「仕事にやる気が出ない」と感じており、その理由のひとつが「変化のなさ」「単調さ」にあると報告されています(出典:Gallup公式リリース)。つまり、「やる気が出ない」のはあなただけではありません。それは“心がサインを出している”とも言えるのです。
たとえば、伝票入力、請求書のチェック、メール整理。どれも重要だけれど、クリエイティブな刺激は少なく、毎日似たような流れに飲み込まれていくような感覚に陥ることがあります。結果、仕事に身が入らなくなり、集中力も低下してしまいます。
だからこそ、ほんの小さな“変化”を意識してみてください。朝のデスク周りを少し変えてみる、タイマーを使って自分とちょっとしたゲーム感覚で向き合ってみる。あるいは「10件終わったらコーヒータイム」とご褒美をセットするのもおすすめです。
単調な日々に、ほんの少し“遊び心”や“変化”を持ち込むこと。それが、事務作業の苦手意識を和らげ、やる気を再点火する第一歩になります。
【原因3】マルチタスクの対応が苦手で混乱しやすい
あれもこれも一度に求められると、どこから手をつけていいかわからなくなる。気づけば頭の中がごちゃついて、仕事が止まってしまう。そんな状況に心当たりはありませんか?実際、事務職の現場では「複数の業務を並行して処理するのがきつい」と感じている人が少なくありません。
東京大学の研究(科研費プロジェクト21K18450)では、マルチタスクを続けることが心身の負荷につながる可能性が示されており、「効率的なはずが逆に疲弊する」という実態が見え隠れしています。
たとえば、電話応対の合間にExcel作業を進めているうちに、上司からチャットが飛んでくる。頭がその都度切り替わるだけでなく、作業の進行も中断され、自分でも何をしていたのかわからなくなる瞬間が出てきます。そうなると小さなミスも起きやすくなり、自己嫌悪に陥ることも。
「マルチタスクが苦手=劣っている」ではありません。むしろ、“ひとつずつ丁寧にやる力”がある証拠です。通知を切り、時間ごとにタスクを区切るなど、自分のリズムを作る工夫を取り入れてみましょう。環境さえ整えば、驚くほどスムーズに集中できるようになります。
【原因4】電話や対人対応がストレスで後回しにしがち
たとえば、事務作業に集中している最中、突然電話が鳴る。そんなとき、心臓がトンと跳ねるような感覚に襲われる人は少なくありません。「今は無理…」と頭の中でつぶやきながら、受話器に手が伸びない。結局、何度も鳴るコール音がプレッシャーになり、電話応対を後回しにしてしまう——これ、珍しいことではないのです。
実際、株式会社うるるが行ったアンケート調査によると、電話応対にストレスを感じている人は全体の75.5%にのぼり、その理由の1位は「作業が中断されるから」(42.9%)というものでした。つまり、集中していた時間を断ち切られることが、心の負荷になっているというわけです。
「また聞き間違えたらどうしよう」「言葉が詰まったらどうしよう」——そんな不安が重なると、電話はただの業務連絡ではなく、ストレスの引き金になります。
けれど、これは性格の問題ではありません。むしろ、慎重さや丁寧さの裏返しとも言えます。もし可能なら、電話対応の時間帯を明確に分ける、あるいはテンプレートを用意しておくと、少しずつ不安は薄れていきます。ほんの小さな仕組みでも、日々の気持ちはずいぶんと変わるものです。
【原因5】細かいミスが多く自信を失いやすい
「またやってしまった…」そんな思いで、何度も自分を責めてしまう——事務作業をしていると、つい細かいミスが気になってしまう方も多いのではないでしょうか。
実際、全国499人を対象にした調査によると、81.8%もの人が「仕事のミスで自己嫌悪を感じた経験がある」と答えています。これはつまり、「ミス=自分の能力不足」と結びつけてしまい、落ち込む人がそれだけ多いということです。
特に事務職は、ミスが表に出やすく、そのたびに「自分は向いていないんじゃないか」と不安が募りやすい環境です。ある調査でも、「自信を失った理由」として“仕事でミスが続いたから”という回答が上位に挙がっていました。
ただ、その事実は「あなたがダメな人間だから」ではありません。正確さが求められる仕事に一生懸命取り組んでいるからこそ、失敗が心に刺さるのです。
大切なのは、“ミスしない完璧な人”を目指すのではなく、ミスした自分を受け入れること。たとえば、「同じ失敗を防ぐ工夫をメモしておく」「気がついた時点ですぐに修正する」など、小さな積み重ねが“自信の回復”に繋がります。
自信を失うことがあっても、少しずつ前を向ければ、それは立派な前進です。
苦手な事務作業を克服する最適な5つの対処法
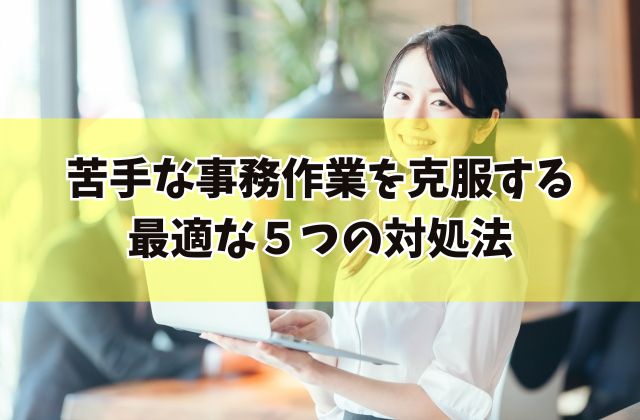
事務作業に対して「向いていない」「どうしても苦手」と感じてしまうのは、実は特別なことではありません。
多くの人が、確認ミスや集中力の低下、作業効率の悪さなどに悩み、自己否定につながっています。
しかし、苦手意識の根底にある原因を整理し、少しの工夫を取り入れるだけでも、日々の業務がぐっとラクになります。
この「苦手な事務作業を克服する最適な5つの対処法」では、具体的かつ今日から実践できるテクニックを紹介していきます。
【対処法1】チェックリストを自作して作業手順を整理する
「作業の途中で、あれ?何か抜けてたかも…」と不安になった経験はないでしょうか。事務作業が苦手な人ほど、こうした“小さな見落とし”に神経をすり減らしがちです。対策としておすすめなのが、自分専用のチェックリストをつくることです。
リストに沿って進めるだけで、確認漏れやうっかりミスが格段に減ります。実際、企業の業務効率化を支援するマネーフォワード社のコラムでも、チェックリストの活用によって業務ミスを防ぎ、作業の標準化が進むことが紹介されています。
しかも、自作なら“自分のクセ”まで織り込めます。「この資料は最後にダブルチェック」「先に封筒を並べておく」など、マニュアルでは拾いきれない細部も盛り込めて、結果的に仕事への安心感が増すのです。
いきなり完璧を目指さなくて構いません。まずは「作業をしながら、気づいたタイミングでメモを残す」くらいのゆるさで大丈夫です。1週間後には、あなただけの“ミスしない地図”ができているはずです。
【対処法2】机の上に必要なものだけ置いて集中力を高める
デスクの上に余計なモノがあると、意外と集中力を奪われるものです。資料の山や使っていない文房具、読みかけの書類…。目に入るたび「後でやらなきゃ」「あれ、これ何のメモだっけ?」と、気づかないうちに注意がそがれてしまいます。
実際、東京大学の池谷裕二教授によると、視界に情報が多すぎると脳のワーキングメモリが圧迫され、思考力や集中力が落ちると指摘されています(出典:参考文献)。つまり、机の上を整えることは、脳のスペースを空けることと同じです。
とはいえ、ただ“何もない机”にすればいいかというと、そうでもありません。自分にとって「必要なもの」と「あると落ち着くもの」は違います。例えば、毎日使うノートや、作業中に目を通すマニュアル、あるいは小さな観葉植物。これらは、逆に集中力を高めてくれる“心の拠りどころ”になることもあります。
大切なのは、自分にとって本当に必要なモノだけを残すこと。片づけるのが目的ではなく、「集中しやすい環境」を作ることがゴールです。試しに一度、机の上のモノをすべてどかして、よく使うものだけに厳選してみてください。静かに集中できる時間が、驚くほど増えるはずです。
【対処法3】まとまった時間で一気に処理して効率を上げる
事務作業が苦手だと感じる人の多くに共通するのが、「細かく中断されることで集中が切れてしまう」悩みです。たとえば、メールを見て、電話を取り、また書類作成に戻る…といった具合に、あれこれ切り替えながら作業していると、頭のスイッチがうまく入らず、いつまで経っても仕事が進まないと感じた経験があるかもしれません。
このような状況を改善する方法として効果的なのが、「バッチ処理」と呼ばれる作業スタイルです。似た内容の作業を一つにまとめて、まとまった時間で一気に取り組むやり方で、実際に多くのビジネスパーソンの間でも取り入れられています。特に事務業務では、メール対応を午前と午後の決まった時間にまとめたり、入力作業を1時間ブロックで集中して行ったりすることで、作業効率が大きく変わってきます。
実際、東日本電信電話の業務効率化に関する解説でも、集中を妨げない環境を意識的につくることが、パフォーマンスを安定させるコツとして紹介されています(出典:事務作業を効率化するポイント)。
まずは30分でも構いません。「この時間は他のことは考えない」と決めて、単一のタスクに向き合ってみてください。集中できたという実感が得られると、作業そのものに対する自信も自然と生まれてくるはずです。
【対処法4】わからないことはすぐ質問してミスを未然に防ぐ
事務仕事に携わっていると、ちょっとした疑問にぶつかる場面は日常茶飯事です。「この書類の出し方、あってるかな…」「前回もこうだったっけ?」と迷いながらも、「忙しそうだし、あとでいいか」と質問を後回しにしてしまう——そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。
けれど、その“あとで”が意外と落とし穴。NRIセキュアテクノロジーズの調査によると、問題が発生した際に“できるだけ早く相談すべき”と考える人は97%もいるのに、実際に30分以内に報告できている人はわずか65%にとどまっている調査結果も出ているほど。つまり、多くの人が「聞いたほうがいい」と頭では分かっていながら、行動に移せていないのです。
質問することは決して恥ずかしいことではありません。それどころか、「早めに確認してくれて助かった」と感謝されるケースも少なくありません。とくに事務作業のようにミスが表に出にくく、気づかれにくい業務では、疑問を放置することが大きな損失につながることもあります。
迷ったら、勇気を出して「ここだけちょっと確認したいんですけど」と一言添えてみてください。あなたのその行動が、チーム全体のミス防止につながり、自分自身の安心にもつながります。
【対処法5】自分の得意分野を活かして苦手をカバーする
「どうしても事務作業が苦手で…」と落ち込む必要はありません。誰にでも得手・不得手はありますし、それをうまく組み合わせて補えば、毎日の業務はぐっと楽になります。
たとえば、「数字のチェックは苦痛だけど、人に説明するのは得意」という人であれば、資料作成よりもプレゼンや確認係にまわる工夫ができます。実際、NTTデータ関西では、作業の一部を自動化しつつ、人が得意な部分に集中できる体制に変えたことで、働きがいが大きく向上したという報告が出ています。
得意なことは、小さくても武器になります。メール文の言い回し、ミーティングでの伝え方、整理整頓のクセ——何気ない得意ポイントでも、職場の中では重宝されることが意外と多いのです。
苦手を克服するのではなく、「得意を軸にする」。そんな視点で日々を見直してみると、事務仕事に対する気持ちにも少し余裕が出てきますよ。
事務作業が苦手な女性向け!デスクワーク以外の仕事5選

事務作業が苦手と感じている方の中には、「毎日パソコンの前に座る仕事より、自分に向いている仕事があるのでは?」と感じている人も多いかもしれません。
デスクワークが合わないからといって、仕事全体が向いていないわけではありません。
実際に、動きが多かったり、人との会話が中心になったりする仕事で本来の力を発揮する方もいます。
そこでここでは、事務作業が苦手な女性向け!デスクワーク以外の仕事5選を紹介していきます。
自分の性格や得意分野に合った働き方を見つけるヒントになれば幸いです。
【働き方1】営業職(対面で話す機会が多く動きのある仕事)
事務作業がどうしても合わないと感じているなら、じっと座ってPCに向かう時間そのものがストレスになっているのかもしれません。そんな方に選択肢として考えてほしいのが「営業職」です。
営業というと“押し売り”のようなイメージを持つ方もいますが、実際には「話を聞くこと」が中心の仕事です。お客さまと対面で会話しながら、その人に合った提案を考える——そのプロセスに魅力を感じる人も多いです。
Indeedが紹介するキャリアガイドでも、営業職の特徴として「外出が多く、同じ空間に留まり続ける必要がない」「顧客との信頼関係がやりがいにつながる」といった点が挙げられています。
「座って黙々と」という働き方がどうにも苦手で、体を動かすほうが気持ちも前向きになる——そんなタイプの方には、営業職のように動きのある仕事のほうが、無理なく続けやすいかもしれません。業界によっては未経験からスタートできる求人もあり、「事務作業 苦手」から抜け出す一歩として現実的な選択肢です。
そして、営業職への転職を目指すなら転職エージェントを活用してみてください。
転職エージェントは求人の紹介だけでなく、キャリアの棚卸しや応募書類の添削、面接対策までしっかりサポートしてくれます。
そこで今回は、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
【働き方2】接客業(レストランやホテルで人と接する仕事)
「人と話すのは好きだけど、パソコンの前にずっと座ってるのは正直つらい」──そんなふうに感じたことがあるなら、接客業という働き方を検討してみても損はありません。
レストランやホテルの接客では、お客様の反応をその場で感じ取れるという魅力があります。「ありがとう」「美味しかったよ」と言ってもらえる瞬間は、事務作業では味わえないやりがいに直結します。たとえば、ホテル業界では接客を通じて顧客満足度を高める取り組みが評価され、キャリアアップにつながることもあります。
また、接客業は比較的未経験からでもスタートしやすく、研修制度が整っている職場も多いです。実際にハローワークや転職サイトでは「未経験歓迎」「研修充実」といった求人も多数掲載されています。
動きのある仕事や、人と直接関わる場面で力を発揮したい方にとって、接客業は単なる選択肢以上の“転機”になる可能性を秘めています。
※
【働き方3】販売職(店舗で接客しながら体を動かす仕事)
もし、パソコンの前で一日中座っているのがつらいと感じるなら、販売職のように体を動かしながら働ける仕事を検討してみてはいかがでしょうか。立ち仕事ではありますが、動きのある日常の中で、人とのやりとりが自然とモチベーションになります。
たとえばアパレルや食品スーパー、雑貨店など、接客をしながらお客様の反応を間近で見られる環境では、「ありがとう」の一言や笑顔にやりがいを感じることが多く、作業に飽きる暇もありません。実際、事務職から転職してきた人の中には「気持ちの切り替えがしやすくなった」「ずっと座っているよりも体もラク」と話す人もいます。
もちろん、立ちっぱなしや品出しなど体力が必要な場面もありますが、それ以上に動きと人との関わりがあることで、仕事のメリハリや達成感を味わえるのが販売職の特長です。事務作業が苦手なら、こうした“動きながら働く”という選択が、自分らしい働き方への第一歩になるかもしれません。
※
【働き方4】介護職(人と関わりながらの身体を使うケアの仕事)
ずっとデスクに座って黙々と作業をこなすのが苦手なら、介護職という選択肢を一度見てみてください。身体を動かしながら、誰かの役に立っている実感を得られる仕事。事務作業のような“静かな作業”に息が詰まってしまう人にとって、気持ちの抜けどころが見つけやすい職種です。
実際、介護の現場では利用者の笑顔や「ありがとう」という言葉が、ダイレクトに心に届きます。公益社団法人全国介護福祉士会の調査では、介護福祉士の7割以上が「利用者の生活の質が向上したとき」「笑顔を見たとき」にやりがいを感じたと答える結果も出ているほど。
加えて、介護職は今後も需要が高まる分野。実際に働いている人のうち、約38%が「将来性があるから」という理由でこの職を選んでいます。人と関わりながら、自分の体も動かして働ける。そうした仕事に、今のモヤモヤから抜け出すヒントが隠れているかもしれません。
【働き方5】清掃スタッフ(自分のペースで体を使って働ける)
「事務仕事ってなんだか気が重い…」と感じる方にとって、清掃スタッフという働き方は一つの選択肢になります。なぜなら、人と会話をする機会が少なく、自分のリズムでコツコツ進められるからです。体を使って働くため、じっと座っているのが苦手な人には特に向いています。
実際、タウンワークなどの求人サイトでも「一人で黙々と作業できる」「自分のペースで働けて快適」といった声が多く見受けられます。しかも、掃除のスキルが自然と身につき、成果が目に見えるため、達成感も得やすい仕事です。
事務作業でミスを指摘されるたびに自信をなくしていた方も、清掃の現場では「感謝される機会が増えた」と感じることもあるようです。自分の力で空間を整え、誰かの快適な時間をつくる——そんな仕事にやりがいを見つける人も少なくありません。
事務作業の研修制度が充実したおすすめ求人サイト3選
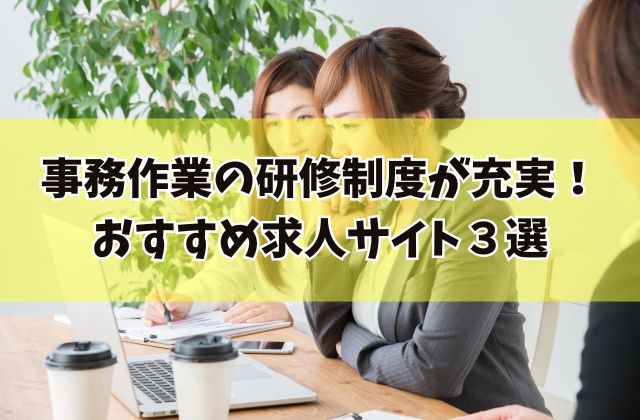
事務作業が苦手と感じている方にとって、丁寧なサポートや学び直しの環境が整っている職場を見つけることはとても大切です。
特に未経験から事務職に挑戦したい方や、ブランクがある方にとって「事務作業の研修制度が充実したおすすめ求人サイト3選」は、仕事選びの第一歩になる情報です。
ここでは、研修制度やフォロー体制が整っていて、初心者にも優しい求人を紹介している信頼性の高いサイトを厳選して紹介します。
【おすすめ1】マイナビキャリレーション
「未経験だから事務職は無理かな…」そんな不安を抱えている方にまず紹介したいのが、『マイナビキャリレーション』です。なぜなら、ここは“未経験歓迎”をうたっているだけでなく、実際に配属前の研修がとにかく手厚いから。電話応対やExcelの基本操作など、実務に直結する内容を、基礎からじっくり教えてくれます。
それに加えて、最大の安心材料は“無期雇用派遣”という働き方です。契約満了のたびに職を探すストレスがなく、正社員と同じように安定した環境でスキルアップできるのが特徴です。これは「事務作業が苦手」と感じている人にとって、実はとても大きな支えになります。
研修制度も働き方も、「不安を減らしながら事務の仕事を続けていきたい」と考える人にはぴったりの選択肢です。事務作業が苦手でも、“できる自分”へ踏み出す後押しが、ここにはしっかり揃っています。
【おすすめ2】ランスタッド
「毎日パソコンの前で細かい作業をするのは本当にしんどい…」そんな悩みを抱える方に、『ランスタッド』の事務求人は一度見てほしい存在です。なぜかというと、未経験者を受け入れる体制が非常に整っているからです。
たとえば、同社が紹介する求人の多くには、リモート研修やOJTがしっかり含まれています。中には「正社員登用率98%」「完全週休二日・年休120日以上」といった働きやすさが魅力の案件もあります。現場の声を反映したサポート体制が整っており、研修内容は基礎から丁寧に段階を踏んで学べる設計です。
つまり、「事務作業に自信がないから不安…」という方でも、安心してスタートできる道が用意されているのがランスタッドの強み。新しい職場で自分らしく働きたいと願う人にとって、頼もしい選択肢のひとつと言えます。
【おすすめ3】テンプスタッフ
「事務作業が苦手。でももう少し自信をつけたい」——そんな方にぜひチェックしてほしいのが、『テンプスタッフ』です。実はこのサービス、未経験からでも安心して働けるサポート体制がとても充実していることで知られています。
まず、扱っている求人の幅が広く、事務だけでなく接客や販売、軽作業など“動きのある職種”も見つけやすいのが特徴です。特に注目したいのが、無料で受講できるeラーニングやOA研修。パソコン操作に不安がある人も、ExcelやWordの基礎を段階的に学べるので、「苦手意識が薄れた」という声も少なくありません。
また、テンプスタッフでは『ファンタブル』という独自の研修制度も提供されており、ビジネスマナーやコミュニケーションまで実践的に学べます。だからこそ、事務職が未経験の方でも「なんとかなるかも」と思える環境が整っているのです。
「苦手だから無理」ではなく、「苦手だからこそ学べる」。そのスタンスを支えてくれるのがテンプスタッフだと感じます。
事務作業が苦手で向いてないから辞めたいときの解決策
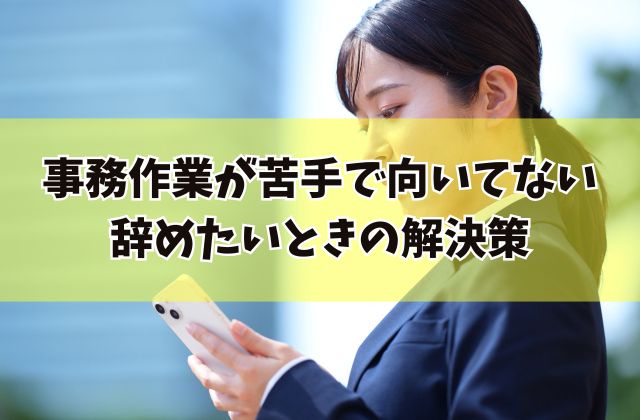
毎日の業務がつらく、「自分は事務作業に向いていないのでは?」と感じている方へ。
実際、細かな作業や同じ姿勢の継続が苦手だと、事務職が大きなストレスになることもあります。
「事務作業が苦手で向いてないから辞めたいときの解決策」は、無理に我慢するのではなく、自分の得意や向いている仕事を見つけるきっかけになります。
ここからは、現状を見つめ直し前向きに進むための具体的な方法を紹介していきます。
【解決策1】まずは自分の強みと苦手を自己分析する
「もう限界かも」「向いてないのかな」と感じるとき、いきなり退職や転職に走るのは不安がつきものです。でも焦らなくて大丈夫。最初にやるべきことは、自分の「得意」と「苦手」を見つけること。つまり、自分の棚卸し(自己分析)です。
実は、苦手な作業にずっと向き合っていると、自分の良さや武器まで見えなくなってしまうことがあります。例えば、人と接するのが得意だったり、スケジュール管理が好きだったり、そんな一面を見逃していることも少なくありません。
最近では、無料で使える自己分析ツールや適職診断サイトも豊富にあります。実際に、大学や行政機関でも「自己理解から始めるキャリア設計」が推奨されており、厚生労働省の職業適性診断や、リクナビのグッドポイント診断などは利用者も多く、参考にしやすいです。
自分の特性を冷静に整理するだけでも、「なぜ事務作業が苦手なのか」がクリアになってきます。原因が分かれば、無理に直すのではなく、得意なやり方でカバーする方法も見つかります。少し肩の力を抜いて、自分とちゃんと向き合う時間をつくってみてください。「苦手」は、伸びしろのヒントでもあります。
とはいえ、自分一人で自己分析を進めるのは簡単ではありません。何から手をつければ良いのか分からず時間だけが過ぎたり、「これが自分の強みかも」と思っても確信が持てず、不安が募るばかり…。
ですが、そんな行き詰った時に役立つのが、20~30代のキャリア相談で受講者数No.1の実績を持つ『ポジウィルキャリア』です。
ポジウィルキャリアは、マンツーマンのキャリアパーソナルトレーニングを通じて、自己分析の進め方を具体的かつ実践的にサポートするサービスです。
特に、無料体験のオンラインカウンセリングがおすすめです。専門家との対話を通じて、自分一人では気づけなかった新たな可能性が見えてくるでしょう。
「一人では難しい」「行き詰まってしまった」という方にとっても、ポジウィルキャリアは自己分析の行き詰まりを打破する心強い味方です。
【解決策2】転職活動を始めて自分の市場価値を知る
「もう事務の仕事、向いてないのかもしれない…」と悩んでいるなら、一度立ち止まって“いまの自分が市場でどれだけ必要とされているのか”を見つめ直してみてはいかがでしょうか。
自己分析や転職活動は、今後の道を探るうえで有効なヒントになります。というのも、企業が人材を採用するときには「この人にいくら払って、どんな貢献を期待できるか」を見ています。つまり、自分の経験やスキルが、どの業界・職種でどんな価値を持つのかを知ることが、キャリアの方向性を決める手がかりになるのです。
たとえば、『アデコ』や『リクルートエージェント』といった転職サイトでは、レジュメを登録するだけで企業やエージェントからスカウトが届く仕組みがあります。実際にスカウトの内容を見れば、自分の強みがどこで求められているのかが明確になります。加えて、類似職種の求人情報や年収相場をチェックするだけでも、思っていた以上に評価されている分野が見つかることも少なくありません。
「自分には何もない」と感じている人ほど、他者からの視点を取り入れることが重要です。行動を起こせば、自信を持つきっかけにもなりますし、今の職場で悩み続けるよりも前向きな一歩につながるはずです。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
【解決策3】求人サイトや転職登録で視野を広げてみる
事務作業に苦手意識を持つと、「自分に合う仕事なんてあるのかな」と不安になることもあると思います。でも実際には、少し視点を変えるだけで選択肢は広がります。その第一歩として有効なのが、求人サイトや転職サービスを使ってみることです。
たとえば、大手の求人サイトでは、自分の希望条件を登録しておけば、該当する求人がメールで届きます。業界未経験OKの案件や、研修制度が整った職場、あるいは「人と接する機会が多い仕事」など、自分が得意そうな働き方に出会える可能性もあります。
また、転職エージェントに登録すれば、履歴書の添削や面接のアドバイスまで無料で受けられることも多く、自信のない人には心強いサポートです。自分では見つけられなかった非公開求人を紹介してもらえることもあるので、視野が一気に広がります。
今の仕事が合わないと感じたときこそ、外の世界に目を向けてみてください。ほんの少しの行動で、可能性の扉が静かに開くかもしれません。
そして、数ある転職エージェントの中でも、特にサポートに定評のある3社を厳選して紹介します。
いずれも相談しやすく、あなたの価値観に寄り添った提案をしてくれる、心強いエージェントです。
✅【無料】相談しやすい&実績豊富!転職エージェントおすすめ3選
- あなたの価値観を最優先に考える転職支援『アデコ』|人材業界実績40年!「とりあえず話を聞いてもらいたい」「平日夜の転職相談」も可能!応募書類の準備~面接対策まで専任コンサルタントがサポート。
- 約8万人の20代が利用中『第二新卒エージェントneo』|1人あたり平均10時間の手厚いサポート!幅広い求人の紹介だけでなく、面談対策や入社後もサポートが受けられる安心の20代向け転職支援サービス。
- 転職支援実績NO.1『リクルートエージェント』|業界最大級の非公開求人数!各業界・各業種に精通した実績豊富なキャリアアドバイザーが揃い、あなたに寄り添う充実した転職サポートを提供。
【Q&A】事務作業が苦手だと感じたときのよくある質問
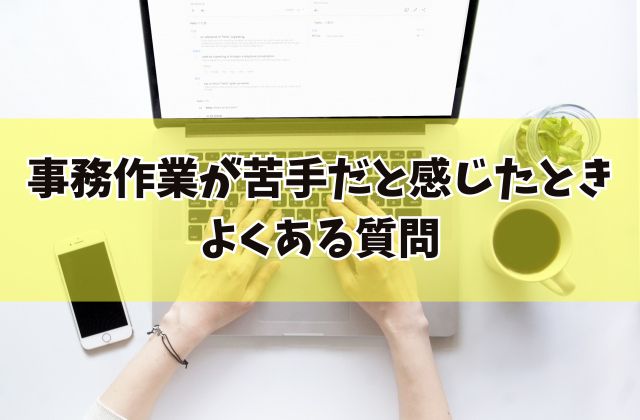
最後に事務作業が苦手だと感じたときのよくある質問をまとめました。
「ADHD」や「HSP」といった気質や特性との関係、向いている仕事の選び方など、多くの人が抱くモヤモヤを少しでもクリアにできる内容になっています。
【質問1】ADHDの人は事務作業を苦手ですか?
ADHDの傾向がある方は、頭の中でいくつものことが同時に浮かびやすく、注意力を一定に保つのが難しいと言われています(出典:参考文献)。
そのため、繰り返しの多い事務作業では「集中が続かない」「些細なミスをしてしまう」といった悩みを抱えることも少なくありません。
ただし、すべてのADHDの方に当てはまるわけではなく、例えば創造性や瞬発力が求められる場面では力を発揮するケースも多くあります。無理に苦手分野を克服しようとするより、自分の得意な場面を見極めて、働き方を見直す視点が大切です。
【質問2】HSPが苦手な仕事は?
HSP(繊細な気質をもつ人)は、音や光、人の感情など、周囲の刺激を敏感に感じ取る傾向があります(出典:参考文献)。
静かで一定の環境であれば集中力を発揮できますが、電話の鳴り続ける職場や、頻繁な声かけが飛び交うような環境では、エネルギーを消耗してしまいやすいでしょう。
たとえば大勢と関わる接客や、時間に追われる営業よりも、自分のペースで作業できるライティングや在宅ワークのような働き方が合っていると感じる方が多いようです。自分に合った環境選びが何よりの鍵です。
【質問3】事務作業が苦手なら営業に向いている?
事務が苦手=営業が向いているとは一概に言えませんが、人と話すのが好きだったり、体を動かしている方が楽と感じるなら、営業職は可能性のひとつです。
たとえば、お客様とのやりとりにやりがいを感じたり、外出が多い仕事の方が気持ちがラクになるなら、検討してみる価値はあります。ただし、営業にも数字管理や報告書作成など事務的な要素は付きものです。「話すことが苦ではないか」「プレッシャーに耐えられるか」など、自分の性格と照らし合わせて選ぶのが良いでしょう。
【質問4】事務作業が苦手なのは病気のサインなの?
「事務が苦手」と感じること自体は、誰にでも起こる自然な感情です。ただ、極端な忘れっぽさや集中の持続が難しいなど、生活や仕事に支障をきたすようであれば、発達特性(たとえばADHDなど)の可能性を考えてもよいかもしれません(出典:ADHDの定義と判断基準)。
とはいえ、即「病気」と結論づける必要はありません。日々の困りごとが続いていて「どうしてもつらい」と感じるなら、専門機関での相談も一つの選択肢。一人で抱え込まず、自分の状態を客観的に知ることが第一歩です。
【質問5】事務できない女でも働きやすい職場は?
「事務仕事が苦手だから向いてないのかも…」と悩む女性は少なくありません。でも、事務ができない=仕事ができない、ではありません。
たとえば、販売や接客のように人と関わることが中心の仕事、清掃や軽作業など黙々と動ける仕事は、むしろ得意分野を活かせるチャンスでもあります。働きやすさは仕事内容だけでなく、職場の雰囲気や上司との相性にも左右されます。まずは「できる仕事」より「無理なく続けられる仕事」を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ:事務作業が苦手な人の特徴と苦手を克服する対処法
事務作業が苦手な人の特徴と苦手を克服する対処法をまとめてきました。
改めて、事務作業が苦手な人の特徴10選をまとめると、
- パソコン作業が苦手で手間を感じやすい人
- 細かい確認作業や書類を扱うのが苦になる人
- 同じ作業の繰り返しに飽きやすい人
- 集中力が続かず作業をやり遂げづらい人
- 注意が散りやすくミスしやすい人
- 物忘れや確認の抜けも気になり集中できない人
- 優先順位をつける判断がしづらい人
- マルチタスクが苦手で一つに集中したい人
- じっと座って同じ姿勢を続けるのが苦しい人
- 黙々と人と話さず作業するのが苦手な人
そして、事務作業が苦手な人に伝えたい5つの重要ポイントもまとめると、
- 事務作業が苦手でも、自分の強みを理解すれば働き方の選択肢は広がる
- 苦手意識の克服には、チェックリストや整理整頓といった小さな工夫が有効
- 事務が合わないと感じたら、転職活動を通じて市場価値を見直すことが重要
- 求人サイトや転職エージェントの活用で、向いている仕事に出会いやすくなる
- 苦手を無理に克服するのではなく、得意を活かす方向へ視野を広げることが大切
事務作業が苦手だからといって、社会での自分の価値が下がるわけではありません。
向き・不向きを冷静に見つめ、自分に合う環境を探すことが重要です。適性を知り、強みを活かせる職場に出会えれば、「苦手」はむしろ次のステップへのヒントになります。